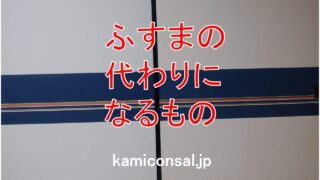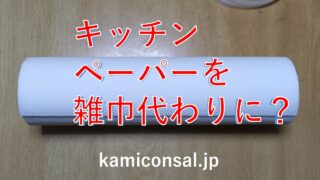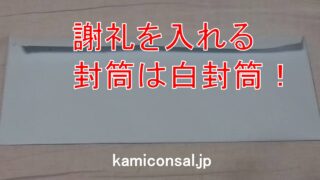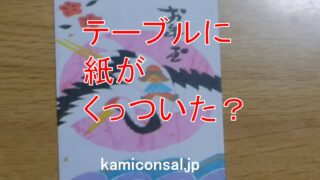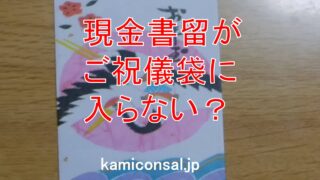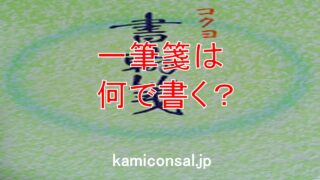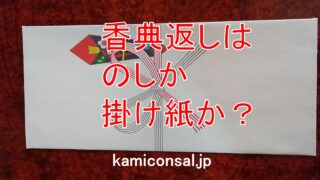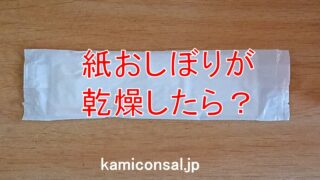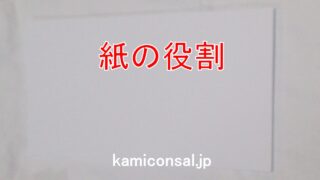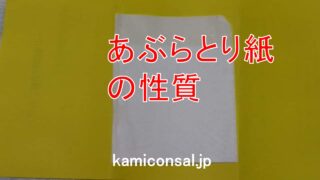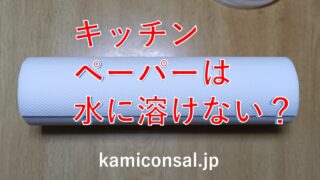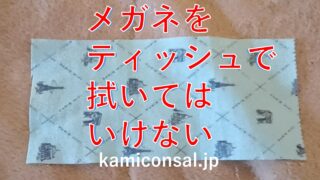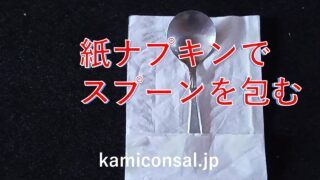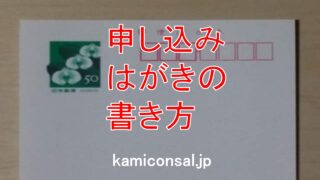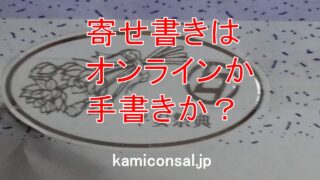管理人の紙コンサルこと、
べぎやすです。
このカテゴリでは紙を生活でどう使うか
についてお話したいと思います。
紙は生活の中で欠かせませんよね。
トイレットペーパーにしても
ティッシュペーパーにしても
当たり前に目の前にあるので
これを使わない生活は考えられない。
新聞をとっている人は
新聞があるのが当たり前だし、
赤ちゃんや病気の人で紙おむつが
必需品という場合もあるでしょう。
このカテゴリでは
紙が生活にどのように関わっているのか
管理人なりに調べたことを
お伝えしたいと思います。
【紙のある生活 トイレットペーパー】
生活する上でなくなって困るもの。
トイレットペーパーはその代表かなと。
災害が発生したときなど
食料も重要ですが排泄も重要。
トイレットペーパーがないと
困るんですよね。
ではいざという時どれくらい
トイレットペーパーを備蓄すればいい?
管理人はこれ計算したことがあります。
何ヶ月分備蓄すればいいか?
というのを調べたところ
経済産業省によると
「日常用のトイレットペーパーとは別に
1か月分程度のトイレットペーパーを
備蓄されることをおすすめします」
となってました。
こんなことでさえ指標が出るのが
日本のお役所らしい気がします。
それででは1ヶ月分はどれくらい?
ということなんですが
これは日本製紙連合会が
2001年に調査していて
1人あたり年間50ロールだそうです。
家族の人数とか男性か女性かなどで
世帯としての使用量は違いますが
とりあえず総務省の統計では
平成27年で2.33人なんだそうです。
1世帯あたり2.33人?
管理人は3、4人だと思っていたので
これはちょっと驚きました。
もう1人、2人の世帯が
62%にもなるんですね。
それはそれとして、
世帯あたりの平均人数で計算してみると
50ロールx2.33人÷12ヶ月=9.7ロール/月
となりました。
2人なら8.3ロール、3人なら12.5ロール。
1パックが12ロールなら1パックあれば
どうにか1ヶ月乗り切れるいう計算です。
生活必需品だけに冷静に計算して上で
備蓄しておきたいものです。
【紙のある生活 新聞紙】
次は新聞紙。
新聞紙は毎日読むのはもちろんですが
それ以外の二次利用が多いですよね。
見つけたものをいくつかあげてみます。
窓拭きに使う。
ホコリっぽい床をほうきで掃くときに
ちぎって撒いて掃除する。
風呂の湯が湯垢で汚れたときに
新聞紙を浮かべて垢を取る。
雨などで濡れた靴に詰めて湿気を取る。
ちょっと変わったところでは、
新聞紙を小さくちぎって水に濡らして
ジップロックに詰めて凍らせる。
これで保冷剤の代わりにする。
新聞紙に殺虫剤を吹き付けて
ゴミ箱のそばに置いておく。
これで虫が来ない。
屋外でロウソクが消えやすいとき。
1cm幅くらいの新聞紙をらせん状に
巻いておけばロウソクの火が消えにくい。
というのもありました。
野菜とかお花とかを包むときも
よく使ってますよね。
管理人は商品を送付するときの
緩衝材に丸めた新聞を使ってました。
捨てる前にもうひと仕事という
使い方が多いようです。
【紙のある生活 ティッシュペーパー】
次に生活の中にある紙といえば
ティッシュペーパー。
駅前を歩くとしょっちゅう
ポケットティッシュを配っています。
管理人もたまにもらうんですけど
何かのときに便利ではあるんですが、
その名の通りズボンのポケットに入れて
忘れて洗濯することがあるんですね。
ティッシュは湿潤紙力増強剤と
呼ばれる薬品が入っていて
水に濡れても溶けませんから
洋服がティッシュまみれになる。
結構悲惨。
なんとか上手く取れないか?
管理人はやったことないんですが
その方法はあるようです。
具体的には以下の通り。
用意するのはオクラなどの
入っている野菜ネット。
これに手袋のように手を入れる。
そして、ティッシュまみれになっている
濡れた状態の洗濯物を
新聞紙などの上において、
この野菜ネットでこする。
という感じ。
洗濯ネットの網目がちょうどいい感じで
ティッシュを取ってくれるようです。
【紙のある生活 紙おむつ】
間違って洗濯して悲惨なのは紙おむつ。
ティッシュの比ではないそうです。
紙おむつに使われている
高分子吸水ポリマーは
水を吸って1000倍以上膨らんで
ゼリー状になるんですね。
だから間違って洗濯すると
洗濯機も洋服もゼリーでドロドロ。
大変なことになるようですね。
管理人が調べた対応策。
メーカーの回答は、
洗った洋服に付着してしまった場合
1.脱水した後、乾かす前に
ブラシなどで落とす。
粘着テープで取り除くこともできます。
2.乾かした後ものこっている場合は
洋服をよく振って落とすか、
もう一度ブラシなどで取り除く。
3.時間に余裕がある場合は
脱水した後や乾かした後に
もう一度洗濯をします。
洗濯機内部に付着してしまった場合
1.くず取りネットに
入り込んだものを取り除く。
2.洗濯機内部は
ティッシュなどでよく拭き取る。
3.取りきるのが難しい場合は
1度水を溜めてすすぐ。
ということでした。
何だか面倒そうです。
なにか裏技ないかなということで
調べると出てきました。
塩を入れる!
量は大さじ3,4杯。
紙おむつを間違って洗ったと思ったら
塩を入れてもう一度洗濯する。
これで洗濯物も洗濯機も助かる
ということだそうです。
もちろんある程度取れるものは
取ったほうがいいですが。
それでこの原理は「塩析」と
呼ばれるものだとか。
水溶性ポリマーに電解質
(ここでは塩)を入れると
ポリマーが析出してくるのですが、
この現象を利用しているようです。
ポリマーに含まれている水が
塩水の方に出てきて
ポリマー中の水分が無くなるので
ブヨブヨのゼリーが収縮する感じ。
細かいところは違うのですが
梅干しを漬けるとき塩を入れると
梅から水が染み出してくるのと
イメージとしてはよく似ています。
塩水で洗った後はもう一度
普通に洗い直すほうがいいでしょう。
それから衣服に多少残っていても
乾燥したら粉に戻るので
乾燥後にキレイにふるえば
大体は大丈夫です。
そもそも紙おむつなのですから
少々人間の肌に接触しても無害。
極端に神経質になることはないでしょう。
洗濯機が塩水で錆びるのではないか
という心配もあります。
それに排水管で詰まるかも知れません。
通常その程度で錆びることは
ないと思われますが
念のため洗濯槽のクリーニングは
やったほうがいいでしょう。
大量の水で流してしまえば
排水管もきれいになるでしょうし。
【管理人のまとめ】
今回は紙のある生活について
お伝えしました。
トイレットペーパー、新聞紙、
テッシュペーパーに紙おむつ、
紙は生活に欠かせないものに
なっています。
紙は安くて便利なもの。
だからうまい使い方やトラブル回避法を
知った上で使って欲しいと思います。
紙を使って豊かな暮らしを
楽しんで下さいね!