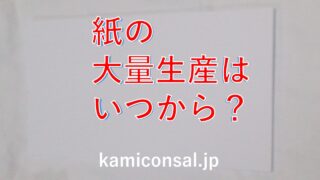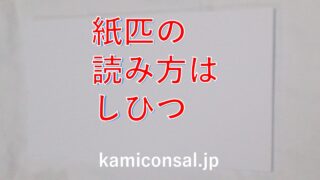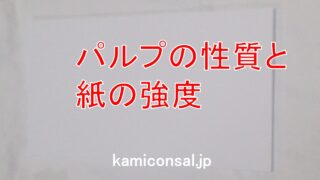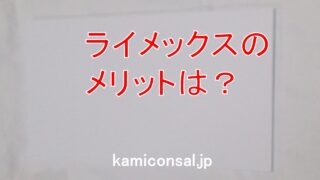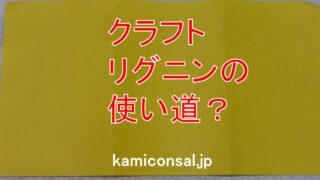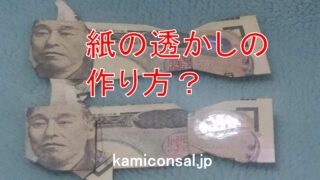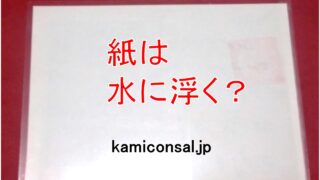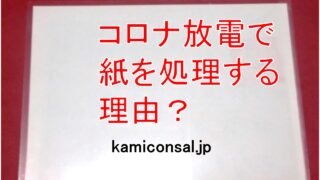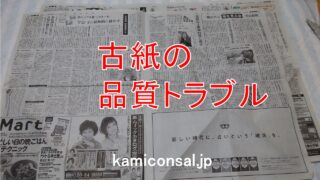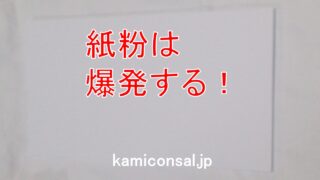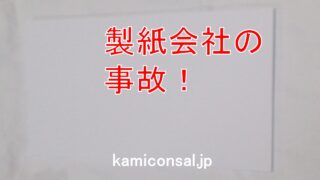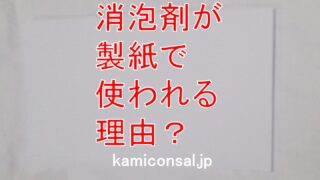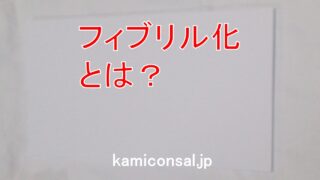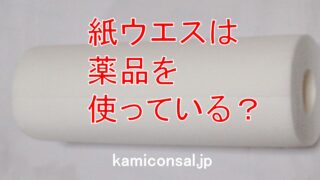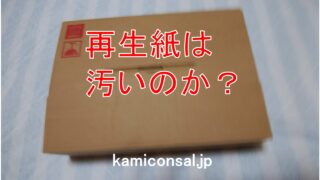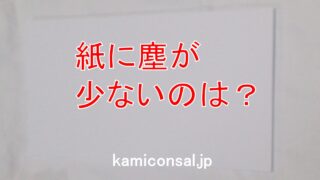管理人の紙コンサルこと、
べぎやすです。
このカテゴリでは紙の製造方法
についてお話したいと思います。
就職活動で製紙会社が気になる
理工系の人も中にはいるかと思います。
管理人は元製紙会社社員ですから
紙の製造には色々関係しました。
直接自分が担当したものもあれば
研修で教育を受けたものもあります。
実は紙なんて年中同じことやってて
技術の進化なんてないだろう
なんて思ってたんですけど
それは大間違いでした。
ITのような急激な変化はないですが
それでも環境に合わせた変化はある。
製紙産業は装置産業で
一旦機械を導入すれば
簡単に設備の変更はできないので
変化は緩やかではありますが
そんな中でも設備は改造されるし
新規の薬品も開発されていく。
管理人が入社した平成元年から
現在を見たときの変化だけでも
古紙配合率は上がりましたし
中性抄紙化も進みました。
コート紙は安価になり
チラシに使えるようになりました。
新聞紙は軽くなりました。
このカテゴリでは紙の製造について
管理人の体験を交えてお伝えします。
【紙の製造方法 コート紙の場合】
今やチラシは塗工紙がほとんど。
スーパーのチラシなどは
光沢のあるコート紙
不動産や霊園などは
マットコート紙が多いでしょうか。
昔はもっとキザラや上質紙が
多かったように思います。
本当に塗工していない紙は減って
身近ではコピー用紙やノートくらい。
漫画や週刊誌は中質紙や
更紙もありますが
ゲームやアニメ関連の雑誌などは
コート紙または微塗工紙。
文庫本や教科書用紙でさえ
今は微塗工紙になってます。
それにしても。
コート紙は元々高級品で
特殊紙だったんです。
写真集とか美術品のカタログとか
そういう用途に使うものだったんです。
それがどんどんコストダウンして
品質はそこそこ良くて安い紙に。
今では無料で配るチラシにも
使われるようになりました。
技術の進化という意味では
カッコよさとか派手さとか
そういうのは全然ないんですが、
広く普及するというのも一つの方向。
紙の場合は薄利多売が可能な方向に
技術が進化したと言えるでしょう。
こういうことが可能になった要因は?
管理人は塗工速度の
高速化だと思っています。
通常のコート紙はブレードコーターと
呼ばれる塗工機で塗工されます。
ブレードというのは刃物のことです。
原理は単純で紙に塗料を吹き付けて
それをブレードでかき取る方法。
塗工方式というのはたくさんあるんですが
速度が速いのがブレードコーター。
ロールとかロッドとかエアナイフ、
ダイコーター(カーテンコーター)など
色々な種類があるんですが
特許の問題があるとか速度が遅いとか
ただ紙に塗料を塗るだけですが
色々ややこしかったですね。
それでブレードコーターの原理が単純
といってもキレイに塗れるかは別問題。
特に高速でキレイに塗るのは難しく
ブレードと塗料の性能向上が必要。
もちろん塗工原紙の品質も重要です。
こういうものを少しずつ改善し、
塗工速度500m/分程度だったのもが
1500m/分程度で塗工出来るように
なっていたと思います。
管理人在籍時でその速度でしたから
今はもっと高速化しているはず。
なにしろ16年勤務している間に
塗工速度は3倍になりましたから。
製造されるコート紙の品質は
あまり変わっていませんが、
製造方法は地味に少しずつ進化して
塗工速度は約3倍になったわけです。
技術の進化というのは色々ありますが、
安く作る技術というのもあるんですね。
塗工速度が3倍になるということは
固定費も大幅に下るということ。
単純に1/3になるわけではないにしても
相当なコストダウンです。
ちなみに当時のコーターが1台60億円程度
だったと思いますから、
固定費の低減がどれほど大きいかが
分かるんじゃないでしょうか。
品質を変えずに安く作る技術。
あまりにも地味ですが
重要なことだと思います。
【紙の製造 新聞紙の場合】
新聞紙も品質の変化が分からないよう
徐々に変わっています。
たとえば軽量化。
新聞紙の米坪(1㎡あたりの紙の重さ)は
もともと52g/m2(重量紙)だったのが
1972年に49g/m2(普通紙)
1981年に46g/m2(軽量紙)
1990年に43g/m2(超軽量紙)
2000年に40g/㎡(超超軽量紙)
と軽量化されています。
現在の主流は43g/㎡だそうです。
元々の52g/㎡からすると43g/㎡なら
9g/㎡も軽量化されているわけです。
だいたい2割。
軽量化した理由は新聞配達員の
負担軽減と言われていましたね。
管理人は新聞社がページを
増やしたかったからだと思っています。
なにしろ紙は重量取引。
同じページ数でも米坪が下がれば
購入金額は減るわけですから。
製紙会社側はこの要求に応えるために
色んな対策をしたんですね。
たとえば強度と裏抜け。
米坪が下がれば紙の強度は落ちるので
その対策に表面のサイズプレスで
紙力増強剤(澱粉、PMA、PVAなど)を
塗工したりしています。
なおサイズプレスという装置は
抄紙の乾燥の途中に設置されていて
ロールなどで紙に塗工すること
が出来る設備です。
また米坪が下がれば紙が
薄くなって裏抜けするわけですが
その改善のために様々な薬品を
内添(パルプと混ぜて紙にする)し、
裏抜け対策のために
使用しています。
管理人が在籍していた頃は
ホワイトカーボン(シリカの微粒子)や
ユーパール(尿素樹脂の微粒子)を
使っていました。
最近では中性抄紙化が進んだので
炭酸カルシウムの微粒子が使えます。
新聞紙の場合約20年の時間をかけて
米坪52g/㎡を43g/㎡に下げたわけで
ユーザーが気が付かないペースで
技術は進化しているということです。
【管理人のまとめ】
今回は紙の製造について
お伝えしました。
紙なんて何の技術開発があるんだろう
そんなふうに思ってました。
しかしそれはそれは大きな間違いで
見えない所で変化は起きている。
ペースが緩慢なので分かりにくいですが
着実に進化してるんですね。
ここではコート紙の高速化や
新聞紙の低米坪化を例にしましたが
他の紙でも同様の進化は起こっており
各社とも対応しているということです。
本当にすごい技術は
あっという間に広まりますが
地味なコストダウンなどは
ゆっくり進行してなかなか広がらない。
しかしその部分が生き残るかどうかを
分けているようにも思います。
新聞、チラシ、コピー用紙など
結構紙には囲まれていますから
たまには紙の製造技術の
進化のことも思い出して下さいね!