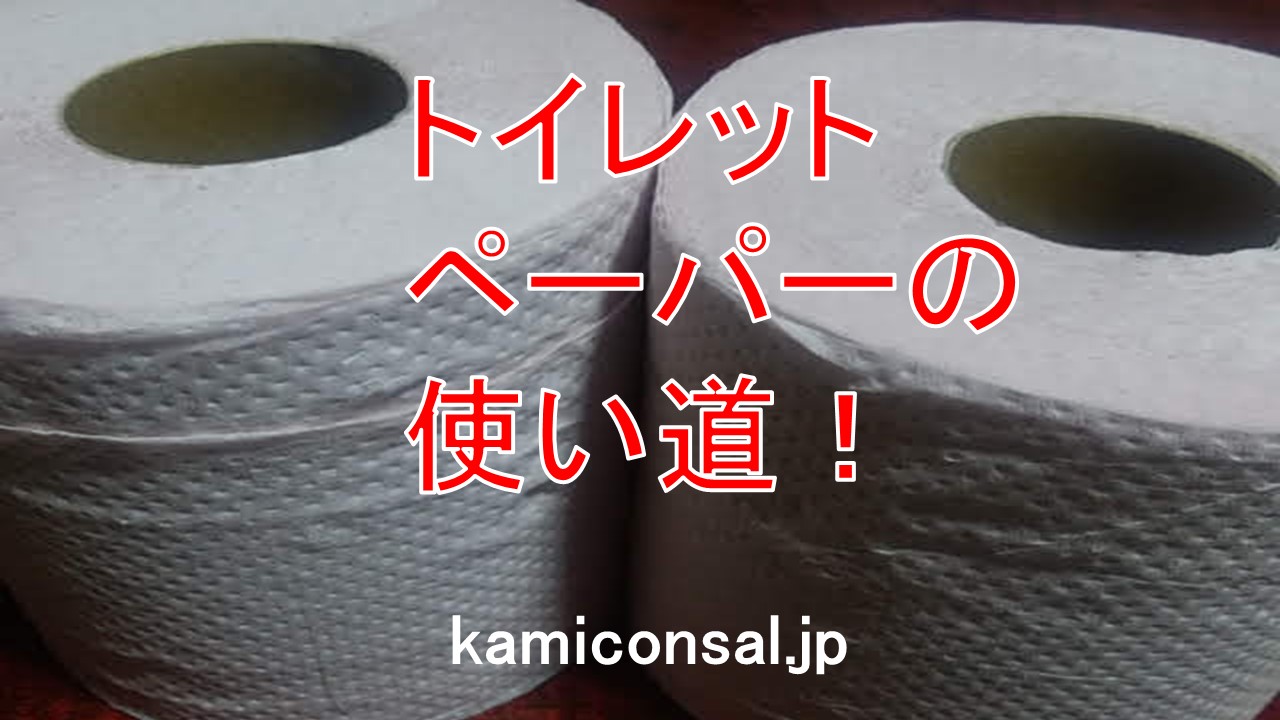この記事は約 7 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、紙の白色度と節水の関係。
十分な水がないと白さが出ない理由
というお話。
管理人は元製紙会社社員。
製紙会社でどれほどの水を
使うかはある程度知ってます。
製紙産業の場合はあらゆる場面で
水を使うことになるんですよね。
原料製造のパルプ工程、
原料供給する原質工程、
紙を製造する抄紙工程
どの工程でも使います。
だいたい、製紙工程なんて
木材を水に分散させて
その分散液を脱水する
と言う作業なんですよね。
ものすごく大雑把な言い方ですけど。
製紙工程なら約1%程度のパルプ分散液を
最終的には水分率6-7%くらいの紙にする。
結局90%以上の水を蒸発させるわけ。
この水が紙に影響しないわけがない!
ということで。
この記事では、紙の白色度と節水の関係。
十分な水がないと白さが出ない理由について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
紙の白色度は水が濁ると低くなる。節水すると水は濁る?
だいたい想像できると思いますが。
紙の白色度は使う水が
濁ると低くなります。
なにしろそもそも紙は99%は水で
そこから脱水するわけですから。
少しでも水が濁ればその影響は大きい。
それで。
問題は節水ですね。
たとえば夏場になってダムが干上がって
川の水の取水制限がかかったとします。
普段なら何の問題もなく使える水が
取水制限がかかって使えなくなる。
そうすると一度使った水を
再利用することになります。
工場内での水のリサイクルですね。
ここが問題になります。
今の技術を使えばリサイクルした水も
川から取水した水並にキレイに出来る。
しかしですね。
そんなことをしていたら
コストがかかって仕方ない。
ある程度きれいな水になれば
それを使うことになるわけです。
結局、再生水はコストが
かかる上にキレイじゃない。
製造する側としては
出来れば使いたくない。
そういえば。
環境問題で用排水のクローズド化なんて
話はしてましたけどコストが合わない。
どこまで行っても再生水は再生水。
限られたコストの中で限界まで
キレイにしても清水にはならない。
ここで言う「清水」は
川から取水した水です。
それでも取水制限がかかれば
再生水を使うしか無い。
当然製造工程に影響が出ます。
紙の最終品質に影響しないよう
考えて使うわけですけど無理もある。
たとえば。
新聞紙とか更紙、中質紙のような
白色度が低い紙はなんとかなる。
もともと白いパルプと黒いパルプを
混ぜて紙の白色度を決めますから。
しかし。
上質紙はなんともならない。
上質紙の原料は基本はLBKPのような
白いパルプだけになっています。
なので節水の影響が大きくんなる。
基準値より低い製品は出せませんが
ギリギリの下限のものが多くなる。
最終消費者が見て分かるような
白色度の低下はありません。
しかし、測定すれば数値に出る。
本当に上質系の紙は大変でしたね~
それに。
白色度の低い紙は白いパルプの割合を
増やして対応するわけですけど、
そうなるとパルプ配合を若干でも
変更しないといけなくなる。
もちろん品質を確保できるように
ある程度の変動幅はありますけど
計画していた数量から増減が
発生するわけで調整が必要になる。
節水率が上がるほど現場彩度では
やりくりが大変になるというわけ。
お天気の問題ですから
如何ともし難いですけど。
製紙工場の節水は何%程度まで出来るのか?
ここからは余談です。
管理人が実際に体験したことですが。
渇水時の節水が65%節水に
なったことがありました。
半分以上の水をリサイクルして使うと。
これはとんでもないんですよね~
普段から水を大事にと言っている
工場でしたがここまでくると
操業自体に支障が出るかも
という感じになってました。
大型マシンは止められないので
小型マシンを何台か止めるかとか。
その時はしばらくして雨が降ったので
助かったんですがその後どうなのか?
対策できていればいいんですが
用水の対策は簡単ではありません。
自治体との取り決めとかがあるので
水利権って相当面倒なんですよね。
多分今でも似たような状況かなと。
管理人的には輸入できなくて
原料が不足するよりも
渇水で生産がままならないほうが
怖いんじゃないかと思ってましたね~
管理人のまとめ
今回は紙の白色度と節水の関係。
十分な水がないと白さが出ない理由
というお話でした。
紙は水で作るわけですけど
本当に水不足は大変です。
節水になって再生水を使うとなると
水が濁って白色度が落ちてしまう。
上質紙は白色度の下限値で
中質紙や更紙も配合が変わる。
色々負担が増えてしまうんですよね。
再生水をもっとキレイにと言うのは
正論ですがコストが合わない。
現実的ではないわけです。
製紙工場が渇水を乗り切るのは
本当に大変なんですよね~
この記事が、紙の白色度と節水の
関係の参考になればと思います。
水が十分に使えるっていいですよね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
紙でリグニンが取り除かれる理由?退色や劣化を防ぐためです
⇒https://kamiconsal.jp/kamirigunin/
紙の原料になる木の種類とは?植林したユーカリや松が多い!
⇒https://kamiconsal.jp/kamigenryokisyurui/
感熱紙と普通紙の違いとはなに?熱で発色するかどうかです!
⇒https://kamiconsal.jp/kannetusifutusi/