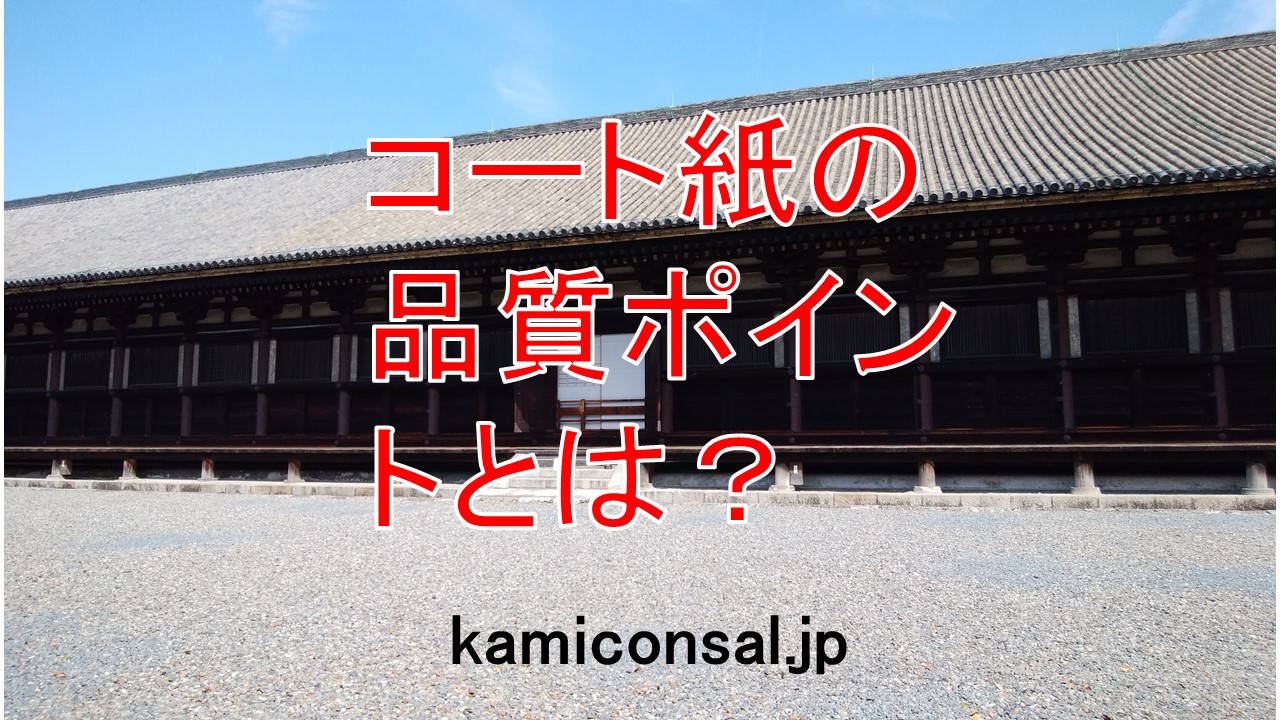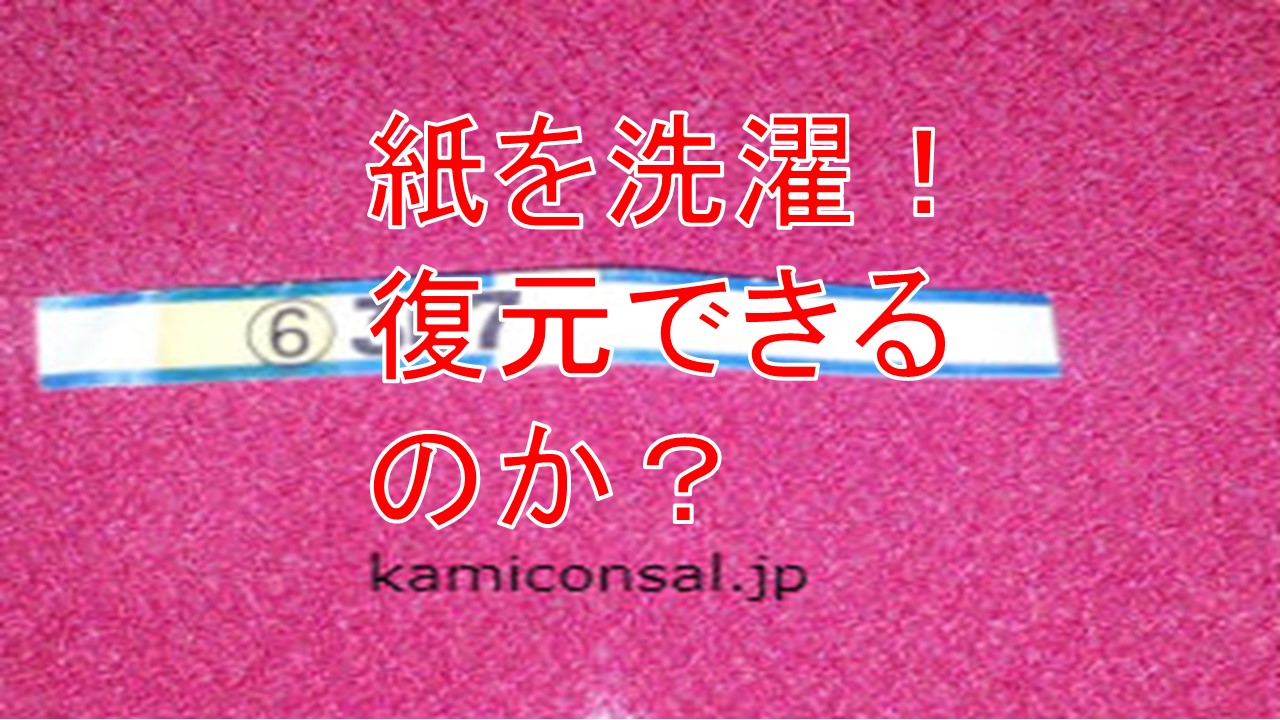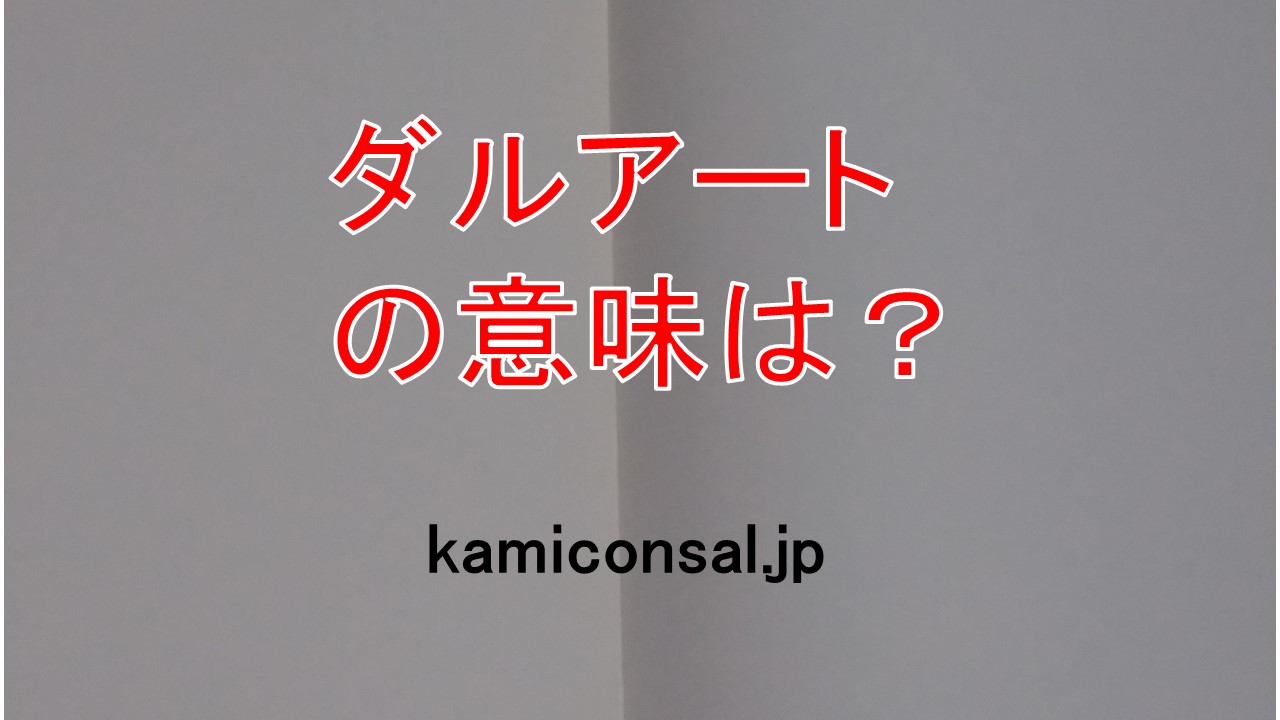この記事は約 11 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
コート紙と聞くと、皆さんはどんな用途を思い浮かべるでしょうか?新聞の折込チラシやカレンダー、雑誌、ポスターなど、実は私たちの身の回りには非常に多くの場面で使用されています。今回は、コート紙の品質レベルについて、特に「印刷仕上がり」がどれほど重要かを深掘りしてご紹介します。元製紙会社の社員としての経験も交えつつ、印刷業界や紙に関わる方にとって有益な情報をお届けします。
管理人が見てきたコート紙の現場と時代背景
私が製紙会社に入社したのは平成元年、つまり1989年のことでした。当時の日本はバブル経済の絶頂期にあり、あらゆる業界が活気に満ちていました。紙の需要も非常に高く、とりわけ印刷用紙の分野では新しい設備投資が盛んに行われていた時代でした。私の勤め先でも、最新鋭のコーター(塗工機)が導入され、コート紙の大量生産体制が整いつつある状況でした。
この頃は「紙の未来は明るい」と本気で信じていたものです。新聞や雑誌の発行部数も多く、広告チラシやポスター、カレンダーなど、紙を媒体とした情報伝達手段が当たり前の時代。特にコート紙は、滑らかな表面と高級感のある質感が評価され、多方面で使われるようになっていました。写真集や美術書、旅行パンフレットなどのビジュアル重視の印刷物にもコート紙の需要が高まり、製紙工場の稼働は常にフル回転状態でした。
今振り返れば、インターネットもスマートフォンもまだ存在しなかった時代。紙が情報の中心を担っていたのは当然といえば当然のことだったのかもしれません。しかしその反面、将来的に紙の需要が落ち込む可能性など、誰一人として本気で考えていなかったのも事実です。デジタル化の波が押し寄せる前夜、私たちは紙の黄金時代の真っ只中にいたのです。
コート紙の品質レベルは「印刷仕上がり」が命
コート紙の品質評価において、最も重視されるポイントは何かと問われれば、私は自信を持って「印刷仕上がり」だと答えます。というのも、コート紙とは、本来印刷効果を高める目的で表面に塗工処理を施して作られた紙であり、印刷結果こそがその品質を語る最大の指標だからです。
具体的には、「印刷光沢」や「平滑性」「インクののり具合」などが重要な評価軸となります。印刷光沢とは、印刷後の用紙表面がどれだけ光を反射するかを示す数値で、光沢計という測定器を使って定量的に評価することができます。光沢値が高ければ、それだけ見た目にインパクトがあり、高級感のある印象を与えられるため、カタログや広告用紙などでは特に重要視されます。
しかしながら、単に光沢が高ければ良いというわけではありません。実際、光沢が強すぎると、ギラギラとした印象を与え、逆に品位を損ねてしまうこともあります。たとえば高級ブランドの冊子やアート写真集などでは、あまりに光沢が強すぎると「安っぽい」と感じられることもあるのです。印刷された面が均一に光を反射し、やさしく上品な輝きを放つ——そうした繊細な仕上がりが求められることも少なくありません。
このように、数値では測れない「見た目の美しさ」や「質感の上品さ」といった感覚的な要素が、コート紙の品質評価において非常に重要な位置を占めているのです。
「上品さ」は誰が評価するのか?
コート紙の印刷仕上がりに対する「上品さ」や「高級感」は、数値では完全に表現できない部分です。こうした感覚的な品質をどう評価するのか——そこで用いられるのが「官能試験」と呼ばれる方法です。これは、実際に印刷された紙を複数の評価者に見てもらい、各自の主観で評価点をつけるという手法です。
しかし、この官能試験には難しさも伴います。評価者の性別や年齢、さらには文化的な背景や美的感覚によって、評価基準が大きくばらつく可能性があるからです。たとえば、若年層向けのファッション誌で使用される紙を評価する場合と、重厚感ある車のカタログで使用される紙を評価する場合とでは、見る人の目がまったく異なるのです。
若い女性向けの雑誌では、柔らかい質感や優しい発色が好まれる一方、男性向けの機械製品カタログでは、シャープでくっきりとした印刷品質が求められます。つまり、製品ごとのターゲット層に応じた評価軸を持つ必要があり、それに合わせてコート紙の種類や塗工処方を調整するのも、製紙メーカーの重要な仕事のひとつなのです。
結果的に「上品さ」とは、見る人と用途に合わせて初めて成立する相対的な概念であり、絶対的な評価基準を持たない、非常に奥深い品質項目だといえるでしょう。
印刷光沢を上げるための製造上の工夫
印刷光沢を高めるためには、紙の表面をできる限り平滑に整えることが欠かせません。これは印刷されたインキが均一に乗るための重要な前提条件であり、結果として高い光沢感を実現する要素になります。この表面の平滑性を得るために、塗料の中に含まれる顔料の粒子径を微細化する工夫がなされます。粒子が細かくなればなるほど、紙表面の凹凸が少なくなり、光の反射も整うため、見た目の光沢度が飛躍的に向上します。
しかし、粒子径を小さくしすぎると、製造工程におけるさまざまなトラブルのリスクが高まります。たとえば、塗工機での塗料の搬送性が低下したり、紙面への塗布が均一にならなかったりといった問題が発生します。また、微粒子の扱いには高度な技術と設備が必要であり、操業性の低下や歩留まりの悪化などの課題を招くこともあります。
加えて、白紙状態では光沢が向上しても、実際に印刷された後のインキ光沢が思うように出ないというケースも珍しくありません。このような場合、印刷後の光沢感を高める手段としてラテックス系バインダーの配合量を増やす方法がありますが、これにはコスト上昇という明確なデメリットがあります。量を増やせば増やすほどコストが嵩み、製品価格とのバランスが取りづらくなってしまいます。
また、光沢向上のための手段として針状の特殊顔料(代表例として「サチンホワイト」など)を導入する試みもあります。これにより、顔料の配向性が高まり、表面に独特の光沢が生まれる可能性があるのですが、その一方で塗料のpHが変動し、安定した操業が困難になるケースもあります。結果として、印刷光沢の改善を目指したはずが、製造現場の調整負荷を増やしてしまうというジレンマに陥ることもあります。
印刷仕上がりを支える「塗工原紙」の品質
印刷の仕上がりにおいて、光沢以外にも「上質感」や「品の良さ」といった要素が求められることが多くあります。こうした印象を左右するもう一つの大きな要因が、「塗工原紙」の品質です。塗工原紙とは、塗料を施す前の土台となる用紙のことで、一般的には上質紙やその変種が使われます。この原紙がしっかりと作られていないと、どれだけ優れた塗料を塗っても効果が発揮されにくくなります。
中でも重要なのが「地合い」と呼ばれる、紙の繊維の分布状態です。地合いが均一であれば、塗料が紙面に均一に広がり、塗工面の滑らかさや平滑性が向上します。逆に、繊維の密度が場所によって異なるような地合いの悪い紙だと、塗料の乗り方にもムラが出てしまい、結果として印刷後の仕上がりにも影響が現れてしまいます。
紙の地合いは、抄紙機の設定やパルプの配合、繊維の長さ・水分量・流れなど、さまざまな要素によって左右されます。製造工程で少しでもバランスを崩すと、紙全体の品質が落ち、印刷に適さない素材となってしまいます。塗料の工夫だけでなく、原紙の品質をいかに安定して供給できるかが、最終的な印刷結果を大きく左右するのです。
印刷品質は製紙工場の総力戦
優れた印刷品質を実現するためには、塗料の設計や印刷技術の向上だけでは十分とは言えません。むしろ、それ以前の段階である紙の製造、すなわち抄紙工程からすでに品質への取り組みが始まっているのです。抄紙工程では、パルプの選定から始まり、紙の厚み、密度、乾燥方法など多くの要素が関与します。
特に、使用するパルプの繊維長や漂白度、さらには針葉樹と広葉樹の混合比率などが印刷品質に大きな影響を及ぼします。これらの調整は非常に繊細であり、わずかなズレが紙の感触や見た目の均一性にまで影響を及ぼします。優れた塗料が開発されても、それを受け止める土台の紙が良くなければ、最終的な印刷物の品質は期待通りにはなりません。
このように、コート紙の品質とは、一つの部署や技術だけではなく、工場全体の組織力と経験に支えられています。工程ごとに専門性の高いスタッフが連携し、試験や改善を繰り返しながらようやく理想的な紙が完成するのです。これは、簡単に模倣できるものではなく、各現場の「地力」とも呼べる継続的な努力と技術の蓄積があってこそ成り立つものなのです。
コート紙の印刷品質を考えるときに意識すべきこと
- 単に印刷光沢の数値が高いからといって、必ずしも「良い紙」とは限らない
- 印象に残る上品な仕上がりは、数値では測れない感性や官能評価によって判断される
- 塗料の改良だけで全てを解決できるわけではなく、コストや製造限界という現実的な壁も存在する
- 紙そのものの基礎的な品質、特に地合いの良さが印刷仕上がりの成否を分ける
- 印刷用紙としての完成度は、製紙から塗工まで一貫した製造現場の技術力と連携力によって支えられている
まとめ:コート紙の品質とは企業の総合力の証
この記事では、コート紙における「印刷仕上がり」を通して、品質の本質を深掘りしてきました。光沢といった目に見える定量的な要素だけでなく、「上品さ」「肌ざわり」「ムラのなさ」といった感覚的な部分にも大きな価値が存在しています。これらは、単なる技術開発では実現できない、長年の知見と現場力の結晶ともいえるでしょう。
塗料の配合比率や機能性の工夫、操業条件の最適化、原紙品質の安定、そしてコストバランスまで、コート紙の製造は一つひとつの工程が密接に関わり合う複雑なプロセスです。その背後には、現場の技術者や職人たちが培ってきた知識、経験、そして何よりも製品に対する誇りが存在します。
ポスターやカタログ、雑誌など、私たちの生活の中で何気なく使われている印刷物。その背後には、ここまでの技術と努力が詰まっています。次に印刷物を手に取る際は、ぜひその「仕上がり」の美しさに注目してみてください。コート紙という素材の奥深さに気づき、印刷の世界がより豊かに感じられるはずです。