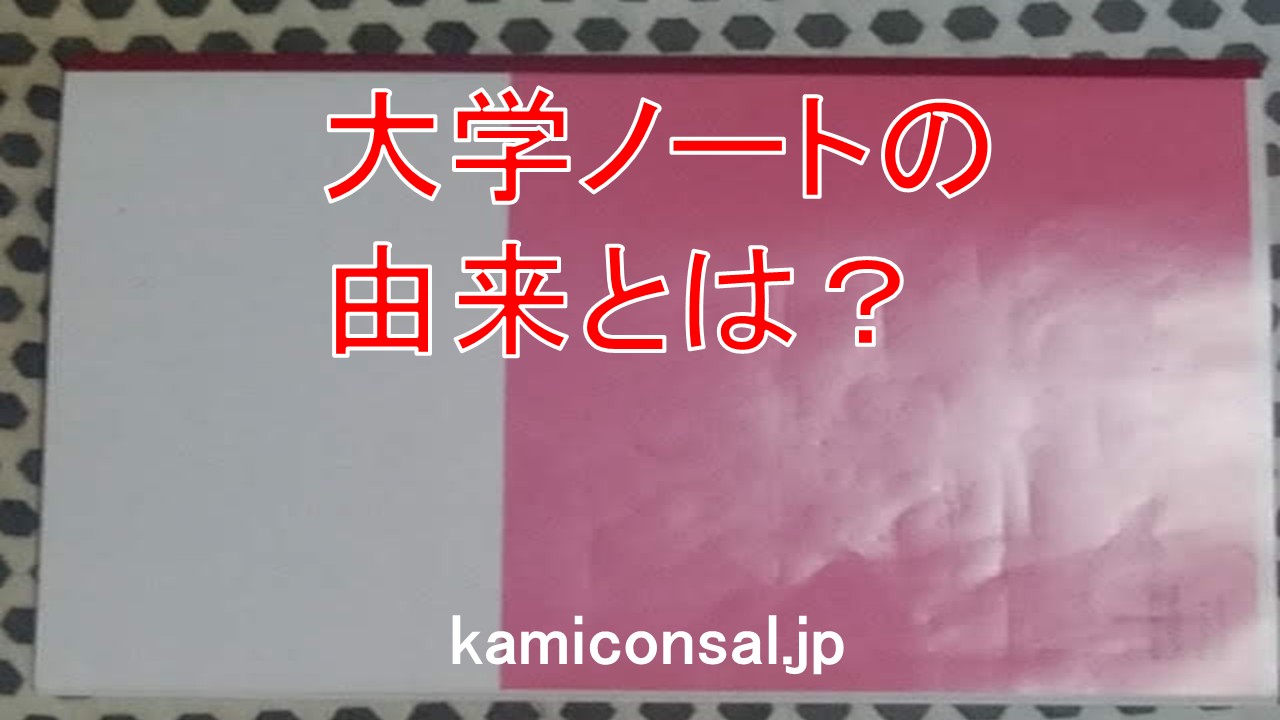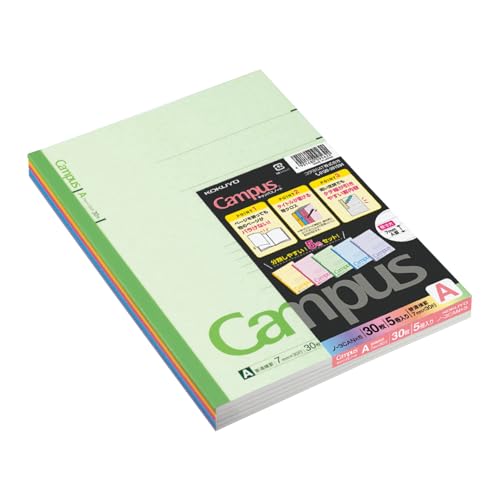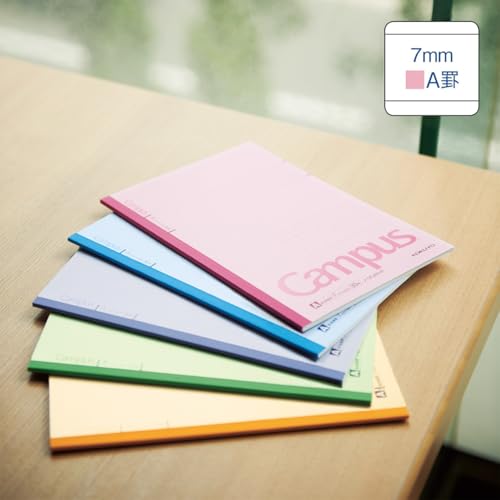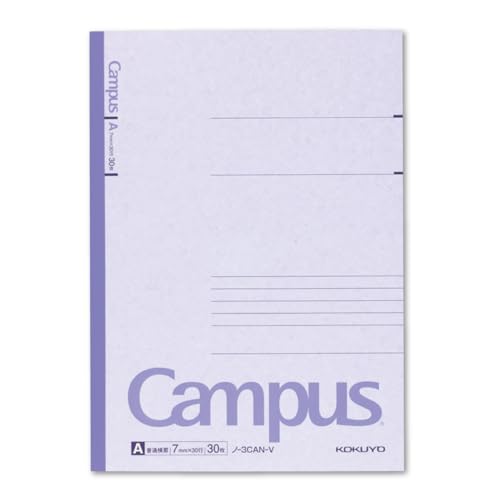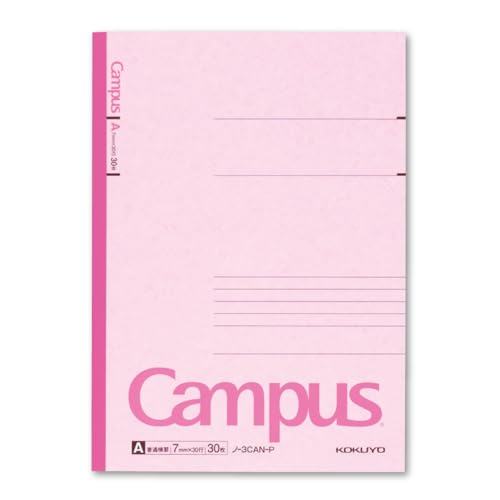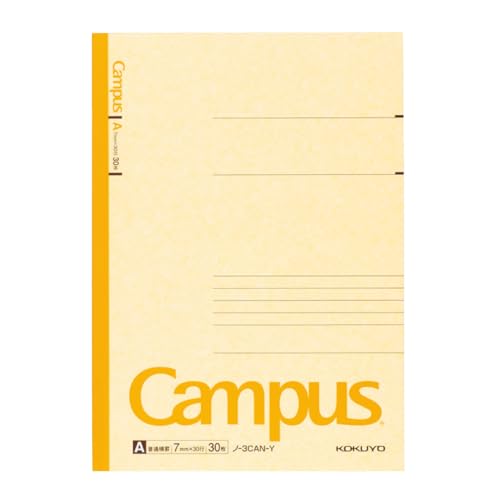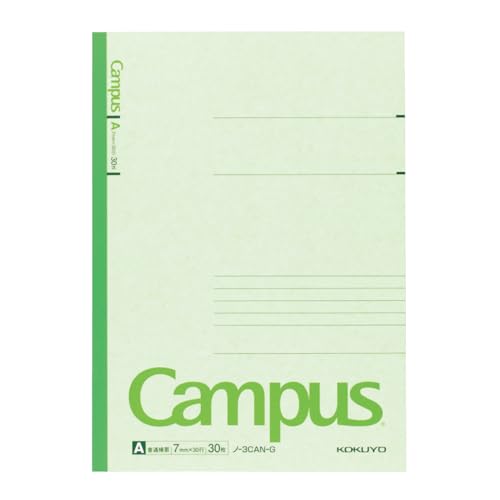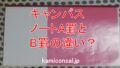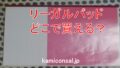この記事は約 9 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、大学ノートの由来。
明治に洋式ノートが導入され大学で使われた
というお話。
管理人も大学ノート使ってます。
これですよね。
コクヨ ノート キャンパスノート 5冊パック 5色アソート B5 A罫 30枚 ノ-3CANX5
子供の頃から使っています。
でもそういえば。
大学で使うから大学ノートだと
思っていましたが子供も使う。
そもそもなぜ大学ノートなのか?
ちょっと気になるんですよね~
ということで。
この記事では大学ノートの由来。
明治に洋式ノートが導入され大学で使われた
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
大学ノートとは?その定義と特徴
大学ノートとは、一般的にB5サイズやA4サイズといった標準的なサイズで作られた、無線綴じ(のり綴じ)タイプのノートのことを指します。
その名前の通り、多くの大学生が講義中のメモやノート取りに使用することから「大学ノート」と呼ばれるようになりました。
紙質がしっかりしていて、インクがにじみにくく、筆記しやすいのが特徴のひとつ。また、サイズも持ち運びにちょうど良く、リュックやカバンにもすっきり収まるサイズ感となっている点も人気の理由です。
さらに、表紙が比較的硬くて丈夫なので、外での筆記時にも安定感があり、書きやすさが損なわれにくいというメリットがあります。
ノートの中身には、太さの異なる罫線が引かれていたり、目に優しい色味の紙が使われていたりと、学習効率や作業効率を高めるための工夫も多く見られます。
ただし、「大学ノート」という名称は日本独特の呼び方であり、海外ではこの呼び名は通用しません。その背景には、歴史的な経緯や文化の違いがあります。
次に、その由来をひもといてみましょう。
大学ノートの名前の由来
大学ノートという名前は、明治時代の日本に導入された「洋式ノート」に起源があります。
当時、日本は明治維新を経て西洋化を進めており、学問や文化、生活様式に至るまで欧米から多くの要素を取り入れていました。
そうした中で、西洋から持ち込まれたノートという新しい文房具もまた、日本に紹介されることになります。
これらのノートは、特に高等教育機関である大学で学ぶ学生たちにとって必要不可欠な学習ツールとなり、徐々に広まっていきました。
その結果、「大学で使われるノート」という意味合いを込めて「大学ノート」と呼ばれるようになったのです。
ちなみに、このノートの形状やデザインは、イギリスやドイツなどの学術書類をモデルにしていたとされ、罫線の形式や製本方法にもその影響が見て取れます。
日本国内でノートが広く使われるようになった背景には、学問の発展と西洋文化の浸透が大きく関わっており、当時の人々にとって「大学」という言葉は知的で信頼性の高い響きを持っていたのです。
そのため、この呼称が定着し、現在でも使われ続けているのでしょう。
日本での普及と進化
大学ノートが日本国内で本格的に普及するきっかけとなったのは、文房具メーカーの積極的な製品開発と販売によるものでした。
ウィキペディアの記述によると、
==ここから==
東京大学の前の松屋という文房具屋で1884年(明治17年)に売り出されたことからその名がついたといわれている。当時としては珍しい洋紙(フールスキャップという)が使われ、表紙に細かい毛が入った紙を使用していた。
==ここまで==
ということで、非常に早い時期から洋紙を使ったノートが販売されていたようです。
ただし、実際に「大学ノート」という名称を広く浸透させたのは、誰もが知っている文房具メーカー「コクヨ」の存在が大きかったと考えられます。
同じくウィキペディアによれば、
==ここから==
1975年に、業界に先駆けて「無線綴じノート」を開発し、Campusを発売。その後「大学ノート」が広く使われるようになった時代から、学生向けのノートを本格的に作り始めた。なお、2022年12月末時点で、国内販売冊数は累計約35億冊となっている。
==ここまで==
ということで、コクヨの「Campus」ブランドの登場は、日本の学生たちの学習スタイルに大きな影響を与えました。
国内には数多くの文房具メーカーが存在しますが、「大学ノート」と聞いてまず思い浮かべるのは、やはりこのキャンパスノートでしょう。
管理人も初めてこのノートを手にしたときは、なんだか「自分も大人の仲間入りをした」ような、不思議な感覚を覚えたものです。
現代の大学ノートとその活用法
現代の大学ノートは、昔ながらのシンプルな罫線入りノートだけではなく、多様なニーズに応じた様々なバリエーションが展開されています。
例えば、以下のようなタイプが人気です。
- ドット罫ノート:等間隔に配置された点線によって、アイデアの整理やマインドマップの作成、図解に非常に便利。プレゼンや会議のメモにも向いています。
- 方眼ノート:方眼のマス目があることで、数式の計算やグラフ作成、建築やデザイン系の図面作成に適しており、理系学生や技術者に重宝されています。
- 無地ノート:罫線がないため、自由な発想でイラストを描いたり、デザインスケッチをするのに最適。アート系や企画職の方によく使われています。
また、近年ではタブレットやPCの普及により、デジタルツールが学習や仕事に欠かせない存在となる一方で、「手で書く」という行為そのものの価値が再認識されつつあります。
手書きによって記憶の定着が促進されたり、アイデアが生まれやすくなるという研究もあることから、アナログノートの魅力は根強く支持されています。
さらに、紙のノートに手書きしつつ、それをスマホやクラウドに保存できる「スマートノート」のような製品も登場しており、紙とデジタルの融合が進んでいます。
こうして、大学ノートは時代に合わせてその役割や姿を変えながらも、今なお多くの人に支持され、活用され続けているのです。
管理人のまとめ
今回は大学ノートの由来。
明治に洋式ノートが導入され大学で使われた
というお話でした。
大学ノートは、明治時代に西洋から
導入された洋式ノートを起源とし、
主に大学の教育現場で使われた
ことからその名が付けられました。
以来、時代とともに進化を遂げながら、
学生だけでなく幅広い世代に愛される
文房具となっています。
ノートそのものの歴史や文化的背景を
知ることで普段使っている大学ノートにも
新たな視点を持つことが
できるかもしれません。
大学ノートは単なる道具以上に、
私たちの学びや仕事を支える重要な
パートナーと言えるでしょう。
そのルーツに思いを馳せつつ、
日常での活用を見直してみるのも
良いかもしれませんね!
この記事が大学ノートの由来の
参考になればと思います。
大学ノート、上手く使ってくださいね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
余ったノートの使い道!捨てずに賢く日常生活に役立てるには
⇒https://kamiconsal.jp/amattanotetukaimiti/
キャンパスノートでトートバッグ!端材を配合した再生紙で?
⇒https://kamiconsal.jp/cumpasnotetotobag/
紙を破るとストレスが発散?書いて破って「スカッとノート」
⇒https://kamiconsal.jp/kamiyaburustress/