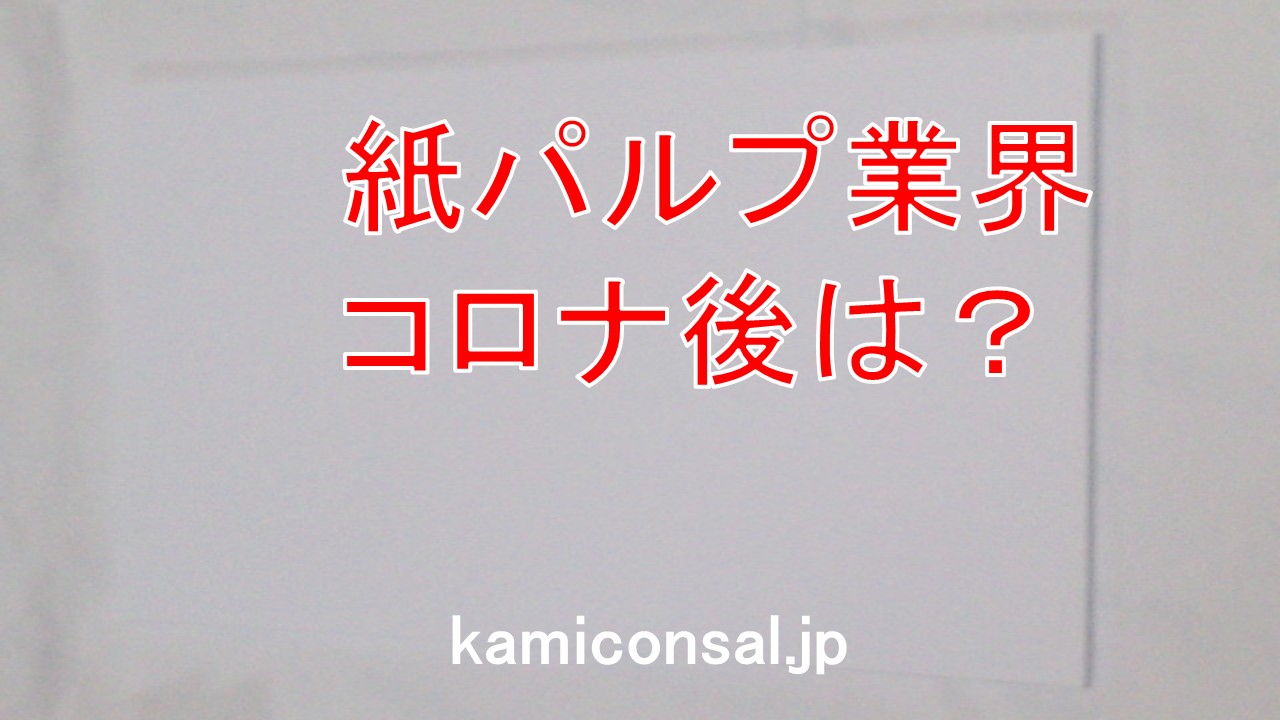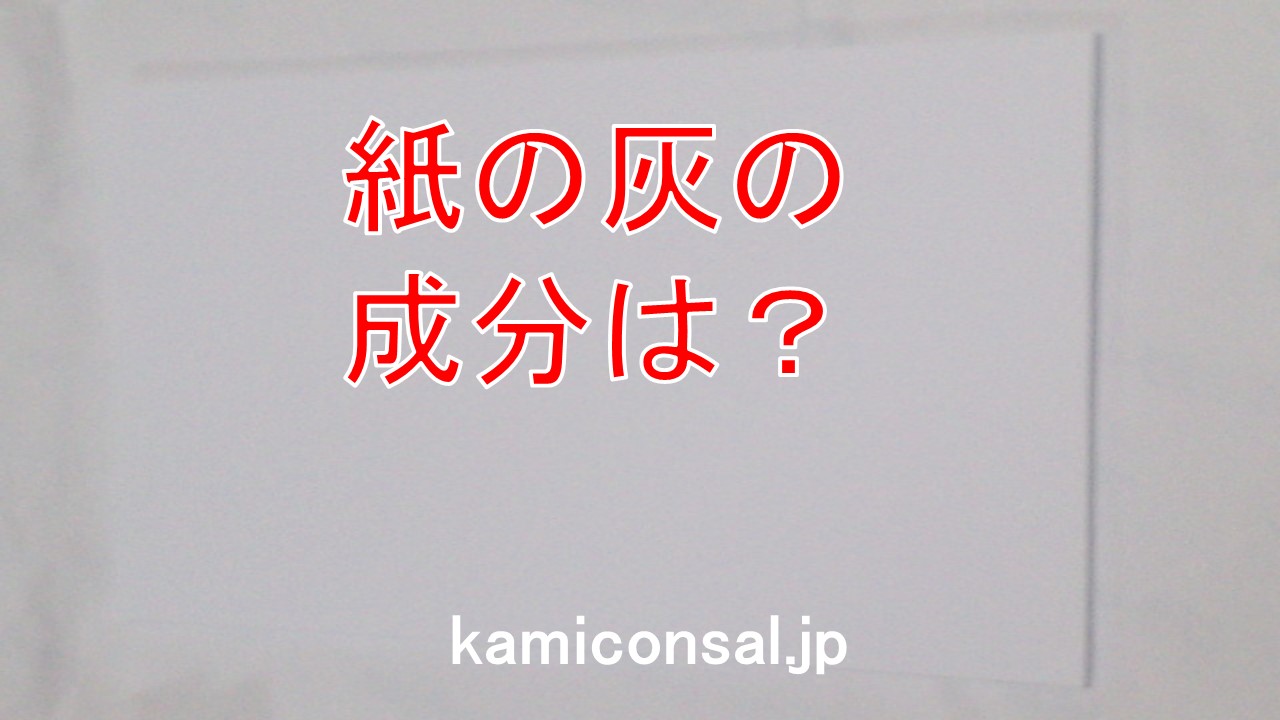この記事は約 10 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は紙パルプ業界のコロナ後は?
構造の変化が加速するらしい、
というお話。
紙パルプ業界は厳しくなってますけど。
特に印刷用紙は厳しいんですが。
なので、どの品種を伸ばして
どの品種を減らすかが重要。
経営者は日々このことを考えてるでしょう。
それがコロナでさらに加速するという。
一体どの品種がどうなるのか?
管理人も気になったので調べてみました。
ということで。
この記事では、紙パルプ業界のコロナ後は?
構造の変化が加速するらしい、について
管理人なりに調べたことを
お伝えしたいと思います。
紙パルプ業界のコロナ後。印刷用紙は減りダンボールが増える
結論から申し上げますと。
紙パルプ業界におけるコロナ後の変化として、印刷用紙の需要は減少し、ダンボールの需要は増加するという傾向がより顕著になっています。
「そんなの今でもそうじゃないか」と思う方もいるかもしれませんが、実際にはその傾向がさらに加速していくという見方がされています。
分かりやすい例が、新聞紙の減少です。
管理人の母親は80代なのですが、この世代ではまだまだ紙の新聞を読むことが生活の一部になっています。朝に新聞がないと落ち着かない、という話もよく聞きます。
そんな背景もあり、管理人も一緒に新聞を読んでいたりします。
ですが正直なところ、読まなくてもそれほど困ることはありません。
というのも、今ではネットニュースが簡単にスマホやPCで読めるため、紙の新聞にこだわる理由があまりないのです。
つまり、紙媒体の新聞に親しみを持つ高齢者が減少することで、新聞紙の需要も比例して減っていくという流れは避けられません。
この傾向については、コロナによる影響というよりは、もともとの時代の流れだったとも言えるでしょう。
出版物に関しても似たような事情があります。
たとえば、漫画やライトノベルの人気は相変わらずあるものの、それをわざわざ紙で読む必要があるかというと、そうでもなくなっています。
今ではほとんどの作品がスマホで読めるようになり、電子書籍が主流になってきました。
そのため、紙の本を買う人はかなり限定的になってきています。
もちろん、手元に置いて繰り返し読みたいとか、コレクションとして本棚に並べておきたいといった理由があれば、紙の本の良さはあります。
しかし、それ以外であれば「一度読んで終わり」という人にとって、紙の本はただの荷物に過ぎません。
軽い読み物である漫画やラノベなら、なおさら電子版で十分だと感じる人が多いでしょう。
確かに学術書など、じっくり読む系の書籍については紙の方が向いているという意見もありますが、そういった本は一般にそれほど多く流通しないため、紙の需要全体から見れば小さな比率に留まります。
このように、コロナによって外出する機会が減った中でも、スマホで電子書籍を購入し、読書を楽しむスタイルが定着し始めました。
この傾向は、コロナによって明確に加速されたと考えられます。
どこからどう見ても、印刷用紙にとっては逆風の時代です。
「どうしても紙の本でなければ」という層は今後ますます減っていくことでしょう。
紙媒体のほうが記憶に残りやすいという研究結果も一部にはありましたが、それを否定するような研究も出ています。
(過去記事)
紙媒体と電子媒体の比較!新研究結果、理解に重要なのは慣れ
⇒https://kamiconsal.jp/kamibaitaidensibaitai/
このような情報を踏まえると、「紙である必要はない」と考える人が今後さらに増えていくことが予想されます。
また、学校の授業やテストがタブレットやPCを活用するようになると、紙を使う機会自体が大きく減ります。
紙に触れる機会が少なくなればなるほど、紙への親しみも薄れていくのは当然の流れです。
もしかしたら近い将来、「紙をめくって本を読む」という行為が贅沢な体験として特別視される時代が来るかもしれません。
ディスプレイ媒体としての紙の役割は、今後ますます縮小していく可能性が高いです。
一方で、ダンボールの需要は非常に大きく増加しています。
コロナ以前からこの動きは見られましたが、コロナを機にさらに拍車がかかりました。
特に、通販の利用拡大によってダンボールの使用量は急増しています。
管理人自身は通販にあまり積極的ではありませんが、外出できない状況になれば通販に頼るしかなくなるものです。
実際、管理人の近所には介護をしている家庭があり、買い物や日用品の購入すべてを通販で済ませています。
外出せずに必要なものが届くこのシステムは、非常に便利で効率的です。
子育て中の家庭でも同じような事情があるでしょう。
こうして通販の利便性を一度体験してしまうと、もう元の生活スタイルには戻れない人が多いのです。
この「便利さへの慣れ」が、人々の行動様式を大きく変えていきます。
その結果として、ダンボールは生活に欠かせない存在となっていき、安定した需要が見込まれるというわけです。
コロナがなくても進行していたこの変化が、コロナによって加速されたことは間違いないでしょう。
紙パルプ業界のコロナ後。その他の品種は?
先ほどは印刷用紙の減少とダンボールの増加について述べましたが、ではそれ以外の紙製品はどうなのでしょうか。
一例としてわかりやすいのが、ウエットティッシュの増加です。
コロナ禍で衛生意識が高まり、手や物を拭くシーンが非常に多くなりました。
ウエットティッシュは厳密には紙ではないのですが、同様に増えたものとしてマスクも挙げられます。
こうした背景から、家庭紙と呼ばれる日常生活に使う紙製品は需要が増えています。
一方で、イベントの中止や縮小により、ポスターやチラシ、カタログなど、イベント系で使用される印刷物の需要は大幅に減りました。
これらも印刷用紙に含まれるため、全体として印刷に使う紙の役割は明らかに縮小しています。
総じて見ると、「紙に印刷して情報を伝える」という機能が減り、「紙で物を包む」「衛生的に使い捨てる」といった実用的な機能が求められるようになっているのです。
包装の分野では、紙とフィルムの競争も激しくなっていますが、強度や環境性能を加味すると、ダンボールは当面安定した地位を保つと考えられます。
一方、「書き記すための紙」は、これからますます厳しい立場に置かれるでしょう。
残っていくのは、感謝や思いを伝えるような、心のこもった手紙など、特別な用途に限られていくかもしれません。
管理人のまとめ
今回は「紙パルプ業界のコロナ後」に関する構造の変化についてご紹介しました。
コロナ前から既にその傾向はありましたが、コロナによってそのスピードが一気に上がったようです。
印刷用紙の需要が下がり、ダンボールなど物流に関連する紙の需要が上がるという動きは、今後も続くでしょう。
しかしながら、製紙業界というのは「装置産業」ですので、簡単に製品ラインの転換ができるわけではありません。
たとえば、新聞紙の需要が落ちたからといって、明日から別の紙を生産しようというのは無理な話です。
そもそも、新聞紙というのは非常に特殊な性質を持った紙であり、全く異なる紙を同じ機械で生産するには、大掛かりな設備変更が必要になります。
そのため、品種変更をするにしても、企業がそれだけの投資を行う余力があるかどうかという点が問われるのです。
技術だけでなく、資金力や経営判断が重要になります。
未来予測として「こう変わるはずだ」と分かっていたとしても、実際にその変化を現場レベルで実現するのは非常に困難なのです。
大手企業であればある程度の柔軟性を持って対応できますが、特定の紙種に特化している中小企業にとっては大きな課題となるでしょう。
さらに、ダンボールの需要が伸びるにしても、今度はその原料をどう確保するかという新たな問題が発生します。
いずれにせよ、この業界の構造転換は一筋縄ではいかないのです。
この記事が少しでも、紙パルプ業界の今後について考える参考になれば幸いです。
この伝統ある業界が、時代に適応しながら、なんとか生き残っていってくれることを願っています。
(参考)
こんな記事も読まれています。
シールをカットする方法。複雑な形状はカッティングマシン!
⇒https://kamiconsal.jp/sheelcuthouhou/
絵をパソコンに取り込みたい!デジタル化はどうすればいい?
⇒https://kamiconsal.jp/epctorikomi/
かさばらないノートについて。筆記用に使える薄い紙はある?
⇒https://kamiconsal.jp/kasabaranainote/