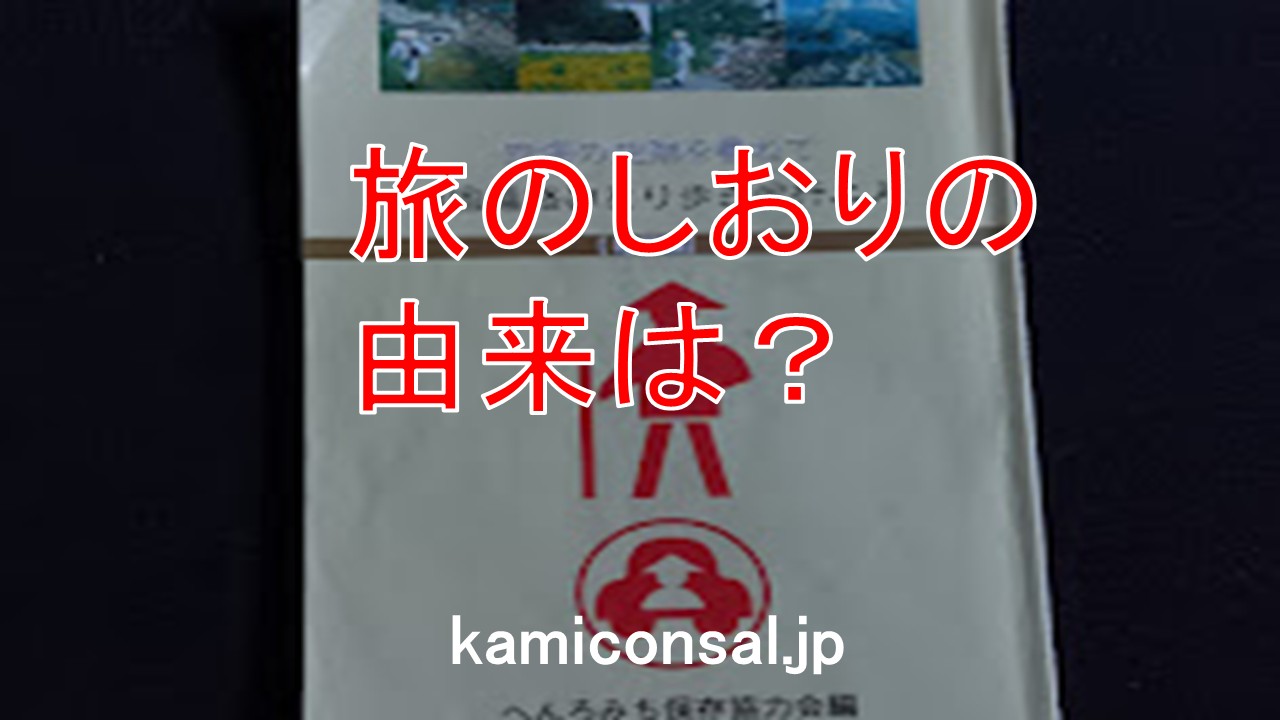この記事は約 7 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、旅のしおりの由来?
小枝を折って道に迷わない目印にしたこと
というお話。
「旅のしおり」という言葉は、
現代では旅行計画や持ち物リスト、
観光地の情報などをまとめた冊子や
プリントを思い浮かべる人が多いでしょう。
しかし、もともとの意味や由来を辿ると、
実は自然の中での工夫に由来しています。
昔の人々は旅をするとき、今のように
地図やスマートフォンのナビが
あるわけではありません。
そこで、小枝や草を折ったり結んだりして、
自分や仲間が道に迷わないように
「目印」として残していました。
この習慣が「しおり」という
言葉のもとになったとされています。
ここでは、旅のしおりの由来と、
その背景にある文化や歴史について
詳しく見ていきます。
ということで。
この記事では、旅のしおりの由来?
小枝を折って道に迷わない目印にしたこと
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
「しおり」という言葉の語源
「しおり」という言葉の由来を考えるとき、
まず注目すべきはその語源です。
日本語の「しおり」は
「枝折り(しをり)」から来ていると
言われています。
山道を歩く際、旅人や狩人は自分の通った道を
分かるように小枝を折って目印としました。
これによって、帰り道を
見失わないようにしたのです。
この行為が「枝を折る」つまり
「枝折り」と呼ばれ、それが
「しおり」という言葉に
変化していったと考えられています。
現代では「しおり」と聞くと、
本に挟む栞や旅行冊子を
思い浮かべますが、もともと
「道を迷わないようにする工夫」
そのものを意味していたのです。
このように、言葉は時代とともに
意味を変えながら受け継がれてきました。
旅と道しるべの関係
旅をする人々にとって、道に迷うことは
大きなリスクでした。
特に山道や森の中は目印が少なく、
同じような風景が続くため、
道を間違えると簡単には元に戻れません。
そのため、昔の旅人は「しおり」という
形で道しるべを残す工夫をしていたのです。
例えば、枝を折って進んだ方向を示す、
草を結んで印を残す、石を積み重ねて
目印にするなどの方法がありました。
これらはすべて
「戻るときに迷わないための工夫」であり、
現代でいうナビゲーションシステムの
原型ともいえます。
また、こうした行為は一人だけでなく、
後から同じ道を通る人への助けにも
なりました。
つまり「しおり」は、単なる個人的な
目印ではなく、共同体的な役割も
果たしていたのです。
書物の「栞」とのつながり
「しおり」という言葉は、やがて
本の世界でも使われるようになりました。
本を読むときに使う「栞」は、
読み途中の場所を忘れないための
道しるべです。
これは、旅の途中で道を間違えないようにする
「枝折り」と考え方が同じです。
つまり、本の栞もまた「読書という旅」の
道標であり、知識や物語の中で迷子に
ならないための工夫なのです。
この転用が起こった背景には、
日本文化における「旅」と「物語」の
つながりがあると考えられます。
古来より物語は旅を伴うことが多く、
読書は心の旅路に例えられてきました。
そのため、道しるべの役割を持つ
「しおり」という言葉が、
読書にも自然と結びついていったのです。
ここからも、「旅のしおり」と「本の栞」は
同じ根っこを持つ言葉であることが
分かります。
現代に受け継がれる「旅のしおり」
今日の「旅のしおり」は、旅行前に
作られる冊子やしおり型のプリントとして
使われます。
そこにはスケジュール、交通手段、宿泊先、
観光情報、持ち物チェックリストなどが
書かれ、旅の準備を整えるための
役割を果たします。
現代の「旅のしおり」もまた、
道に迷わないための工夫といえるでしょう。
さらにデジタル化が進んだ今では、
スマートフォンのアプリや
オンラインサービスを使って
「デジタルしおり」を作ることも
一般的になりました。
グループ旅行であれば、オンラインで
共有できる旅程表を作ることで、
参加者全員が同じ情報を確認できます。
これはまさに、
昔の「枝を折って道しるべを残す」行為と
同じ精神を受け継いでいるといえるでしょう。
つまり「しおり」という概念は、
時代とともに形を変えながらも、
「迷わないようにする」
「正しい道を見失わないようにする」
という根本的な役割を守り続けているのです。
管理人のまとめ
今回は、旅のしおりの由来?
小枝を折って道に迷わない目印にしたこと
というお話でした。
「旅のしおり」という言葉の由来は、
道に迷わないように小枝を折って
目印を残した昔の習慣にあります。
そこから「枝折り(しをり)」という
言葉が生まれ、後に「栞」として読書や
旅行計画にも用いられるようになりました。
現代の「旅のしおり」は冊子やアプリの
形をとりながらも、その本質は昔と同じく
「迷わないための道しるべ」です。
形は変わっても人々が安心して
旅を楽しむための工夫として、
「しおり」は今も受け継がれています。
この記事が旅のしおりの由来の
参考になればと思います。
旅行、楽しんで下さいね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
旅行雑誌の廃刊の理由とは?業界の変化と読者ニーズの変遷!
⇒https://kamiconsal.jp/ryokouzassihaikanriyu/
観光パンフレットのお取り寄せは?旅行会社、鉄道、ネットも
⇒https://kamiconsal.jp/kankopanfphletotoriyose/
旅ノートの作り方!思い出をカタチにすればもっと楽しいかも
⇒https://kamiconsal.jp/tabinotetukurikata/