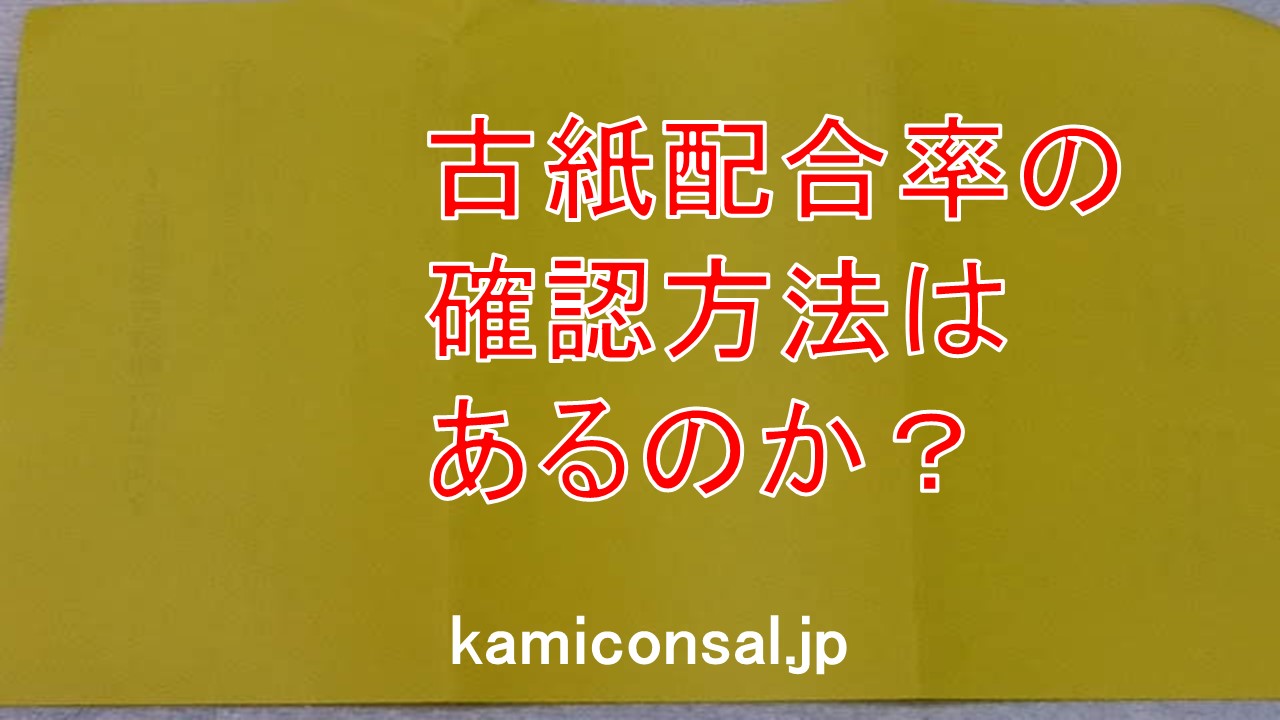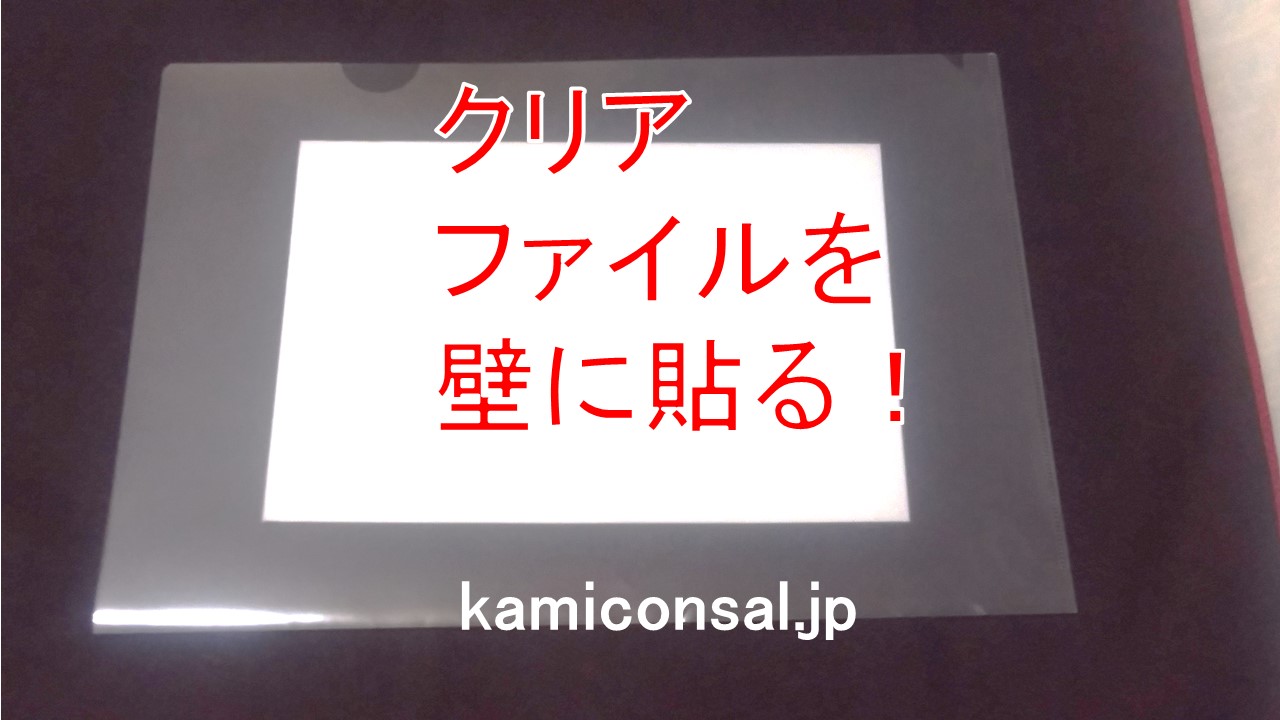この記事は約 12 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回のお話は、古紙配合率の
確認方法はあるのか。
ずいぶん専門的なお話ですが。
以前、古紙入りPPC用紙で
古紙配合の偽装問題がありました。
はがき、でも偽装があったと思います。
管理人が会社をやめてから
発覚したお話なんですけど。
偽装の内容は、古紙配合率が低いのに
古紙配合率が高いように言っていたこと。
ただこの問題、普通の
偽装問題と違うところがある。
それは、偽装してもユーザーには
品質で迷惑をかけていないということ。
一般的な話をすると。
古紙を配合すると紙の品質は
落ちるものなんですね。
だから、古紙が入っていない方が
紙の品質は良いという事ができる。
そこをあえて環境に配慮するため
古紙配合率を高く表示していた。
他の偽装問題の場合はたとえば
食品の賞味期限を変更するとか
そういう品質が悪いのに良いように
偽装するのがだめということですよね?
しかし、この古紙配合率の場合は
品質が良いのに悪いように偽装した。
偽装には違いないのでユーザーを
裏切っていた、嘘をついていた
そういう意味ではダメなんですが、
じゃあその紙使って問題あるか?
というと全く問題はなくて
むしろ品質がいいわけです。
こういう感覚は製造側にもあって
良いものを売ってるのに、となるわけ。
偽装だからモラルはダメですけどね。
まあ、そんな問題があったので
古紙配合率の確認方法はあるのか?
ということになるんですが、
これはなかなか難しい。
実際のところを元製紙会社社員として
意見を述べたいと思います。
ということで。
この記事では古紙配合率を
確認する方法はあるのかについて
管理人の調べたことを
お伝えしたいと思います。
古紙配合率を確認する方法はあるにはあるが
結論から申し上げますと、古紙配合率の確認方法というのは一応存在します。ただし、それを実際に行うとなると、なかなかハードルが高く、容易ではないというのが現実です。
まず大前提として知っておくべきことがあります。それは、紙に使われているバージンパルプと古紙パルプとを、見た目や物理的な特性から明確に判別するのが極めて難しいという点です。
バージンパルプというのは、主に木材チップを原料として作られたパルプで、一度も紙として使用されたことのない新品のパルプです。一方、古紙パルプは、一度使用された紙製品を回収して再処理したものになります。
理想としては、これら二つのパルプを簡単に見分けることができればいいのですが、現実にはそれは不可能です。たとえて言うなら、洋服を一度着たものか、二度着たものかを素材だけで判断しろと言われるようなもので、明確な違いは見た目に現れないのです。
そのため、紙に含まれている古紙の割合、すなわち古紙配合率を確認するのは、思っている以上に複雑で、正確性に欠ける場合も多いのです。
さて、管理人が独自に調査したところによると、古紙配合率を推定する方法としては、大きく分けて2種類が存在するようです。以下ではそれぞれの方法について、詳しくご紹介していきます。
古紙配合率を蛍光染料から確認する
まず1つ目の方法ですが、これは古紙配合率を「蛍光染料の含有量」から確認しようという方法です。
少し仕組みを説明すると、古紙パルプというのは、複数の種類の紙が混ざってできています。なかでも最も多く含まれているのが新聞紙で、それにチラシなどが混ざってきます。
とくに印刷用紙などに使われる古紙パルプの原料は、新聞紙とチラシが主になります。
ここでポイントとなるのが、それぞれの紙の性質の違いです。新聞紙は非塗工紙と呼ばれ、表面にコーティングがされていない紙で、白色度もあまり高くありません。また、新聞紙には基本的に蛍光染料は使用されていません。
一方、チラシはその多くがコート紙であり、見た目を白く美しく見せるために、塗料に蛍光染料が添加されていることがほとんどです。
このため、古紙パルプの中にはチラシ由来の蛍光染料が一定量含まれていると考えられます。そこで、蛍光染料の量を測定することで、間接的に古紙がどのくらい含まれているかを推定できるという理屈です。
つまり、「古紙配合率が高ければ、それに伴って蛍光染料の量も多くなるだろう」と推測し、そのデータを使って古紙配合率を確認するというわけです。
確かにこの方法なら、ある程度の目安にはなるでしょう。しかしながら、実際にこの方法だけで正確に判断できるのかというと、それは少々甘いと言わざるを得ません。
なぜなら、抜け道が存在するからです。
たとえば、もしも製紙会社が意図的に古紙配合率を高く見せようとした場合、原料に人工的に蛍光染料を加えて紙を作ることが可能です。
もし検査が蛍光染料の含有量だけを基準にしているのであれば、製紙会社が意図的にその基準をクリアするよう蛍光染料を添加することができてしまいます。
こうなると、実際には古紙がほとんど含まれていなくても、あたかも多く配合されているように見せることが可能になるわけです。
実際、古紙100%で作られた紙の蛍光染料の平均値を基準に、その数値に近づくように調整することは、製紙現場ではそれほど難しくありません。紙の色調を整えるのと同じ技術を応用すればよいからです。
つまりこの方法は、製紙会社側にとっては対策が比較的容易であり、第三者機関が正確に監視するには不向きな側面もあるのです。
もちろん、コストがかかるため常にそのような操作を行うわけではないと思いますが、やろうと思えばできてしまう。それが問題の本質です。
この方法を使うのであれば、抜き打ち検査のような形で行わないと、実態を把握するのは難しいでしょう。事前に知らせてしまえば、それに合わせた対応が可能になってしまいますから。
そういった意味で、蛍光染料による測定は牽制としての効果はありますが、絶対的な確認方法にはなり得ないのです。
古紙配合率を機械パルプから確認する
次にご紹介するのが、古紙配合率を「機械パルプの含有量」から確認するという方法です。
先ほどの蛍光染料を使った方法と違い、こちらは機械パルプという素材に注目する点が特徴です。
すでにお話しました通り、印刷用紙に使用される古紙パルプは、主に新聞紙とチラシが原料です。このうち、新聞紙には古紙と機械パルプが含まれています。
新聞紙の構成としては、半分以上が古紙で構成され、残りの一定割合は機械パルプが使われています。この機械パルプの含有量を手掛かりにして、古紙配合率を逆算的に推定しようというわけです。
機械パルプの量を調べるには、C染色液という特定の染色液を使います。この染色液に紙を浸した際に、化学パルプと機械パルプで異なる色に変化するという性質を利用して、それぞれのパルプの割合を把握するという方法です。
この技術によって、紙にどのくらい機械パルプが含まれているかを調査できるようになり、それを根拠として古紙配合率も一定の精度で推定できるということになります。
この方法の良いところは、蛍光染料のように添加すればすぐに見破れないという点ではなく、より物質的な構成要素に基づいている点です。
しかしながら、この方法にもやはり抜け道は存在します。
検査する側が「機械パルプの量で配合率を判断する」と分かっていれば、製紙会社は紙の原料に機械パルプを意図的に追加することが可能です。
その結果、古紙をあまり使っていなくても、機械パルプの量だけを見れば、まるで古紙が多く含まれているかのように見せることができるのです。
製紙の現場では、通常から機械パルプを使う工程は存在しており、少量追加することはそれほど難しくありません。さらに、もし自社で機械パルプを製造していない場合でも、市場から購入すれば対応可能です。
つまり、この方法も事前に知られてしまえば、ある程度対策されてしまうというわけです。
もちろん、頻繁にそういった対応を行うにはコストがかかるため、日常的にやっているとは考えにくいですが、「どうしても高い古紙配合率を見せたい」という場合には、手段があるということを理解しておく必要があります。
古紙配合率遵守は製紙会社のモラル
ここまで紹介してきたように、古紙配合率を紙から正確に把握する方法は、一応存在します。ただし、それぞれの方法には抜け道があり、検査対象となる製紙会社が意図的に対策を講じれば、いくらでも数字を作ることができてしまうのです。
結局のところ、古紙配合率の遵守は製紙会社のモラル、つまり倫理観や誠実さにかかっているということになります。
たとえば、製造記録である操業日報を確認したとしても、そこに嘘が書かれていれば真実は分かりません。極端な話、検査員が現場に立ち会っていても、記録や表示が偽装されていれば、それを見破るのは不可能に近いのです。
そのような偽装が明るみに出るのは、内部告発のような例外的なケースに限られます。
つまり、第三者がいくら科学的・技術的に検査を試みたところで、根本的に「本当のところ」を知る手段は極めて限られているということです。
結局、古紙配合率の遵守は、製紙会社が「正しく表示し、正しい製造を行う」という誠実な姿勢を持っているかどうかに委ねられています。
過去には実際に偽装問題が発覚したこともありますが、現在では問題が明るみに出たことにより、技術的に無理のない範囲で、きちんとした古紙配合率が守られていると感じています。
管理人のまとめ
今回は、古紙配合率の確認方法についてのお話をしてきました。
まとめると、「古紙配合率を確認する方法は確かに存在するが、その方法には限界があり、完全に真実を見抜くことは難しい」ということです。
バージンパルプと古紙パルプは区別がつかないため、蛍光染料や機械パルプといった間接的な指標に頼るしかないのが現状です。
しかし、それらも意図的に操作が可能であり、抜き打ち検査でない限り、製紙会社が対策してしまえば正確な配合率を見抜くことは難しいのです。
ですので、最終的には製紙会社の誠実さ、つまりモラルが非常に重要な要素となってくるというわけです。
現在は、過去の問題を教訓に、製紙会社も無理のない配合率で製造しているように見受けられます。
この記事が、古紙配合率の確認に関心のある方にとって少しでも参考になれば幸いです。
たまには、紙の裏にある「見えない成分」にも目を向けてみてくださいね。