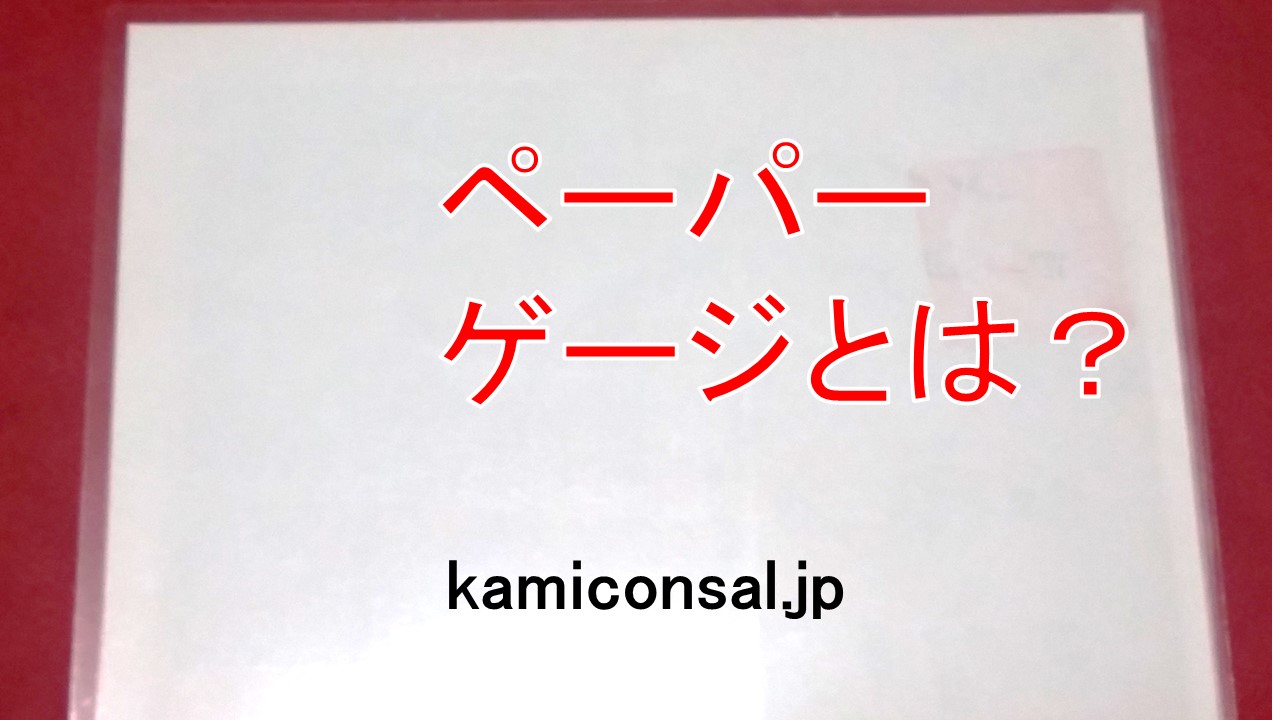この記事は約 9 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、ペーパーゲージとは?
紙の厚さを簡易的に測定する機械のこと
というお話。
管理人もペーパーゲージは使ってました。
これも種類が色々あるんですけど
簡易的なのはこれですかね。
尾崎製作所 ダイヤルシックネスゲージ ペーパーゲージ PG-10
ピーコックで紙厚を測る。
特に営業所とかでは活躍してました。
正直言うとハンディタイプの
ペーパーゲージは個人差がある。
実際に試験室で使っている据え置き型の
紙厚計と若干違っていることもあります。
しかしながら。
これほど精度良く簡易的に紙厚を
測定できる機械はないでしょう。
ということで。
この記事ではペーパーゲージとは?
紙の厚さを簡易的に測定する機械のこと
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
ペーパーゲージの使い方
ペーパーゲージの使い方についてですが、これは一見シンプルに見えて、実際のところも比較的簡単です。ただし、正確な測定結果を得るためには、いくつかの基本的なポイントを押さえる必要があります。
まず最初に行うのが「ゼロ点調節」です。これは、何も挟まない状態でメーターの針、もしくは数値がゼロを示すように調整する作業です。管理人が使っていたのはアナログ式のペーパーゲージだったので、外側にある目盛り付きのダイヤルを手で回しながら、針がちょうどゼロに来るように合わせていました。
一方で、最近の機種ではデジタルタイプのものも多く見かけます。その場合は、通常リセットボタンやゼロセットボタンと呼ばれるボタンがあり、それを押すことで簡単にゼロ点が調整できるようになっています。もちろん、メーカーやモデルによって調整方法は若干異なりますので、取扱説明書などで確認しておくと安心です。
ゼロ点調整が完了したら、次は実際に紙を挟んで厚さを測定します。ペーパーゲージのレバー部分を指で操作して、紙を計測部分にしっかりと挟みます。測定時の操作感としては、「ガシャガシャ」とレバーを何度か開閉しながら、紙を安定して挟み込むような感覚です。
このときに注意しなければならないのがいくつかあります。まず、紙は必ず水平に挟む必要があります。もし斜めに挟んでしまうと、実際の厚さよりも厚く測定されてしまう可能性があります。これは特に、薄くて柔らかい紙ほど影響が出やすいので要注意です。
また、ペーパーゲージの挟む部分が汚れていたり、紙粉やホコリなどが付着していると、正確な測定ができません。常に清潔な状態を保つようにしましょう。さらに、レバーの押さえ方も大切です。毎回、同じ力加減で押さえないと、これも数値にブレが出る原因となります。
管理人が以前使用していた「ピーコック」のペーパーゲージでは、特にレバーの押し加減が微妙で、少し力を入れすぎると測定値が高く出ることがありました。プラスチックフィルムのように硬くてしっかりした素材なら誤差も少ないですが、ふんわりした紙などの場合は、押し方次第で厚みの数値が変わることがあります。
試験室に設置されているような据え置き型の紙厚計では、紙を押さえる圧力が機械的に一定に保たれているため、測定者による個人差はほとんど発生しません。しかし、持ち運び可能な簡易型のペーパーゲージでは、どうしても人によるばらつきが出てしまうのが現実です。
そのため、測定結果の細かい数値を絶対的に信用しすぎるのは危険です。あくまで参考値として捉え、「紙Aと紙Bではどちらが厚いか」といった相対的な比較に使うのが適していると言えるでしょう。
また、熟練の現場作業者などは、無意識に「手心」を加えて自分の期待する数値を出してしまうこともあります。それは決して不正の意図がなくても、結果的に測定精度に影響を及ぼすことになります。
製造現場などで毎回同じ製品を測定している場合には、ある程度安定した数値が出るかもしれませんが、それでも人為的な微調整の余地がある以上、常に慎重な姿勢で取り扱う必要があります。
ペーパーゲージのメリット・デメリット
ここまで、ペーパーゲージの使い方について詳しくご紹介してきましたが、続いてはそのメリットとデメリットについて触れておきたいと思います。
まず、最大のメリットは「手軽さ」にあります。ペーパーゲージはコンパクトで持ち運びがしやすく、電源も不要なものが多いため、いつでもどこでも手軽に紙厚の測定ができる点が魅力です。実際に管理人も、工場や出張先、紙の仕入れ先など、さまざまな場面で使ってきました。その場ですぐに紙の厚さを確認できるというのは、現場において非常に重要な機能です。
一方で、デメリットもいくつか存在します。その最たるものが「測定精度のばらつき」です。特に、指でレバーを押すタイプのペーパーゲージは、どうしても使用者によって力の加減に違いが生じ、結果として測定値に差が出てしまう傾向があります。これが原因で、同じ紙でも人によって厚さの測定結果が微妙に異なることがあります。
試験室などに設置されている機械式の紙厚計は、自動的に圧力を一定にして測定を行うため、人の手による影響はありません。そのため、極めて高い精度が求められる場面では、やはりそうした装置の方が信頼性は高いと言えるでしょう。
また、数ミクロン単位の違いを正確に測定したいような繊細な用途では、簡易型のペーパーゲージではやや力不足な印象です。どんなに本体の測定機構が高精度でも、使用者が不慣れであれば正確な数値は得られません。
ですので、特に初心者や測定経験が浅い方が使用する場合には、あくまで目安として利用し、最終的な判断は複数回の測定や他の手段と併用するのが望ましいです。一方で、経験豊富な職人や現場担当者が使えば、かなり安定した数値を出すことも可能であり、その点では使用者のスキルが大きく関与する道具とも言えるでしょう。
管理人のまとめ
今回はペーパーゲージとは?
紙の厚さを簡易的に測定する機械のこと
というお話でした。
ペーパーゲージは簡易的に紙厚を
測定するにはとても便利な器具。
試験機器としては価格も高くありません。
薄いものを測定する機会があるなら
持っていても損はないアイテムです。
ただし、使い方は注意すべきところがある。
特に薄いものを人間が測定するので
器具やサンプルの取り扱いが悪いと
せっかく測定しても正確な数値が
得られない場合があります。
管理人的にはペーパーゲージを過信せずに
数値は目安として確認するのがいいかなと。
でもお客さんの前でピーコックを使って
紙厚を測定すると信用される気がしてました。
いかにも技術者と言う感じがしますから。
演出として持っておくのもありですかね~
この記事がペーパーゲージの
参考になればと思います。
ペーパーゲージ、うまく使って下さいね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
紙の検査を依頼したい!どこで紙質試験をやってくれるのか?
⇒https://kamiconsal.jp/kamikensairai/
紙の剛度とは?曲げたときの抵抗でコシと呼ばれることが多い
⇒https://kamiconsal.jp/kamigoudo/
紙の品質を管理する項目とは?基本的な物性と独自の物がある
⇒https://kamiconsal.jp/kamihinsitu/