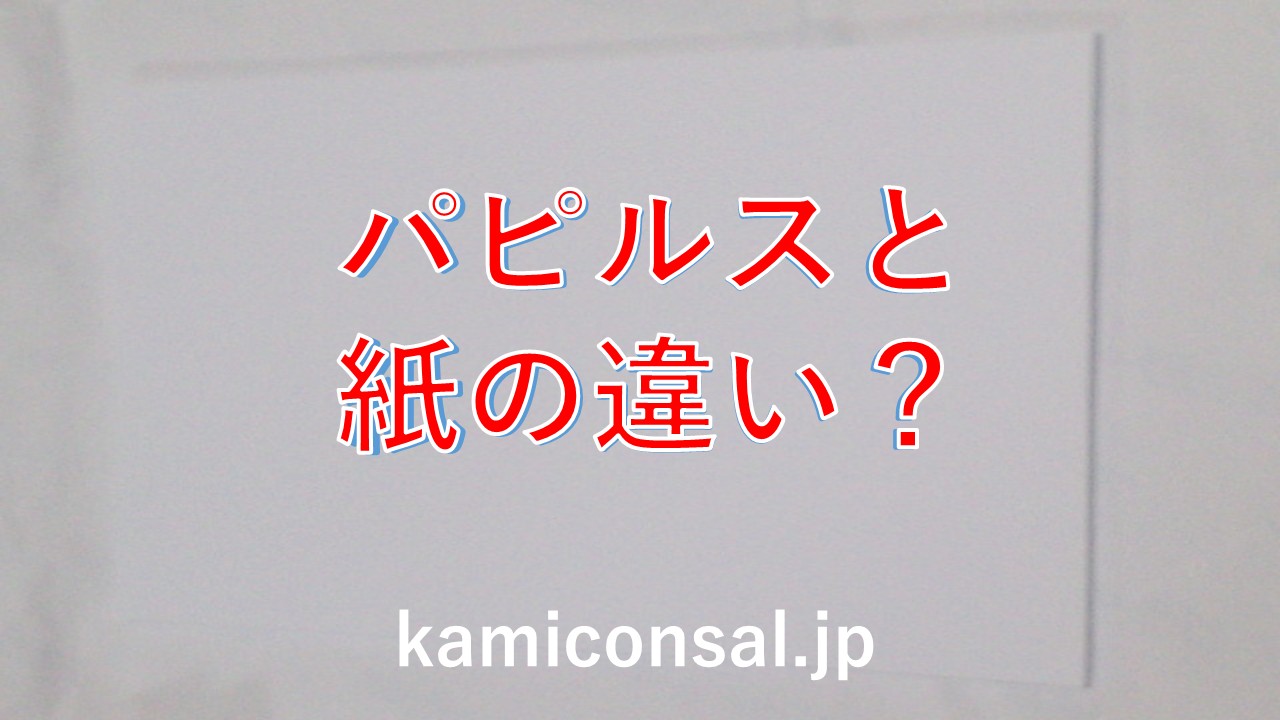この記事は約 9 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、パピルスと紙の違い?
圧力を加えた脱水シートか水中で抄くか
というお話。
書くための素材といえば、現代では
「紙」が一般的ですが、古代には
「パピルス」という植物を利用した
筆記材が用いられていました。
どちらも情報を記録するという
目的は共通していますが、
構造や製造方法、材質には
大きな違いがあります。
この記事では、パピルスと紙の製法の
違いに注目しながら、それぞれの特徴を
具体的に掘り下げていきます。
圧力を加えて脱水しながら作るパピルスと、
水中で繊維を抄いて乾燥させる紙。
この2つの製法の差が、それぞれの
素材としての性質を大きく左右しています。
ということで。
この記事では、パピルスと紙の違い?
圧力を加えた脱水シートか水中で抄くか
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
パピルスとは何か?その製法と構造
パピルスは、古代エジプトを中心に使用されていた、歴史的にも重要な筆記媒体の一つであり、特に書類や文書の記録に広く利用されていました。現代の紙とは構造も製法も異なり、自然素材を活かした独自の加工法で作られていた点が大きな特徴です。
その素材となるのは、ナイル川流域に生息しているパピルス草(Cyperus papyrus)で、この植物は湿地帯に多く見られ、背丈が高く成長することでも知られています。
製法としては、まずこの植物の茎の中心部分を取り出し、これを薄くスライスして細長い帯状に加工します。次に、それらのスライスを縦方向と横方向に交差させるように格子状に配置し、上から圧力を加えながら脱水します。この工程により、素材が平らなシート状になります。
このとき、接着剤のようなものは一切使わず、植物自体が持っている粘着性や、水分の蒸発による自然な収縮力を活かして、各繊維同士を密着させていきます。その結果、パピルスは植物繊維がそのまま交差している状態を保ちつつ、しっかりと接着された構造になります。
この製法は現代の紙とはまったく異なるアプローチで、パピルスの特徴としては、植物本来の繊維構造を損なわずにそのまま残していることが挙げられます。そのため、見た目にも繊維の方向性が明確に分かり、素材としての独自性を持っています。
仕上がったパピルスは、書き込み可能な表面を持ち、古代においては記録媒体として非常に重宝されていました。また、硬さや裂けやすさから、折るのではなく巻いて保存されることが多く、巻物としての使用が一般的でした。長い文書になる場合は、複数枚のパピルスを丁寧に接着して一本の長い巻物を作り、それによって情報を体系的に残す工夫もされていました。
紙の発明とその製法の特徴
一方で、現在一般的に使用されている紙のルーツは、中国にまでさかのぼることができます。紙の発明は紀元前2世紀頃とされ、その製法は蔡倫(さいりん)という宦官によって改良されたと伝えられています。この技術は後にシルクロードを通じて各地に伝わり、世界中に広まることになりました。
蔡倫によって改良された製紙法では、まず麻くずや木の皮、布などの植物性の繊維を水に浸し、叩いて細かくし、繊維をバラバラに分散させる工程から始まります。この繊維を混ぜた水を「紙料」と呼び、それを水中に沈めた網目状の道具(漉き簀)で掬い上げることで、繊維が均等に広がったシートが形成されます。
この「抄紙」と呼ばれる工程の中で、水中の繊維が自由に動きながら自然に絡み合い、全体に均一な厚みを持った紙の元ができていきます。そして、漉き簀を水から引き上げた後は、水分を自然に排出させながら乾燥させていくことで、紙が完成します。
この製法の最大の特徴は、繊維を水の中で一度バラバラにしてから、再び絡ませて結びつけるという点にあります。繊維の隙間が少なくなり、表面も滑らかになるため、文字を書く際のインクの乗りもよく、書きやすい素材が得られます。
また、この紙は折り曲げたり、冊子として綴じたりするのにも適しており、書籍文化の発展にとって大きな一歩となりました。紙はその加工のしやすさから、行政記録、文学、宗教文書など、あらゆる分野に活用され、文明の情報伝達のインフラとなっていきました。
パピルスと紙の製法の根本的な違い
パピルスと紙は、どちらも植物を原料とした筆記媒体ですが、製造方法や構造には根本的な違いが存在します。最も大きな違いは、繊維の処理方法と、最終的にシート状に仕上げる工程にあります。
パピルスの場合は、植物の繊維をそのまま活かして物理的に圧縮・脱水することで一枚のシートに仕上げます。つまり、原料そのものの構造を保ちながら押し固める「脱水圧縮シート」と言えます。この方法では、繊維同士が上下に交差しているため、一定方向に裂けやすく、加工には注意が必要です。
それに対して紙は、「水中で繊維を分解し、均一に分布させてから再び絡ませて結合させる」という工程を経ています。いわば「水中抄造シート」と呼べる製法で、これは繊維を完全にほぐしてから再構成するという発想です。
この違いは、完成した素材の性質にも顕著に現れます。パピルスは繊維の向きが一定であるため、強度に方向性があり、裂けやすいという短所があります。また、硬めの表面を持ち、筆記の際にインクがにじみやすい場合もあります。
一方、紙は柔軟性と強度のバランスが良く、均一な表面と厚みを持ち、筆記や印刷に適しています。折ったり綴じたりすることも容易で、多用途に対応可能であるため、その後の出版や教育、行政文書などの分野でも幅広く活用されてきました。
こうして見ると、パピルスと紙は似た目的を持ちながらも、その構造や製法、使用感において明確な違いがあり、それぞれの文化や技術的背景を反映していることがわかります。
管理人のまとめ
今回は、パピルスと紙の違い?
圧力を加えた脱水シートか水中で抄くか
というお話でした。
パピルスと紙はどちらも
人類の情報伝達を支えてきた
重要な素材ですが、その構造と
製法には決定的な違いがあります。
パピルスは植物をそのまま活かした
圧力による脱水圧縮シート、
紙は水中で繊維を分離・再構築する
抄紙によって作られるものです。
この違いが、それぞれの筆記材としての
性質や用途を大きく左右してきました。
今日では紙が主流となっていますが、
パピルスのような古代の技術にも
学ぶべき点が多くあります。
自然素材の活かし方や脱水技術などは、
現代の持続可能な素材開発においても
ヒントとなるかもしれません。
素材の違いを知ることは、
単に歴史を理解するだけでなく、
今後の技術や文化のあり方を
見直す手がかりにもなるのです。
この記事がパピルスと紙の違いの
参考になればと思います。
パピルスと紙の違い、面白いですね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
パルプの性質と紙の強度の関係!長さと引張フィブリル化と引裂
⇒https://kamiconsal.jp/pulpkamikyoudo/
フィブリル化とは繊維が毛羽立つこと。絡めば紙が強くなる!
⇒https://kamiconsal.jp/fibrilka/
紙の透気度とは?一定量の空気が抜けるまでの秒数で表します
⇒https://kamiconsal.jp/kamitoukido/