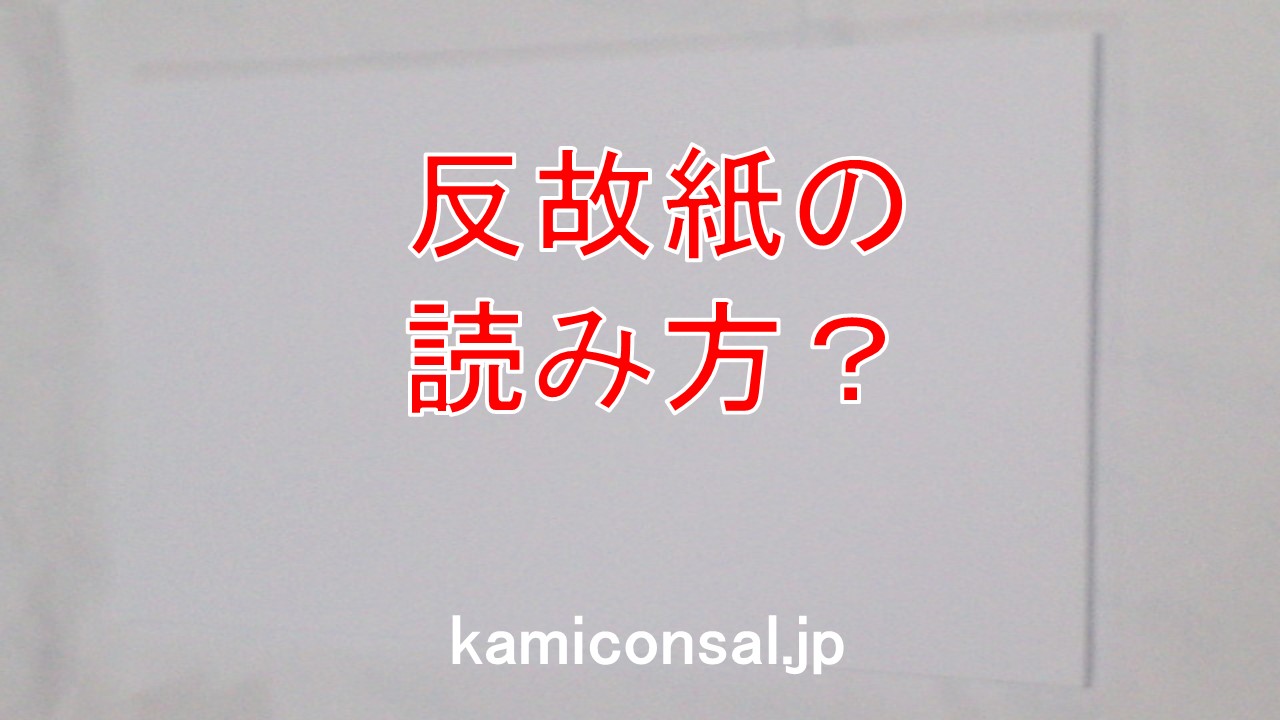この記事は約 7 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、反故紙の読み方は
「ほごがみ」や「ほごし」。
不要な紙のこと、というお話。
反故にする、という言い方があります。
だいたいは、以前にした言動などを
ないものとする。無効にする。と言う意味。
約束した側からすると「勘弁してください」
といいたくなる行動ですよね。
管理人も何度そんな目にあったことか・・・
それはいいんですけど。
その「反故にする」の元になったのが
反故紙ということになるそうです。
それはどういうことなのか?
ちょっと気になりました。
ということで。
この記事では反故紙の読み方は
「ほごがみ」や「ほごし」。
不要な紙のことについて
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
反故紙の読み方
反故紙の読み方についてですが、これは「ほごがみ」あるいは「ほごし」と読みます。読み方に複数のバリエーションがあるのは、漢字の訓読みと音読みの組み合わせによるもので、日本語特有の面白さが感じられますよね。
さて、「反故」という言葉の成り立ちを少し詳しく見てみましょう。
まず「反」という字ですが、これは「反対面」、つまり「裏側」「裏面」という意味を持っています。何かの反対、もしくは反転した側というニュアンスですね。単なる否定ではなく、物の裏側や、転じて使われなかった面のことを指すようです。
次に「故」は、「ゆえに」や「理由」、「いわれ」という意味があります。昔から「事故」や「故障」のように、何かしらの理由があって起きたことを意味する際に使われてきました。ここでは「理由があって」という意味で使われています。
つまり、「反故」は「理由があって裏面を使うこと」、または「表面が使えなくなった理由がある紙」といったニュアンスになります。
例えば、表に何かを書いたけれども内容を間違えてしまったとか、書き損じてしまったなど。そういった場合に、ただ捨てるのではなく、裏面を有効活用しようという意図が「反故紙」の概念です。
ちなみに「反」の読み方には「はん」「ほん」「そる」「かえる」「たん」などがあり、この中で「反故」の「反」は「ほん」と読むのが正しいとされています。
一方、「故」は「こ」「ゆえ」「もと」「ふるい」「ことさら」などの読み方があり、「こ」がこの場合の音読みですね。
この2文字を合わせて「ほご」と読み、それに「紙(かみ)」がついて、「ほごがみ」あるいは「ほごし」となるわけです。
読み方としてはこれで全体像がつかめたのではないでしょうか。漢字の成り立ちを知ることで、言葉の背景にある意味合いがより深く理解できるようになります。
反故紙について
さて、ここからは「反故紙」そのものについて、もう少し踏み込んでみましょう。
まず大前提として、反故紙とは再利用された紙のことを指します。現代のように紙が安価で大量に手に入る時代ではなかった昔、紙は非常に貴重な資源でした。そのため、できる限り何度も使いまわすという考えが基本だったのです。
紙が貴重だった時代では、一枚の紙を最大限に使い切る工夫がされていました。書き損じたらすぐに捨てる、ということはほとんどありません。表面に書いて間違えたとしても、裏面が使えるならそれを使うのが当然だったのです。
そのうえで、表裏の両面に書き終えた紙も、まだまだ役割がありました。たとえば、反故紙は単にメモ書きや草稿用として使われるだけでなく、襖(ふすま)や障子の裏打ち用の下紙として使われたり、物を包む紙として活用されたりしていました。
また、細かく裂いて構造材や断熱材として再利用されることもありました。つまり、「書く」「包む」「支える」「飾る」など、紙が持つ多機能性をフル活用していたのです。
その後、最終的には古紙としてさらに再生利用される流れになります。反故紙とは、紙が再生紙となるまでの途中段階で、非常に有効に使われていた紙だといえるでしょう。
このように、反故紙は一見「使えなくなった紙」「駄目になった紙」のように思われがちですが、実際には非常に機能的で、便利に再活用されていた存在だったのです。
管理人のまとめ
今回のテーマは、「反故紙」の読み方と意味についてでした。結論としては、「ほごがみ」や「ほごし」と読み、使い終わった紙や不要になった紙を再利用する文化の象徴ともいえる存在です。
「反故にする」という言い回しは、現代ではネガティブなイメージが強く、「約束を反故にする」などのように、無かったことにするとか、破棄するといった意味で使われることが多いですよね。
しかし、もともとの「反故紙」という言葉には、むしろ紙を最後まで大切に使うという精神が込められているともいえます。いわばリサイクルやサステナビリティの先駆けともとれる考え方です。
現代では紙が安価になり、気軽に使い捨てられる時代ですが、それでもこの「反故紙」の精神を忘れないようにしたいものです。無駄をなくし、資源を大切に使うという視点は、今なお私たちに必要な価値観だと思います。
ちなみに、現実の生活では「反故にする」ことを軽々しく言うような人が、エコやサステナブルを語ると少し違和感があるかもしれませんね。約束を守る、物を大切にする、それが本当の意味でのエコだと思います。
この記事が「反故紙」という言葉の理解を深める手助けになれば幸いです。紙という身近な資源に、もう一度目を向けて、大切に使っていきたいですね。
(参考)
こんな記事も読まれています。
襖の張り替えに茶ちり紙を使うのは?下地の凹凸や絵柄隠し!
⇒https://kamiconsal.jp/fusumanoharikaetyatirigami/
和室の障子の歴史は?原型は平安時代後期だが普及は江戸時代
⇒https://kamiconsal.jp/wasitusyoujirekisi/
和紙はリサイクルできるのか?金紙銀紙や障子紙は出来ません
⇒https://kamiconsal.jp/wasirecycle/