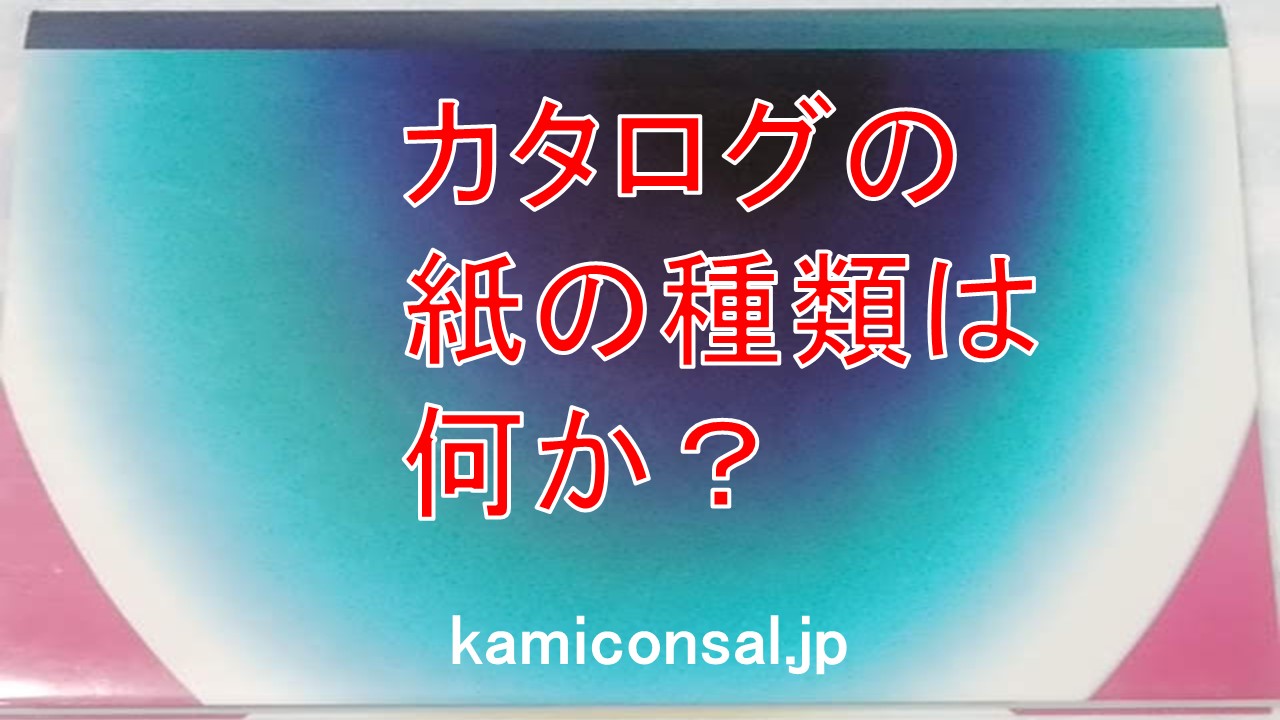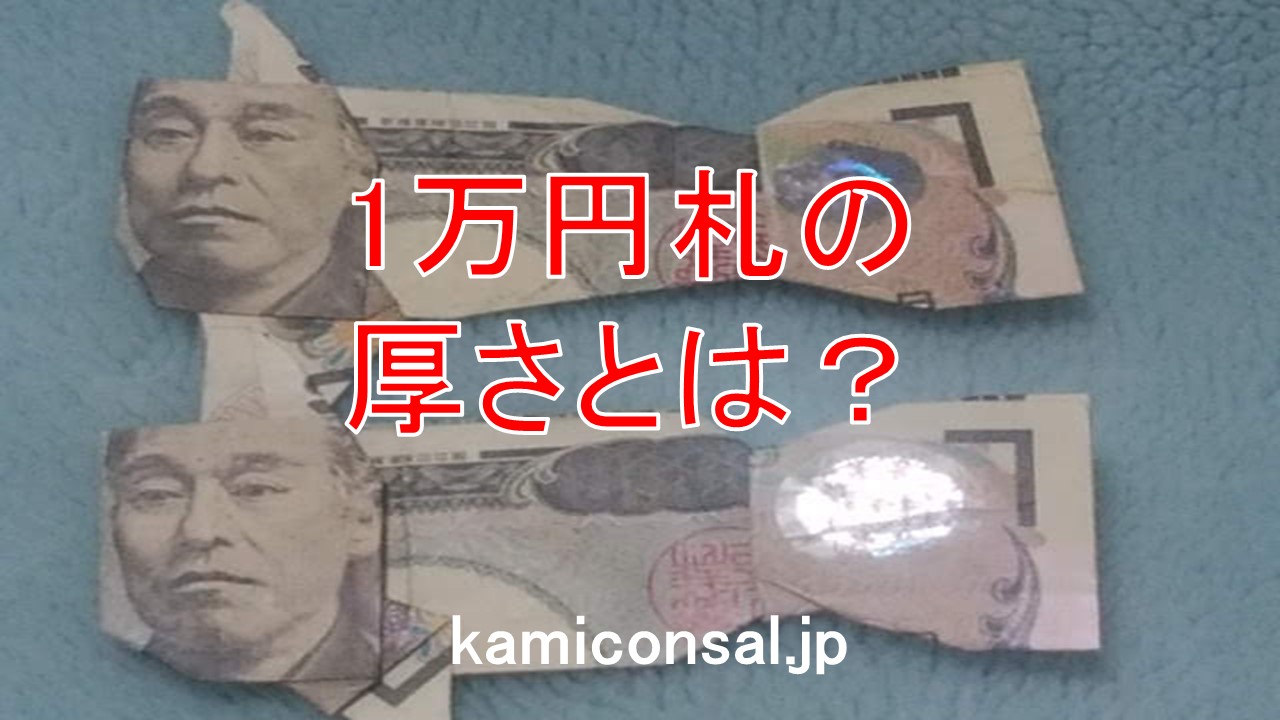この記事は約 10 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、カタログの紙の
種類は何かというお話。
管理人、カタログ用紙にも
少し関わったことがあります。
当時はまだ通販と言っても
通販カタログの時代。
スマホどころかネットもなかったですね~
通信手段が電話とFAXの頃です。
だから、電話やはがきでカタログの
冊子を取り寄せてそれ見て注文する。
決済もカードより銀行振込。
管理人の周囲の人は通販なんて
何送ってくるかわからん、という感じ。
スマホでアマゾン調べて衝動買いとか
今思えばありえない時代でした。
まあ、そういう時代ですから紙の
カタログがとても重要だったわけです。
ではこのカタログに使われる
紙の種類はなにか?
ということで。
この記事ではカタログの
紙の種類は何かについて
管理人の調べたことを
お伝えしたいと思います。
カタログの紙の種類は軽量コート紙
結論から申し上げると、カタログに使用される紙の種類は「軽量コート紙」になります。これは業界でも一般的に採用されている選択肢のひとつです。
紙の分類としてはA3コート紙に該当します。これはコート紙の中でも比較的軽量で、印刷用途に適した仕様となっています。
ただし、一般的に流通している標準的なA3コート紙とはやや異なり、実際には塗工量が若干多めに設定されていたと思います。これは印刷の品質を高めるための工夫の一環です。
このような仕様になっているのには、いくつかの理由が存在します。
まず第一に、通販カタログにおいては、紙の重量が非常に重要な要素となります。これは主に郵送コストに関係しています。
通販のカタログは、商品数が多いためページ数も自然と増加し、その結果として全体の重量も重くなりがちです。そのため、少しでも軽量な紙を使用することで、郵送にかかる費用を抑えることが可能となるのです。
そうした背景から、高級でしっかりした質感のあるA2コート紙よりも、より軽量なA3コート紙が選ばれる傾向にあります。
しかし、だからといって見栄えを犠牲にするわけにはいきません。通販カタログは、実物を手に取ることができない代わりに紙面上で商品を判断する必要があるため、印刷の品質が購買に直結します。
そのため、見栄えを保つために、通常のA3コート紙よりも塗工量を少し多くし、光沢感や発色を高める工夫がされていました。
さらに、こういったカタログ用の紙は、大量に生産されるため、ほとんどが特注品(特抄品)として作られていました。
紙メーカーが、特定の雰囲気や印象を出したいというクライアントの要望に応える形で設計されたものです。そのため、そのメーカー専用の仕様で作られることが多く、汎用品とは違った独自性がありました。
つまり、分類上はA3コート紙ではあるものの、品質的にはA2コート紙に近いものが提供されていたというわけです。
どちらにしても、通販用の紙は常に「重さとの戦い」になります。どれだけ軽く作れるか、そしてその軽さを保ちながら、どこまで見栄えを高められるか。
ギリギリのラインを見極めながら設計されていた、非常にシビアな現場だったと思います。
カタログの紙で苦労したこと
ここからは少し余談になりますが、管理人自身もカタログ用紙に少し関わったことがあります。
特に大変だったのは「色合わせ」の工程です。
通販カタログでは、紙面の色と実際の商品との色が一致していないと、顧客からクレームが入ることがあります。なぜなら、顧客はカタログの写真を見て商品を選ぶため、掲載された色が現物と異なっていると、大きな不満につながるのです。
この問題は特に女性向け商品で顕著で、微妙な色合いの違いにも敏感な傾向があります。そのため、わずかな色のズレが原因で返品に発展することもしばしばありました。
こうした状況が非常に厄介で、細かな調整が求められました。
具体的なエピソードを一つご紹介します。
管理人が関わったのは、女性用下着を扱うカタログでした。関わったと言っても、紙の色調調整を行う工程の一部を手伝った程度なのですが、それでも苦労は多かったです。
商品の色をカタログに正確に再現するため、印刷会社は事前に色見本(色校正)を作成し、メーカーに承認をもらいます。
しかし、その色校正の段階で、紙の色がばらついていては意味がありません。一定の色味を保った紙でなければ、いくら印刷を正確にしても意味がないのです。
この仕事がさらに難しくなったのは、1社購買ではなく2社購買の体制だったからです。
つまり、1社が最初に紙を開発し、もう1社が後追いでその紙を再現するという体制でした。管理人はその「真似する側」の立場だったのです。
簡単に思えるかもしれませんが、これは想像以上に厄介です。
紙というのは、同じ「白」と言っても微妙に色味や質感が異なりますし、製造マシンや原材料が異なれば、仕上がりの雰囲気も変わってしまいます。
たとえ最終製品の見た目は同じでも、原料が異なると微妙な再現性のズレが生じるのです。
これは、まるで豆腐でステーキを作ってくれと言われているようなもので、お手本があっても簡単には真似できません。
このような事情から、こういった場合は最初に作るほうが圧倒的に有利です。なぜなら、色や質感を自分で決められるからです。
真似するのは簡単だと思われがちですが、実際には非常に高度な技術と労力が求められます。
カタログの紙の怖いところ
さらにもう一つ余談ですが、カタログ用紙には「怖さ」もあります。
ここでいう怖さとは、主にクレームやトラブルのことです。
カタログの紙は軽量コート紙であることが多く、印刷には主に「オフセット輪転機(オフ輪)」が使用されます。これは非常に高速で印刷できる機械で、インクを強制的に乾燥させるのが特徴です。
この乾燥方法がくせ者で、たしか100℃以上の熱風でインクを乾かしていたと記憶しています。
インクだけを乾燥させるなら良いのですが、当然紙自体も熱にさらされるため、水分が急激に蒸発してしまいます。
その結果、紙の内部構造が弱かったり、塗工層が厚かったり、印刷でベタ(インク面積)が多かったりすると、紙面が一部膨らむ「ブリスター」という現象が起こることがあります。
これはミクロなレベルの現象ですが、仕上がりに影響が出るため、印刷物としては不良扱いになります。
もしこれが印刷後の検品で発見されればまだマシなのですが、製本後に見つかった場合には大変です。
その場合、倉庫に保管されている何万冊ものカタログを一冊ずつ目視で検品しなければならず、品質管理の担当者が総出で作業に当たる羽目になります。
この検品作業が、非常に神経を使う上に時間もかかるため、本当に大変なんです。
ブリスターに限らず、こういった欠陥は紙面の一部に過ぎなくても、本として完成した状態では非常に目立つため、問題視されやすくなります。
個人的には、今思い出しても背筋が寒くなるような作業でした。
大量生産が可能というメリットがある反面、それだけリスクも大きく、しかも利益はあまり出ないということで、できれば関わりたくないジャンルの紙だったと思っています。
管理人のまとめ
今回は「カタログの紙の種類」について、詳しくお話ししてきました。
結論としては、通販カタログなどには「軽量コート紙」が使われることが多く、分類上はA3コート紙となりますが、実際にはそのメーカーの要望に合わせた特注仕様(特抄品)で製造されることが一般的です。
その理由は、郵送費の削減を目的として、可能な限り紙の重量を抑えつつ、印刷品質を損なわないように設計されているからです。
また、管理人が関わった色合わせの工程では、非常に繊細な調整が求められ、多くの苦労がありました。特に他社製品の模倣となると、材料や製造方法の違いによって再現性が難しくなり、技術的にも高度な対応が必要でした。
さらに、ブリスターをはじめとした印刷・製本後のトラブルにも触れましたが、これも大量生産ならではのリスクの一つです。
品質を保ちながら、大量に安定供給しなければならないという点で、非常に神経を使うジャンルであることが伝わったのではないでしょうか。
この記事が、カタログ用紙についての理解を深める一助となれば嬉しいです。
ぜひ、今後カタログを見るときには、使われている紙の特性にも注目してみてください。カタログショッピングが、少しだけ違った視点で楽しめるかもしれません。
(参考)
こんな記事も読まれています。
厚紙の印刷はどこで出来る?キンコーズかネット印刷が便利!
⇒https://kamiconsal.jp/atugamiinsatudokode/
コピー用紙をコンビニ持ち込みできる?基本的に出来ません!
⇒https://kamiconsal.jp/copypaperconvinimotikomi/
紙の折り目を消す方法はある?低温でアイロンをかけるとマシ
⇒https://kamiconsal.jp/kamiorimekesu/