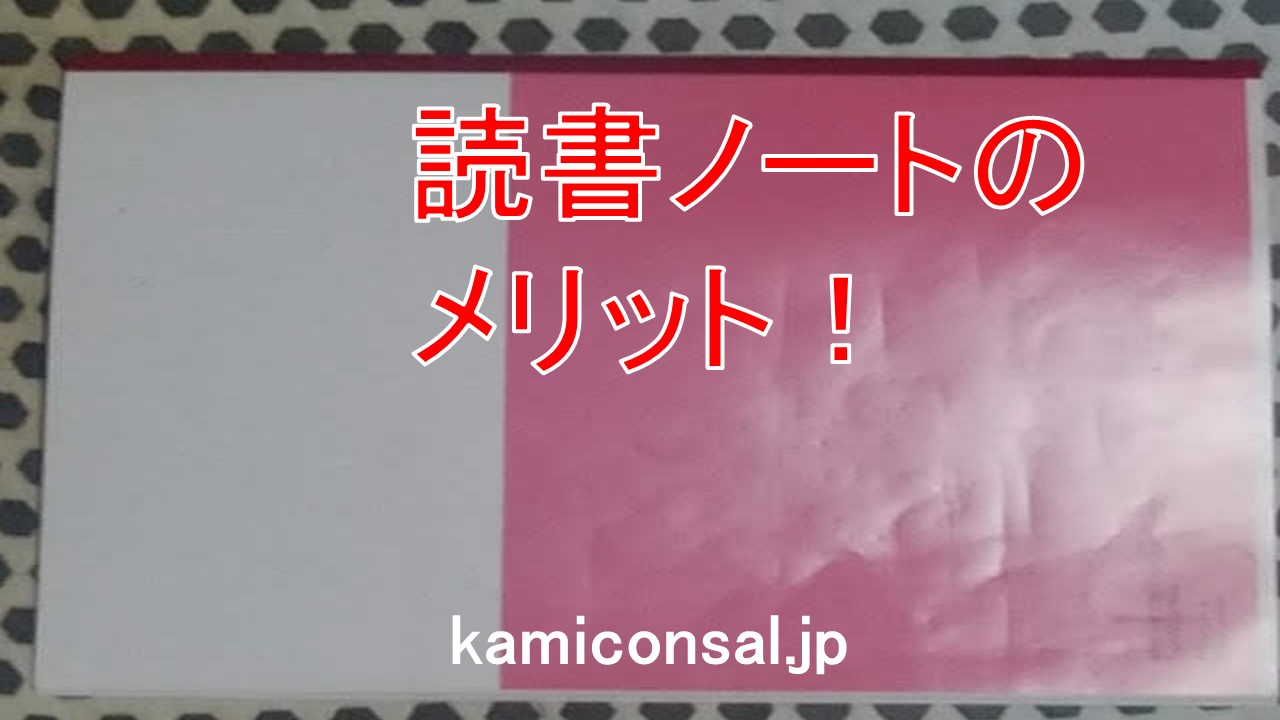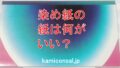この記事は約 11 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
読書ノートというと、まじめな学生や意識の高い読書家がつけるもの、というイメージがあるかもしれません。実際、管理人自身はこれまで一度も読書ノートを本格的につけたことがありませんでした。
それどころか、最近では本を読む機会すら減ってきてしまいました。読書ノートは良いものだとわかっていても、正直「面倒くさい」と思ってしまうのが本音です。
特に小説などの娯楽的な読書では、「ノートを作ってどうするの?」という疑問も湧いてきます。とはいえ、「やったほうがいい」と言われれば確かにその通りだとは思います。にもかかわらず、なかなか行動には移せない…そんな人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「読書ノートのメリットとは何か?」について、管理人なりに調べてみたことをまとめてご紹介したいと思います。少しでも自分や誰かの参考になれば嬉しいです。
読書ノートの最大のメリットは「理解の深化」
読書ノートをつける最大の目的は、読んだ内容をより深く理解することにあります。特にビジネス書や自己啓発本、歴史書、哲学書といった情報量が豊富で、抽象的な内容も多く含まれる書籍では、重要なポイントをノートに書き出して整理することで、記憶への定着や内容の整理が格段に進みます。
ただ読むだけでは、その場では「なるほど」と思っても時間が経つとすぐに忘れてしまいがちです。しかし、読書中に気になった箇所をその都度書き出したり、あとから要点をまとめ直したりすることで、「自分なりの解釈」や「著者の意図への気づき」が生まれるのです。これは、受け身の読書から一歩踏み込んだ、能動的な読書への転換とも言えるでしょう。
また、教科書や参考書など学習目的の書籍でも、ノートを取りながら読むことで内容の理解度が高まります。ただ漫然と目を通すだけでは頭に入りにくい内容も、「書く」という行為を通じて頭の中にしっかりと残りやすくなります。これは記憶の定着に大きく関わる「アウトプット効果」が働くためです。さらに、書きながら読むことで集中力も持続しやすく、眠気を防いでくれる副次的な効果も期待できます。
とくに管理人のように年齢を重ねて記憶力がやや心もとなくなってきた場合、「あの場面、誰が出てたっけ?」「この物語の主人公は何をしてたんだっけ?」といった細かな内容が曖昧になることもしばしば。そんなときにノートがあれば、すぐに見返して確認できます。記憶の補助ツールとしても非常に有効なのです。
読書ノートは「参照しやすさ」と「記録性」にも優れる
読書ノートのもうひとつの大きな魅力は、「必要な情報にすぐアクセスできる」という利便性です。本を読み返したいと思ったとき、「あのセリフどこにあったかな?」「このテーマについて書かれていたのは何ページだっけ?」と記憶を頼りに本をめくるのは、かなり手間がかかります。特に分厚い書籍であればあるほど、その労力は膨大です。
しかし、自分でまとめた読書ノートがあれば話は別です。重要な箇所を自分の言葉で要約し、引用も記載しておけば、目的の情報に素早くたどり着くことができます。いわばそれは「自分専用の教科書」や「知識の検索データベース」とも言える存在です。原文に忠実である必要はなく、自分が理解できる形でまとめられているからこそ、活用価値が高いのです。
また、読書ノートは単なるまとめではなく、「読んだという事実」の記録としても機能します。どの本をいつ読んだのか、どんな感想を持ったのか、何を学んだのかが一目でわかるため、時間が経ってから読み返すことで、そのときの自分の関心や問題意識の変化を振り返ることもできます。
これは自己成長の軌跡をたどるうえでも非常に有益です。数年前には感動して書き留めたフレーズが、今の自分には違和感を感じたり、逆に今の自分には深く刺さったりすることもあります。読書ノートは、そうした「思考と感性の変化」を記録する貴重なツールにもなります。
読書ノートの書き方ガイド:基本から応用まで
では、実際に読書ノートを作成するには、どのような要素を押さえておけばよいのでしょうか。基本的な記載項目としては、以下の内容が一般的であり、どのジャンルの本にも対応可能です。
- 書名(タイトル)
- 著者名
- 出版社名
- 発行年月日・初版日
- 読了日(読み終えた日)
- 本の概要・要約(章ごとにまとめるのも可)
- 印象に残ったフレーズや引用
- 自分の感想・気づき・考察
これらの情報に加え、以下のような応用的な工夫を取り入れることで、自分だけのオリジナルノートとして完成度を高めることができます。
- 小説なら人物相関図や時系列の整理(物語構造が把握しやすくなる)
- ビジネス書なら図解やマインドマップを使った概念整理
- イラストが得意な人は挿絵や図表を加えることで理解度を向上
- 読書の動機や当時の生活環境・心境を一緒に記録(背景がより鮮明に)
また、色分けやマーカーを活用して視覚的に整理することもおすすめです。たとえば、重要な引用には黄色、感想には青、疑問点には赤、といった具合にルールを決めておくと、後から見返すときにも情報の区別がしやすくなります。
読書ノートは決して正解があるものではありません。自分が理解しやすく、あとで活用しやすい形で記録することが大切です。形式にこだわりすぎず、自由で柔軟なスタイルで、自分だけの読書体験を記録していくことが、読書の価値を何倍にも高めてくれるのです。
読書ノートを「続けるコツ」:継続が何より大事
読書ノートは一度作って終わりではなく、継続することで初めて真価を発揮します。1冊だけ記録して満足するよりも、複数冊にわたって続けることで、自分の思考のクセや好みの傾向が見えてきます。しかし実際には、「面倒くさくて続かない」「書くことが浮かばない」といった悩みを抱える人も多いのが現実です。では、どうすれば読書ノートを無理なく続けられるのでしょうか。以下のような方法を実践することで、負担を減らしながら継続の習慣が身についていきます。
- ノートは大きな文字で、行間を広めに書く:詰めて書くよりも、見返しやすさを優先することが大切です。余白があることで、後から追記やコメントも入れやすくなります。
- 気になったページに付箋を貼っておく:読書中にすぐ書けないときは、まずは「目印」を付けるだけで十分。あとから思い出しやすくなります。
- 写真やチラシなど関連する資料を貼る:視覚的な記録は記憶の定着に効果的です。旅のガイド本や料理本など、実物と結びつけると印象も強まります。
- 引用したい部分をその場で書き写す:面倒でも写すことで内容が頭に入りやすくなります。書くことでその言葉の意味がより深く理解できます。
- 感情や感想をそのまま言葉にする:論理的である必要はありません。「おもしろかった」「共感した」など、自分の素直な気持ちを大切にしましょう。
- 完璧を目指さず、とにかく書くことを優先:体裁や構成を気にしすぎると手が止まってしまいます。とにかく「書くこと」に意識を向けるのがコツです。
- 読み終えた直後にノートを書く習慣を作る:内容が記憶に新しいうちにまとめることで、思い出しやすく書きやすくなります。時間が経つほどハードルが上がります。
とにかく「シンプルに・気軽に・早く書く」ことを心がけましょう。最初から力を入れすぎると、かえってハードルが上がって続かなくなります。肩の力を抜いて、「雑でもOK」「今日は1行だけ」など、自分なりの基準を設けておくと気が楽です。特に重要なのは、完璧を目指さないという姿勢。多少内容が抜けていても、間違っていても、書いたこと自体に価値があります。
「完璧じゃないけど、とにかく書いた」——このスタンスこそが長く続ける最大のポイントになります。続けるうちに自然と自分なりのスタイルやテンプレートができてきて、「あまり考えずに書ける」ようになります。最初は試行錯誤でも、少しずつ積み重ねることで、気づけば「読書がもっと楽しくなる」そんなサイクルが生まれていくでしょう。
管理人のまとめ:読書ノートは「やらないよりやる」が正解
今回は「読書ノートのメリット」について、特に理解が深まる、参照がしやすい、記録として残るといった側面を中心にご紹介しました。日々の読書にひと手間加えることで、その内容がより自分の中に定着し、学びや気づきとして活かしやすくなります。読書は受け身の行為になりがちですが、ノートを通じてアウトプットすることで、より能動的な体験へと変わっていきます。
読書ノートを書くことによって、単なる「読んだ」という事実だけでなく、何を感じ、どんなことに関心を持ったかまで記録されます。その記録が積み重なれば、自分の成長や興味の移り変わりを振り返る貴重な材料になります。また、同じ本を再読したときに以前のメモを見ることで、新たな発見や比較ができるのも大きな魅力です。
もちろん、最初から完璧なノートを作ろうとする必要はありません。むしろ最初は箇条書きや一言メモから始めて、無理なく自分のペースで続けるのが長続きのコツです。堅苦しく考えず、思いついたことを自由に書くことが、結果的に最も実用的なノートになります。
「面倒くさい」「うまく書けない」と感じる方こそ、あえて形式にこだわらず、ラフに書いてみることをおすすめします。まずは手を動かすこと。そこからすべてが始まります。読書ノートは義務ではなく、自分の読書体験を深めるためのツール。気楽に始めてみてください。
日々の読書がより充実し、学びや気づきにあふれたものとなるよう、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
(参考)
こんな記事も読まれています。
デジタルノートのメリット。複数のノートを持ち歩く必要がない
⇒https://kamiconsal.jp/diditalnotemerit/
手帳やノートがなくならない理由。合理性だけではないから?
⇒https://kamiconsal.jp/tetyonotenakunaranai/
カラーノートは目に優しい?視覚過敏があってもなくても楽!
⇒https://kamiconsal.jp/colornotemeniyasasi/