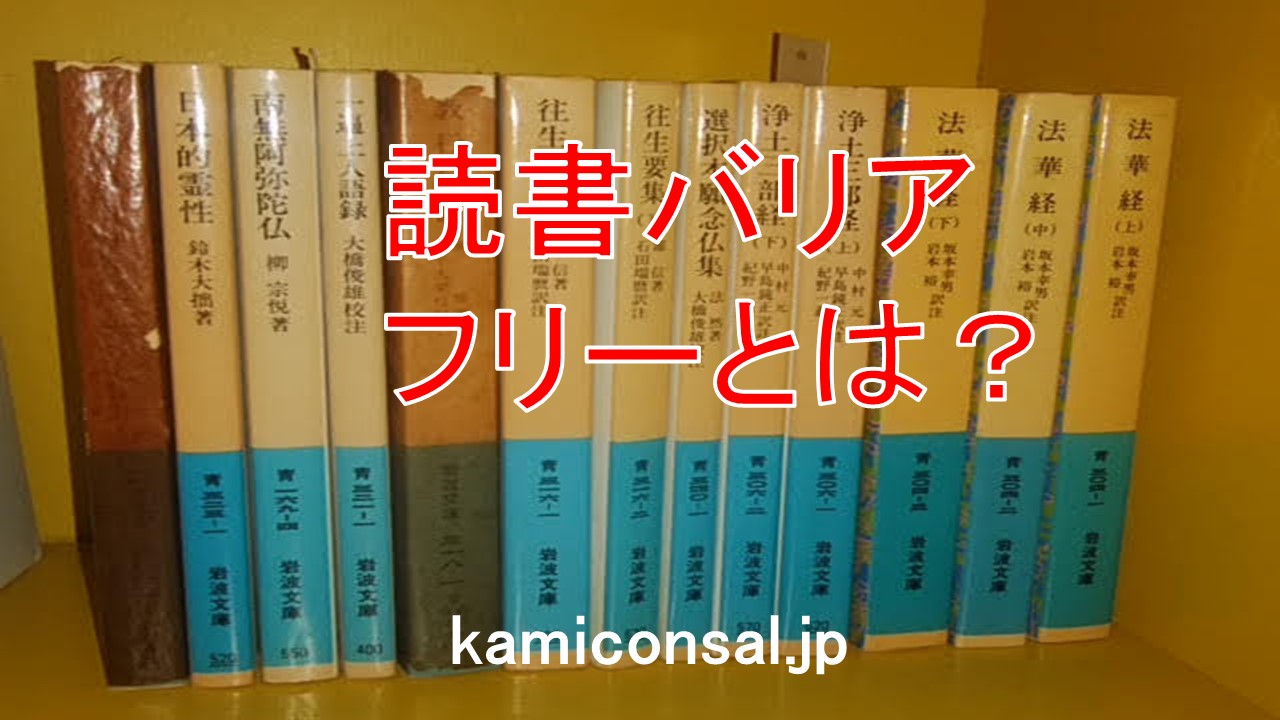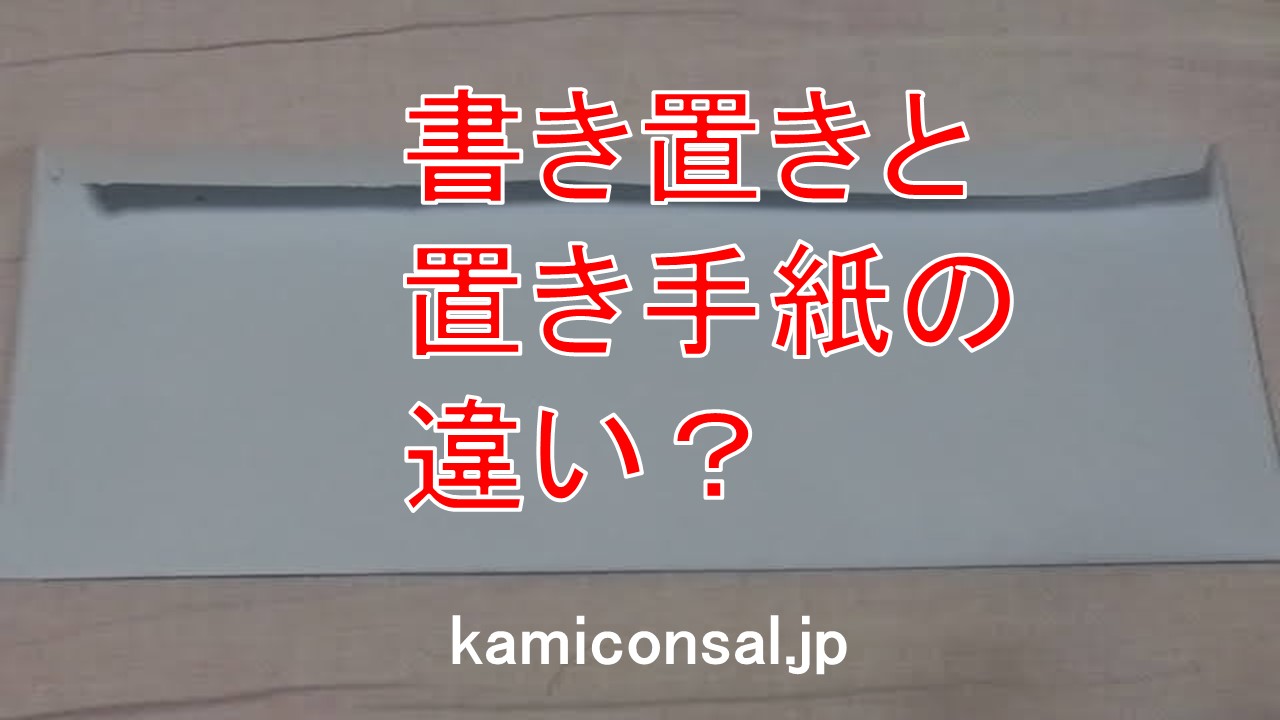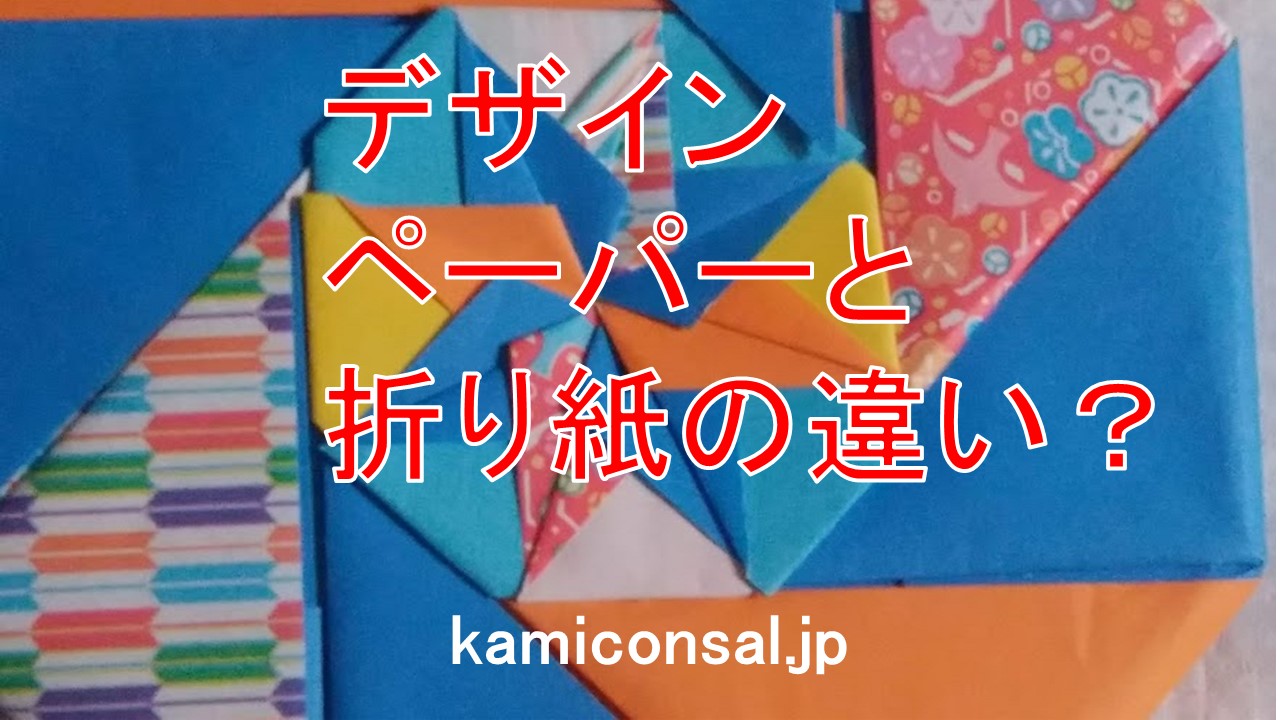この記事は約 9 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、読書バリアフリーとは?
障害の有無に関わらず読書できる環境
と言うお話。
管理人、読書バリアフリーという
言葉を知らなかったんですが。
ニュースで芥川賞のことを見て
そういうのがあるのかと。
これですね。
市川沙央さんの著作。
管理人は内容は読んでいませんが
市川沙央をテレビで見たんですよね。
新聞のニュースでも見ました。
これをみてああそうか
紙の読書って大変だと。
障害を持つ人がどれほど大変な
思いで読書をしているのか。
管理人には思いも及ばない世界です。
なにしろ、本のページをめくる
その重さがつらいそうですから。
こういう人のためにも読書バリアフリーは
実現していかなければいけないと思います。
ということで。
この記事では読書バリアフリーとは?
障害の有無に関わらず読書できる環境
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
読書バリアフリー法が2019年6月に成立
管理人は正直、この法律の存在をまったく知りませんでした。
しかし実は、2019年6月に「読書バリアフリー法」という名の法律が、日本で正式に成立していたのです。
文部科学省の公式ホームページには、この法律についての情報が詳しく掲載されています。
⇒誰もが読書をできる社会を目指して~読書のカタチを選べる「読書バリアフリー法」~(啓発用リーフレット)
文部科学省のHPによると、
この法律の正式な名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」とされています。
初めて聞いたという方も多いかもしれませんが、読書環境を整えるための法律が、すでに存在しているのです。
では、この法律は具体的にどのような目的をもって制定されたのでしょうか?
==ここから==
障害の有無に関係なく、すべての人々が、読書によって文字・活字文化の恩恵を受けられることを可能にするための法律です。
視覚障害や身体の不自由さを持つ方を含め、あらゆる障害を抱える方が、読みやすい形式で書籍の内容に触れることができるようにすることを目的としています。
==ここまで==
つまり、読む力に制限のある方々も、読書の機会を失わないようにするための取り組みがこの法律なのです。
では、この法律の施行によって、どのような点が実際に変わるのでしょうか。
これも同じ文部科学省のページに具体的な記述があります。
==ここから==
紙の本
これまでの点字本に加え、文字の大きさやフォントを変更して、視認性を高めた書籍も手に入りやすくなります。視力に不安のある方や高齢者にも読みやすい仕様の本が増えることでしょう。
デジタルの本
パソコン・タブレット・スマートフォンといったデバイスを活用して、ユーザーが自分に最適な方法で読めるようになる書籍が拡充されます。
- 文字の大きさや色の変更が可能
- 音声で内容を読み上げる機能
- 漢字にふりがなを自動表示
- スイッチでページをめくる操作
==ここまで==
こういった多様な機能によって、従来の読書のスタイルが大きく変わる可能性があります。
管理人としては、今後の読書環境は紙の本からデジタルブックへと主流が移っていくのではないかと考えています。
というのも、紙の本はどうしても障害のある人にとって扱いづらい側面があるからです。
点字の本は確かに存在していますが、それはあくまで視覚障害者向けの特化型書籍であり、すべての障害に対応しているわけではありません。
たとえば、芥川賞作家の市川沙央さんは、「先天性ミオパチー」という筋力が低下していく難病を抱えておられます。
この病気の影響で、紙の本を自力でめくるだけの筋力さえ持ち合わせていないそうです。
このような状況下では、読書は日常の中の楽しみどころか、大きな障壁となってしまいます。
それならば、デジタルブックや音声読書のように、操作が簡単で補助機能のついた形式の方が、ずっと現実的で親切と言えるでしょう。
ページ送りが簡単にできるだけでなく、内容を自動で音読してくれる機能もあるなど、読書のバリアを大きく下げる助けになります。
実は管理人は元々、製紙会社に勤めていた経験があるため、紙の書籍の良さをできるだけ強調したい気持ちもあるのですが、
このバリアフリーという視点で考えると、どうしても紙の本の優位性は見つけにくいのが正直なところです。
現代のバリアフリー読書を支えるのは、やはり音声読書のようなデジタルサービスになっていくのではないでしょうか。
⇒オーディオブック配信サービス – audiobook.jp
![]()
読書バリアフリーから考えると紙の本は贅沢なのか?
ここからは余談になりますが、今回、読書バリアフリー法について少し調べてみて、あらためて感じたことがあります。
紙の本で読書するという行為は、障害のある人にとっては想像以上にハードルが高いのではないかということです。
管理人は、特に何の支障もなく、普通に目で本を読み、手でページをめくっています。
視力もあり、腕や指先に問題があるわけでもなく、本を読むのはごく日常的な行動です。
けれど、そんな「当たり前」のことが、実は一部の人にとっては「贅沢なこと」だったのかもしれません。
「普通」の行動ができることを、深く考えたことがなかった自分にも驚きました。
たとえば、紙の本をめくれない人がいるということさえ、これまで全く想像したことがありませんでした。
今回の調査でようやく、「筋力が低下する病気の人なら確かにそうかも」と気づいたくらいです。
ページをめくるという行為が、当たり前すぎて、その動作が困難な人の存在に思い至らなかったのです。
このような視点の変化こそが、バリアフリーの本質なのかもしれません。
自分にとっては当然のことが、他の人にとっては大きな障壁になる――。
こうした気づきを得ることで、私たちは少しずつ、より優しい社会へと歩んでいけるのではないでしょうか。
管理人のまとめ
今回は読書バリアフリーとは?
障害の有無に関わらず読書できる環境
というお話でした。
管理人は読書が難しいと
思ったことはありません。
しかし世の中には紙の本をめくるのが
つらいと言う人もいるんですね。
読書バリアフリーというのは
目の見えない人がメインですが
それ以外にも様々な理由で
読書が難しいと言う人がいる。
そう思うと普通に本が読めるのは
ありがたいことなんだと思います。
そしてこういう人のためには
デジタル本が必要なのかなと。
だれもが読書しやすい環境が
整っていくといいですね~
この記事が、読書バリアフリーの
参考になればと思います。
読書バリアフリー、
上手く行って欲しいですね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
電子書籍は高い?イメージの問題で今は紙より安いことが多い
⇒https://kamiconsal.jp/densisyosekitakai/
読書は紙か電子書籍か?文字主体なら紙のほうが良さそうだが
⇒https://kamiconsal.jp/dokusyokamiensi/
紙の書籍が好きな理由。めくる感覚や手触り、目が疲れにくい
⇒https://kamiconsal.jp/kamisyosekisuki/