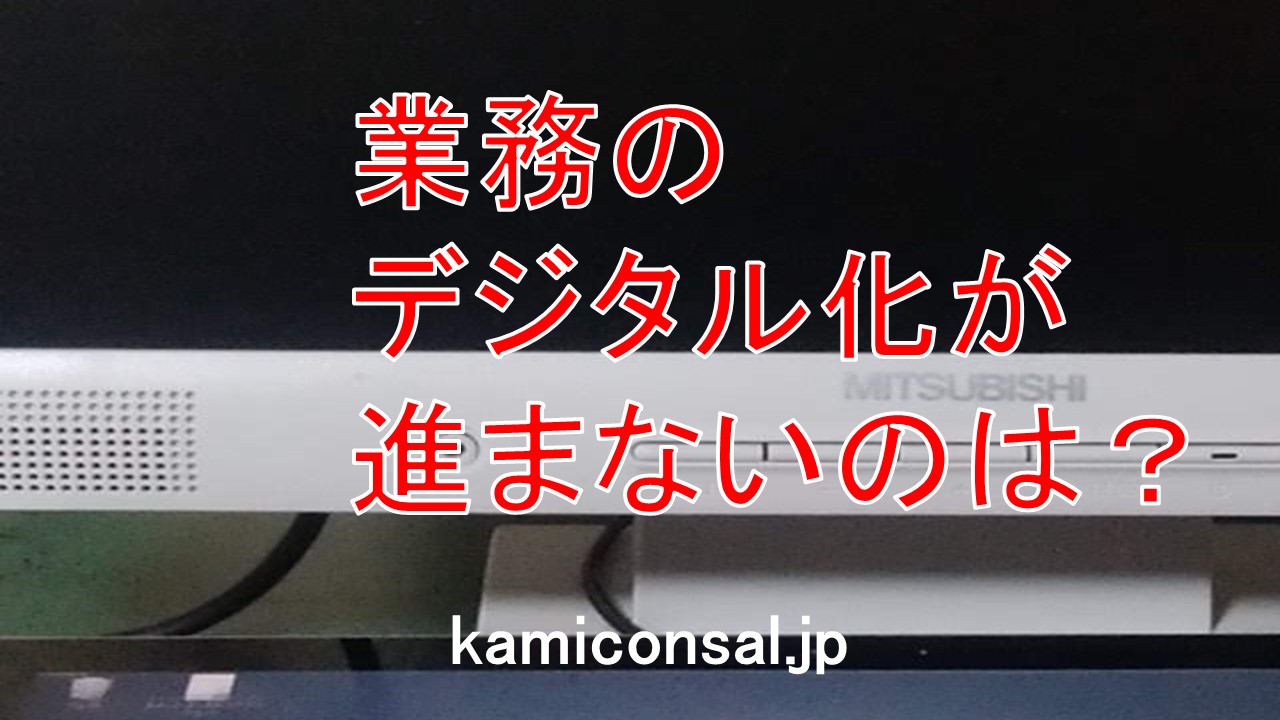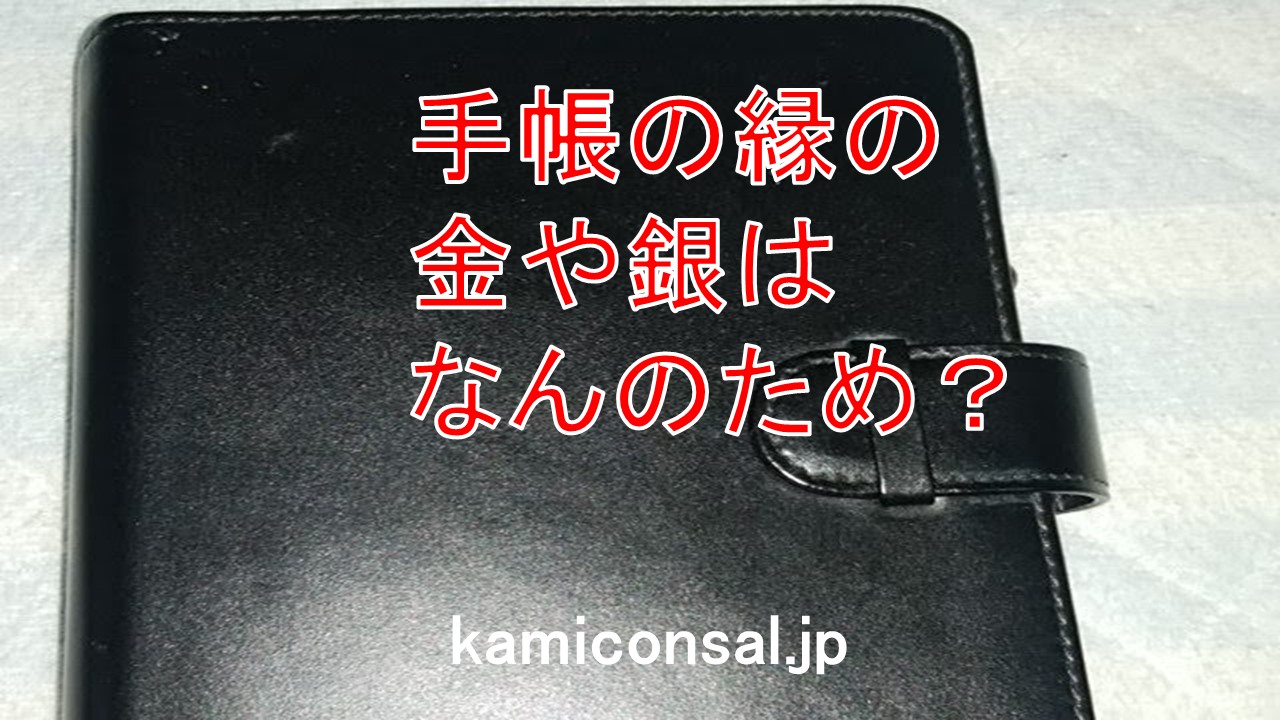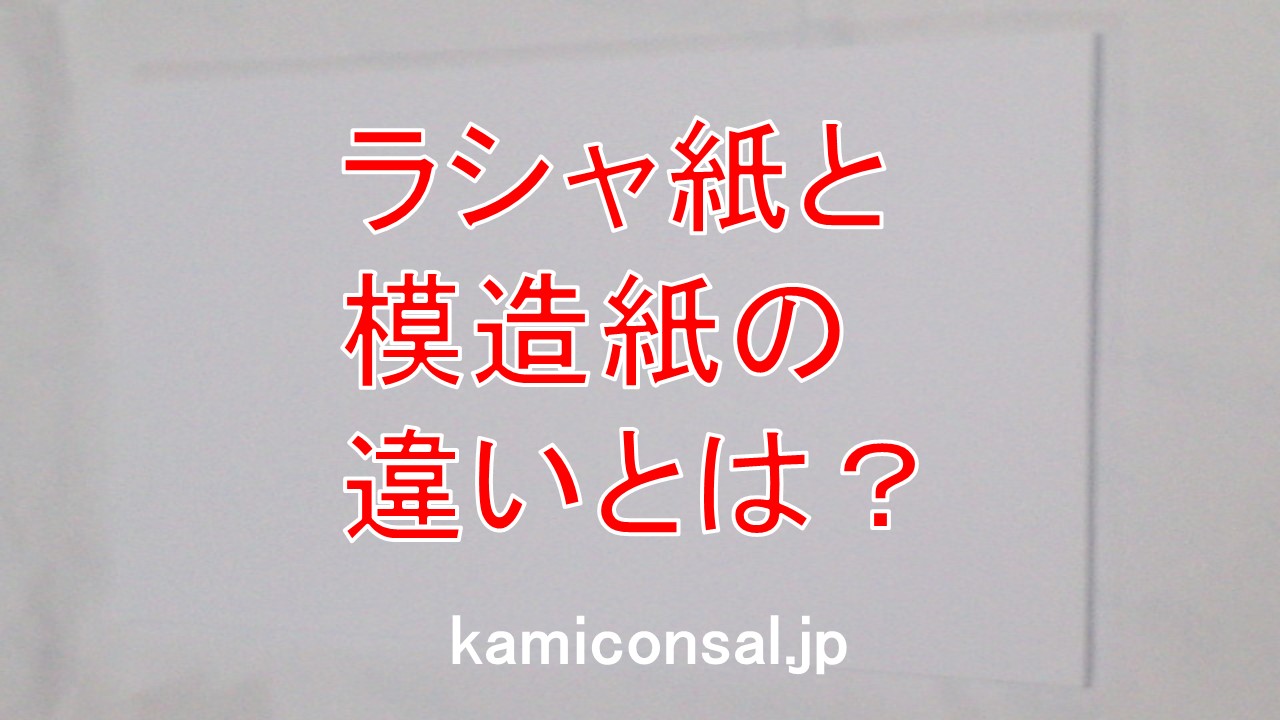この記事は約 8 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、業務のデジタル化が進まないのは?
書類にペンで署名が9割!というお話。
管理人、古い人間ですから
書類に印鑑は当たり前でした。
大した会社じゃないのにというか
大した会社じゃないからなのか
どれだけの人間に印鑑を押させるのか
というくらい印鑑をもらってましたね。
製紙会社というのは保守的だし
設備を動かすとお金がかかる。
技術部や開発部にいたときに
ちょっとテストをお願いすると
関係部署の部課長に計画書の印鑑を
もらうだけで何日もかかるとか。
当時からバカバカしいと思ってましたが
今思えばもっとバカバカしいんですよね。
相手の部長や課長がまともな人なら
それも仕方ないと思うんですが
かなりピントが外れていたり
意地が悪い人もいました。
どういうわけか怒り狂うとか。
人としておかしい人も多かった。
今思えば自分の判断ミスにはしたくない
という保身が相当強かったんでしょう。
だからなかなか印鑑を押さない。
承認がないとテストは出来ませんから
担当者としては困ってましたね~
しかし今は違う。
ネットがあるので、書類の内容さえ
不備がなければ簡単に承認できる。
作成者本人の説明が必要なときだけ
呼び出して確認すればいい。
それも無理に目の前に立たさなくても
チャットなどで確認することも出来る。
データ管理さえきちんと出来れば
もう紙の文書は不要なはずなんです。
しかし。
実際は業務のデジタル化は進まない。
2019年の調査では中小企業の9割が、
書類にペンで署名しているそうです。
またその中の6割がそれを紙で
保管していると回答されたようです。
これではね~、という感じ。
ではなぜそうなるのか?
ということで。
この記事では、業務のデジタル化が
進まない理由が何なのかについて
管理人の調べたことを
お伝えしたいと思います。
業務のデジタル化が進まない理由
管理人の考えをとりあえず2つお話します。
仕事のやり方を変えたくない
管理人の考えとしては。
業務のデジタル化が進まない一番の
理由は仕事のやり方を変えたくないから。
特に会社の中の上層部が変化を嫌う。
そうするとどんなに頑張っても
デジタル化なんて進まない。
先程もお話しましたが、報告書を
持ってこさせて机の前で説明させる。
こういう報告スタイルを続ける限り
紙の書類がなくなることはない。
上司としては自分が上だという
立場を確認できる場になります。
こういう習慣なくすのは難しい。
目の前の上司なのにメールで報告とか
血が通っていないと言われたりしますが
しかし、そういう部分を認めないと
業務のデジタル化は難しい。
目の前の人に説明するなら紙の
書類が使いやすいですからね。
そこにいるんだから声をかけろ
という感覚を変えられるかどうか。
多分、本当のペーパーレス化は
こういうところを受け入れられるか、
ということで出来るかどうかが
決まってくるように思うんです。
正直言うと、管理人の世代は無理。
目の前にいれば話しかけますから。
管理人の感覚では40代以下
じゃないと無理なんじゃないかなと。
結局、隣りにいても地球の裏側にいても
ネットでつながれば同じという感覚が
普通になった世代が上司になるまで
業務のデジタル化は難しいでしょう。
まあそうなれば、オフィスに出勤する
意味もなくなるわけですけど。
デジタルデータの保管管理を信用できない
管理人が思うもう一つの理由はデジタル
データの保管管理を信用できない、です。
これも若い人はそうでもないんでしょうけど
年配になるほど信用できないんですよね。
紙の書類でも整理が悪ければ
紛失してしまうわけなんですが
デジタルデータは誤って削除
したり流出したりするわけです。
ネットのことが分かっていない人ほど
よく分からずにミスをするんですよね。
これは怖い。
ただこの点は本当に分かっていない
自覚があればその部分は任せればいい。
中途半端なのが一番困ります。
それから、データ保管で気になるのは
運用を守らない人がいると困ること。
作成した書類を所定のところに保存
しないとか勝手な名前をつけるとか。
これをやられるともう収拾がつかない。
今は検索技術が良くなったので
あまり気にならないかも入れませんが
いずれにしてもデータ管理において
運用ルールを無視するのは最悪。
それで、そういう事をするのが
上層部だったりするんですよね。
無理を通そうとする。
こんな状態で業務のデジタル化は
うまくいくわけないんですよね~
下手にやると泥沼にはいりますから。
そうそう、デジタルデータへの不信感は
停電したら業務が止まるというのもあります。
そういう対策はあるんですけど
それでもなお心配をする。
よく知りもしないのにサーバーは
大丈夫かとか言ってみたり。
そうなるとどうしても紙の書類にペンで
署名して印鑑を押したものを保管となる。
これはこれで、膨大になるので
費用もかかるんですが
物質として目に見えたほうが
安心だということなんでしょう。
こういう感覚が変わらない限り
業務のデジタル化は難しい。
管理人は古いタイプだから
難しい側かも知れません。
管理人のまとめ
今回は、業務のデジタル化が
進まない理由というお話でした。
管理人の考えでは仕事の
やり方を変えなければ無理。
上司と部下の報告という
コミュニケーションとか
データの保管という
基本的なところとか。
そういう部分がデジタルでいい、
紙はいらないとなるまで難しい。
ということでした。
そういえば。
天体の天動説が地動説に変わったのは
天動説派がみんな引退してからだとか。
それくらい人の思想は変わらない。
正直言うと。
紙の書類で仕事をしていた人が
みんな引退してようやく本来の
業務のデジタル化が進む
のではないかなと思います。
あと10年くらいかかる気もしますが。
この記事が、業務のデジタル化が進まない
理由の参考になればと思います。
業務効率、上げましょうね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
裏紙の再利用は危険?コピー機にもセキュリティ的にも悪い!
⇒https://kamiconsal.jp/uragamisairiyou/
紙を破るとストレスが発散?書いて破って「スカッとノート」
⇒https://kamiconsal.jp/kamiyaburustress/
紙に書き出す効果とは?モヤモヤのストレス軽減になるのか?
⇒https://kamiconsal.jp/kaminikakidasukouka/