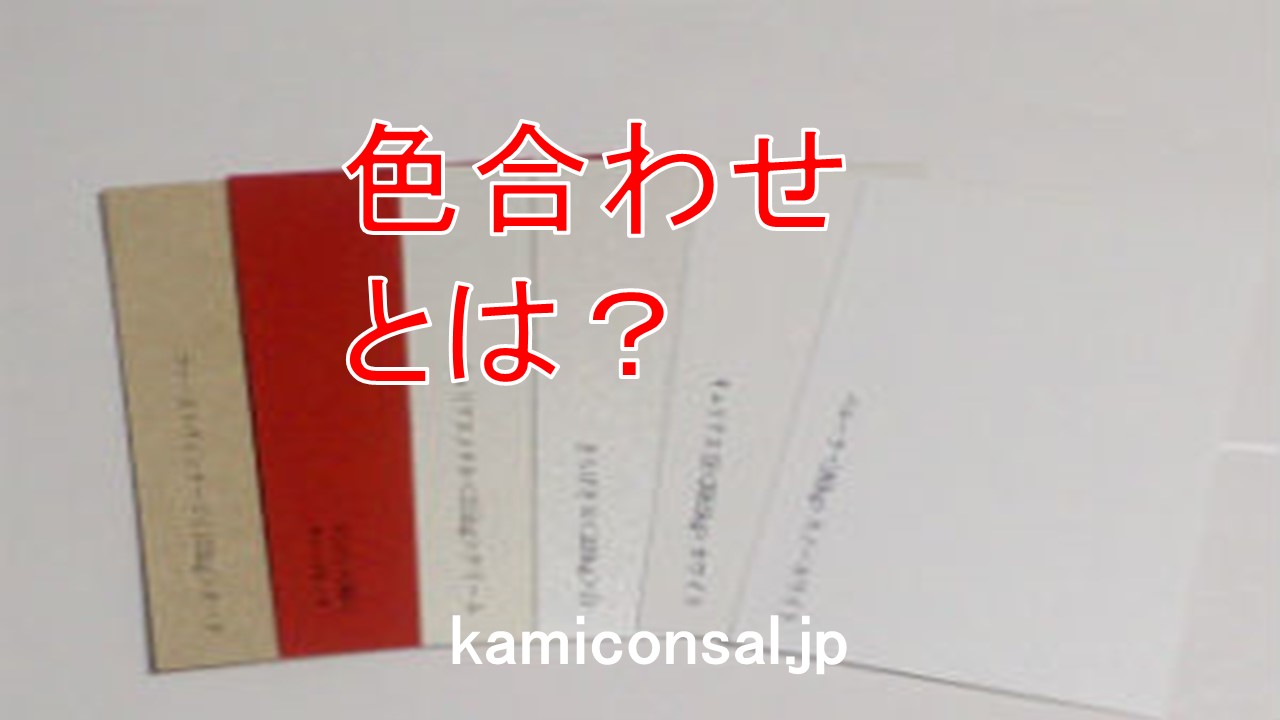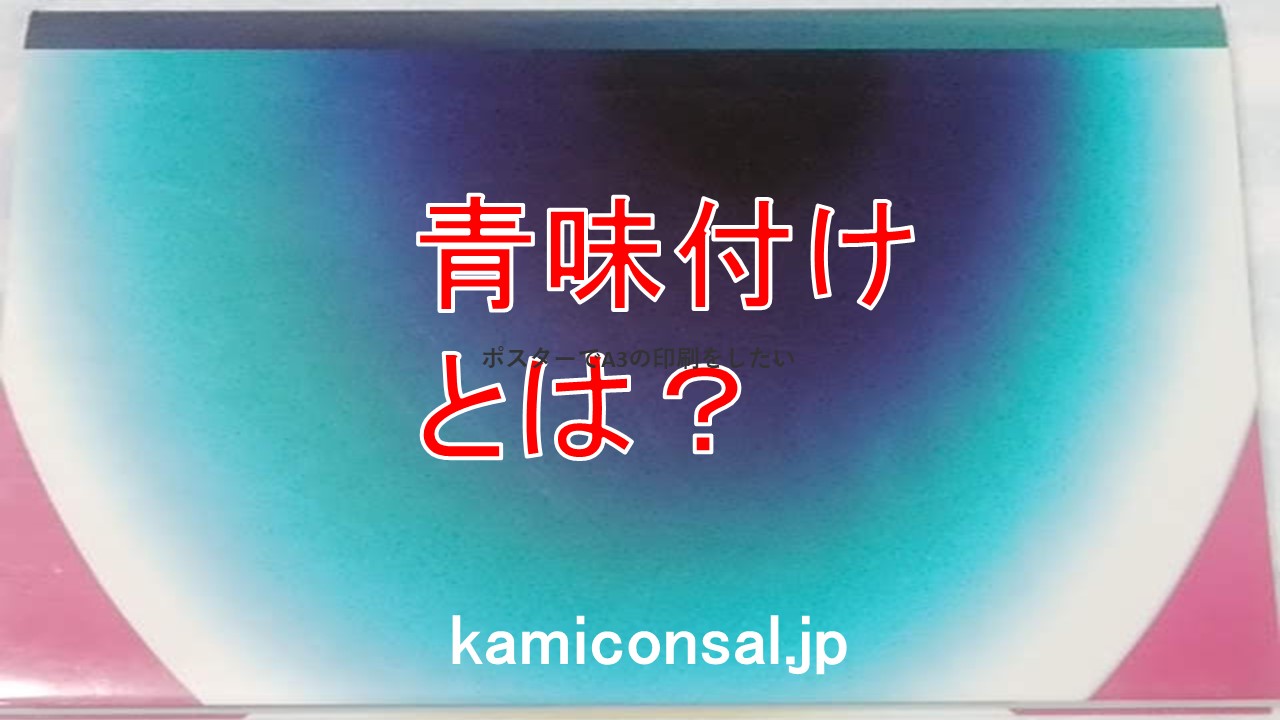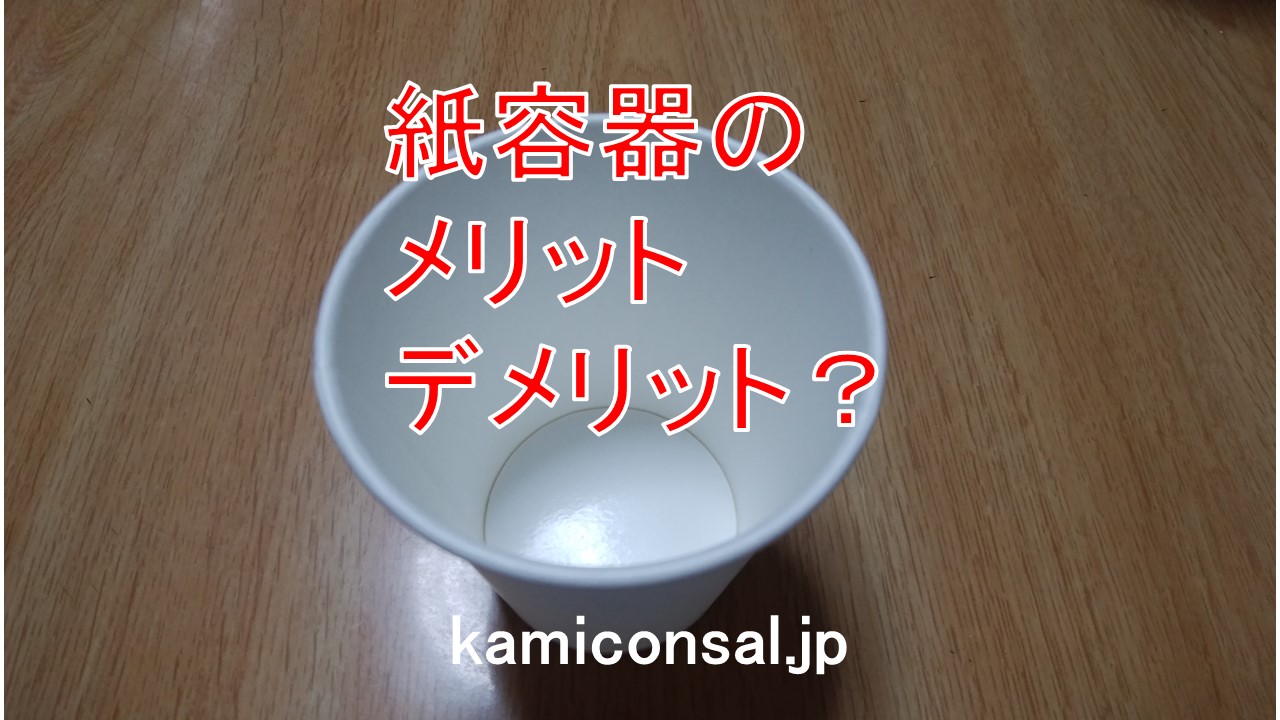この記事は約 12 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、色合わせは紙にもある?
白色も微妙に違うのでかなり難しい!
というお話。
管理人は元製紙会社社員。
紙の開発なんかもやりました。
といっても管理人の場合はレベルが低くて
とりあえず他社品の真似をする感じでしたが。
それはそうとして
管理人が担当していた印刷用紙。
本当に技術的に難しいのは
印刷の仕上がりなんですが
とりあえずよくにたものを作るなら
まずは見た目を真似しないといけない。
その第一歩が色合わせってことです。
紙なんてだいたいなんとなく白いし
それに差があるのかと思いますが
実際に細かく見ていくとこれが
色んな色があるんですよね~
正直言って全く同じ見た目は無理。
でも出来るだけよく似たものにする。
それが意外と難しかったりします。
ではどんなことをやっていたのか?
ということで。
この記事では、色合わせは紙にもある?
白色も微妙に違うのでかなり難しい!
について
管理人がやってきたことを
お伝えしたいと思います。
色合わせは紙にもある。そもそも他社と同じ色にはならない?
それで紙の色合わせなんですが、これがまた意外と複雑で奥が深い作業なんです。
まず初めに行うのは、他社が使用しているサンプル品の徹底的な調査です。とにかく情報を集めて、基準となるデータを把握します。
管理人の場合、とりあえず見るべき基本的な物性項目は外せません。たとえば米坪、紙厚、平滑度、白色度、不透明度、色差(Lab)、灰分、白紙光沢、そして印刷光沢といった項目が中心となります。
もし対象が塗工紙であれば、さらに塗料の顔料比率をチェックし、必要に応じて紙の断面写真を撮って構造の確認も行います。
次に重要なのがパルプ配合の割合や構成です。パルプが何からできていて、どのような比率で混ぜられているかというのは、最終的な紙の色や質感に大きく影響を及ぼします。
顔料の比率に関しては、X線による元素分析を用いて構成を明らかにします。パルプの構成は紙を一度離解し、顕微鏡で観察することで、どのような種類の繊維が使われているかを分析します。
こういった作業を全部自分で行うことも可能ですが、電子顕微鏡やX線装置の操作には専門の試験員に依頼することがほとんどです。試験機器の数も限られているため、実際には数日から一週間ほどかかることもあります。
正直に言って、本当に一致させなければならないのは紙厚や白紙光沢といった部分です。紙が薄ければ不透明度の調整も不可欠になってきます。
そして何よりも重要なのが「色調」なんですよね。
で、色合わせについてですが、紙厚に関しては米坪を増やせばある程度調整できますし、白紙光沢を上げるためには塗工量を増やせば対応できます。もちろん、これらはコストが増加する原因にはなりますが、やろうと思えばなんとかなる領域です。
ところが、色調だけは全く別の問題です。
本当に全く同じ色を再現するためには、分光光度計を使って光の反射率曲線、いわゆる分光反射スペクトルを完全に一致させなければなりません。しかし、それは現実的にはほぼ不可能に近い作業なんです。
その理由は非常にシンプルです。
まず他社が使用しているパルプの種類や染料が、自社とはまるで異なっています。原料となる木材自体が違う産地や種類で、クラフトパルプであれば、蒸解の方法や漂白工程も各メーカーで大きく違ってきます。
古紙パルプを使う場合でも、漂白に使われる脱墨剤は各社で異なっており、同じように見えても実際にはまったく違うものが使われています。
さらに言えば、同じ会社内でも工場が違えば薬品の種類や調合方法が異なってくることはよくあります。
とどめに、古紙を原料とする場合は原料そのものがまちまちです。その時々で入ってくる紙が異なれば、品質もばらつきが出ます。
そして、もうひとつ大きな要因として「水」があります。
紙漉き工程では、パルプ濃度はわずか1%程度。つまり残りの99%は水で、それを脱水して紙を作っていきます。
当然ながら、この水の質が色に与える影響は非常に大きいです。
例えば、例として挙げられるのは大雨の後。大量の雨水が混じることで取水地の水が濁り、結果的に紙の白色度が下がるという現象がよくあります。
どれだけ濾過を行ったとしても、水の状態が悪ければ何らかの影響は避けられません。
目標の紙の白色度がもともと低ければ誤差として処理できる場合もありますが、上質紙系であれば要求される白色度が高いため、最悪の場合、基準値に達しないこともあるのです。
そうしたときには、「基準値の下限で許してほしい」と交渉するような、品質管理としてはちょっと疑問が残るような場面も経験してきました。
もちろん、こういった苦労以上に厄介なのが染料の問題です。
染料は一種類ではありませんし、供給元となるメーカーも複数存在します。さらには同じ会社でも、使用するマシンによって染料の設定や調合が異なるケースも多々あります。
ですから、見た目が似ているように見えても、光を分解して分析すると反射率曲線が完全に一致するということはまずありません。
では実際にどのように色合わせを行うのかというと、「Lab値」と呼ばれる色差の数値を目安に調整する方法が一般的です。
管理人が色合わせをしていた頃も、このLab値をできるだけ近づけることが精一杯でした。
Lab値はピンポイントで数値化されるため、一定の範囲内でなら調整が可能です。
実際のところ、Lab値が一致すれば、見た目としてもかなりよく似た色になります。
それに加えて、その上に印刷が施されることを考えれば、紙自体の色の微妙な違いは一般的にはほとんど目立たなくなります。
とはいえ、それでも「見た目が違う」とクレームをつけてくる人もいるのが現実です。
そのため、色に厳しいお客様に対しては、実際に立ち会ってもらいながら色を決めるという対応をしていました。
あとから文句を言われないようにするには、その場で納得してもらうのが一番です。
このような経験を通して、管理人は営業力の重要性を実感しましたね~。
色合わせは紙にもある。光源も重要な問題
ここまでで紙の色合わせについて、どれほど細かい工程と注意が必要かを見てきました。
しかし、実はこれだけでは終わらないんです。
もうひとつ非常に重要な要素があります。それが「光源」なんです。
どんな環境、どんな光の下で紙を見て評価するかによって、色の見え方は驚くほど違ってきます。
たとえば、昼間の太陽光の下で見るときと、夜間の蛍光灯の下で見るときでは、同じ紙でもまったく違う色に見えることがあります。
さらに、工場の控室の蛍光灯の光と、部長の席のスポットライトでは、光の色温度や強さが異なるため、紙の印象も大きく変わってしまいます。
工場内の試験室で「OK」とされた色合いが、会議室で複数人の目にさらされた途端に「NG」とされる、というようなことも日常茶飯事でした。
使われている蛍光灯の種類やメーカーも違いますから、紙の見え方が一致しないのは当然といえば当然なんですよね。
これがまた非常に厄介な点なんです。
先ほど触れたように、分光曲線が完全に一致すれば理論上はどの光源でも同じ色に見えるはずですが、それを実現するのはまず無理。
だからこそ、数値での色合わせが重要になるのですが、その際に「どの光源のもとで見るのか」を事前にしっかり決めておくことが必須となります。
しかし「白色光」といっても、実はメーカーごとに波長成分が異なっており、照明の特性は統一されていません。
たとえばこの部屋は東芝の蛍光灯、隣の部屋は松下のLEDといった具合に、部署や建物ごとにバラバラです。
そのため、色合わせを行う際には「どの照明環境で最終確認をするか」まで詳細に決めておかないと、色が合わないという問題が起きやすくなります。
でも、こういった話は実際に色合わせの業務を経験したことがない人には、なかなか理解されません。
昔、京都のある染料メーカーでは「色を確認するのは午前中の北向きの窓際の部屋で」と決めていたそうです。
このように、時間帯も場所もきっちり指定してチェックするという徹底ぶりだったんですね。
こうした感覚を理解してくれる上司やお客様がいれば良いのですが、そうでない場合は説明するのに本当に苦労しました。
管理人のまとめ
今回は「色合わせは紙にもあるのか?」というテーマで、紙の白色や色調の微妙な違い、そしてそれを合わせるために行われる多くの工程についてお話しました。
紙というのは基本的には白いものだと思われがちですが、その白さにもさまざまな種類があり、微妙な色の差が存在します。
他社製品と見た目が似た紙を作るには、それらを精密に分析し、見た目だけでなく成分レベルでも近づけていく必要があります。
管理人も過去に何度もこの作業に取り組んできましたが、本当に骨が折れる大変な仕事だった記憶があります。
最終的には、色差Labという色を数値で表す指標に基づいて調整を行うことになるのですが、この数値が一致したからといって、見た目が完全に同じになるとは限りません。
あくまで「かなりよく似た色」になるというレベルです。
そもそも使っている原料が、パルプも染料も塗料も、さらには使う水の性質まで異なるのですから、完全に同じになるわけがないのです。
しかも、見る環境によって色の見え方も変わるわけで、その調整は非常に難しいのが現実です。
最終的には、ユーザーが「これでいい」と納得する色になることが重要で、技術的な限界を理解してもらう必要があります。
技術的には色合わせの方法はある程度決まっていますが、営業的には「お客様にどう納得してもらうか」が最大の課題だと感じていました。
個人的な感覚としては、「そこそこ似たような色になったら、あとは営業の腕次第」といった印象でしたね。
この記事が、紙の色合わせについて少しでも参考になれば幸いです。
紙を見るときには、その色にも注目してみてくださいね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
紙と布の違い?前者はパルプの積層体、後者は糸を織ったもの
⇒https://kamiconsal.jp/kamitonunonotigai/
段ボールベッドのメリット!安くて強くて組立も処分も簡単!
⇒https://kamiconsal.jp/danborubedmerit/
シール台紙ではがせるものは何?それは剥離紙ともいいます!
⇒https://kamiconsal.jp/sheeldaisihagaserumono/