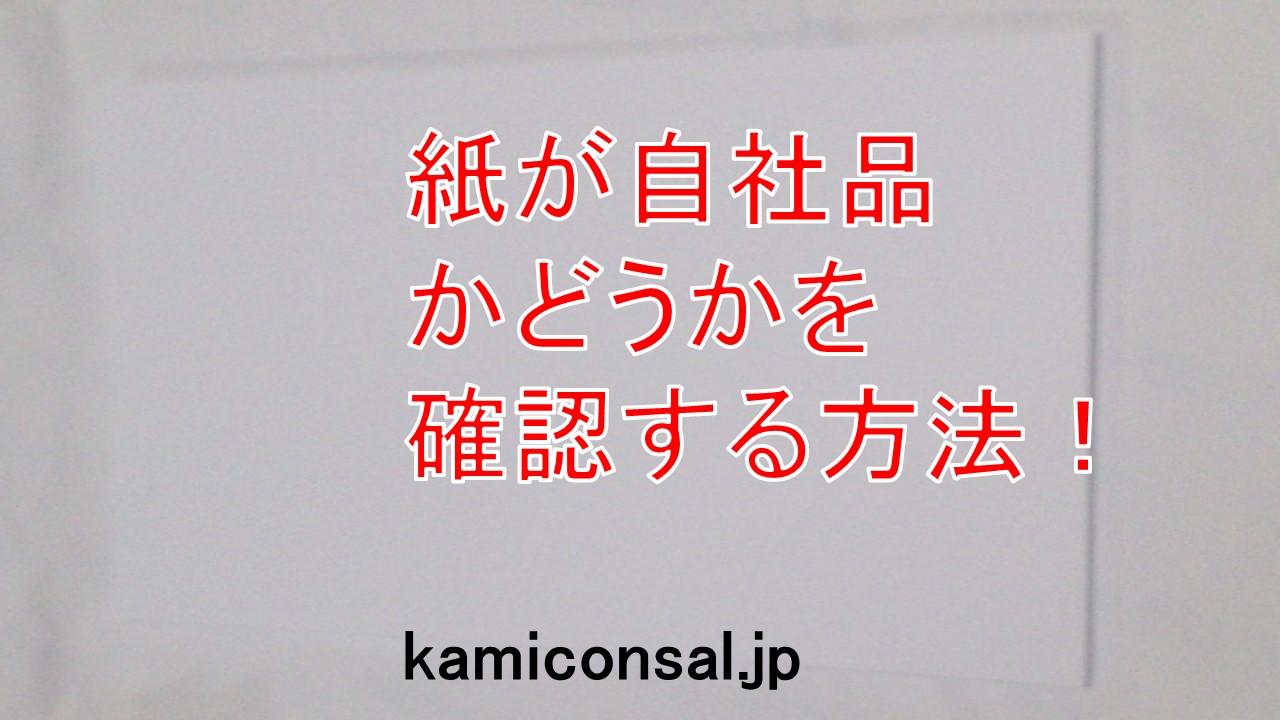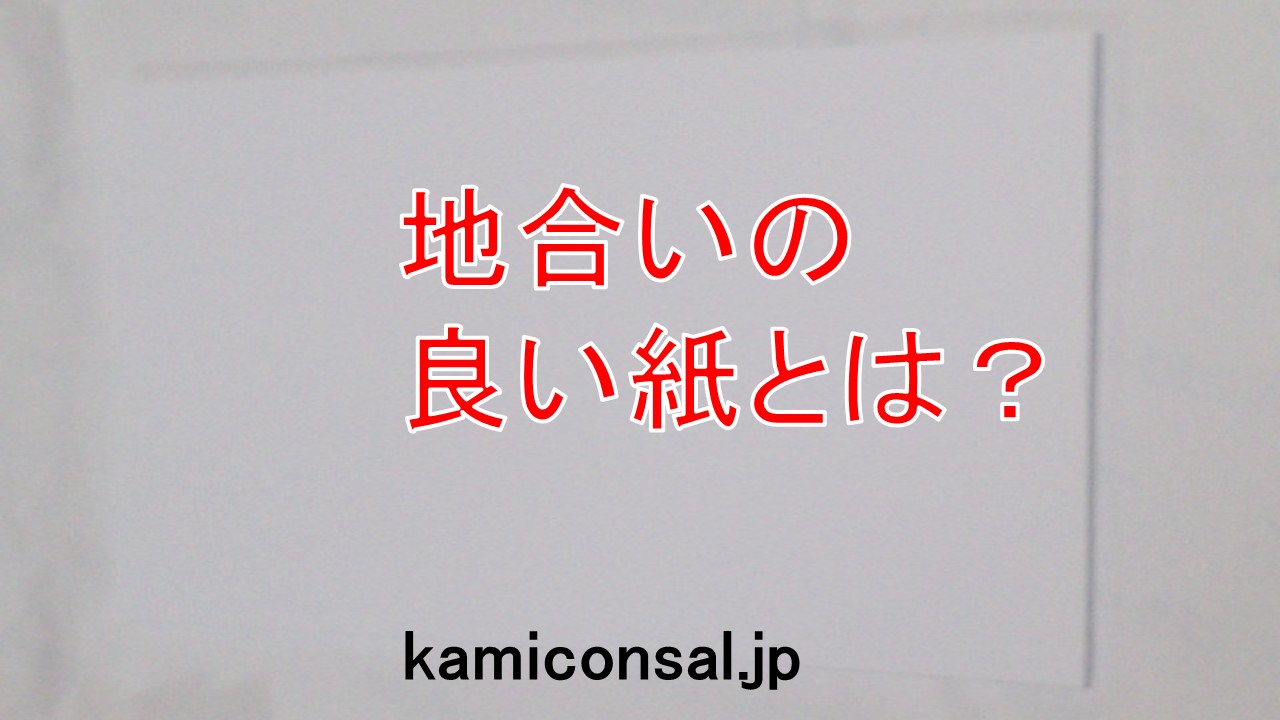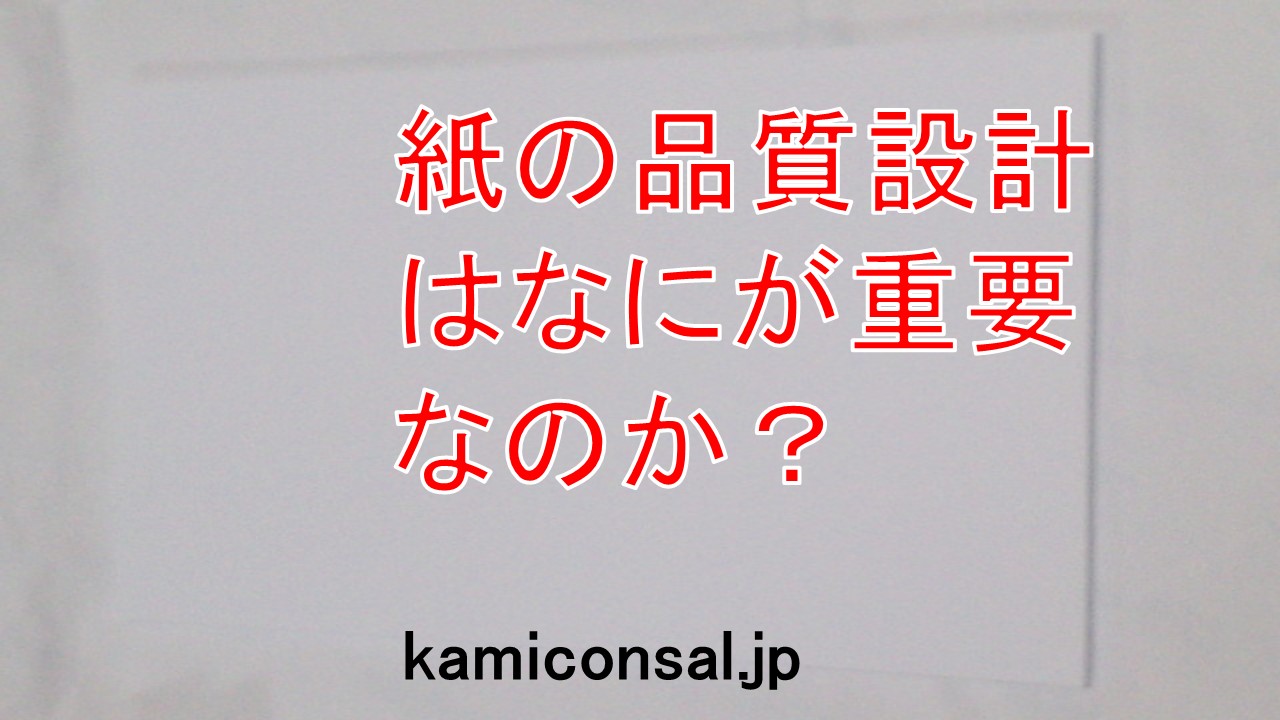この記事は約 10 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、紙が自社品かどうかを
確認する方法というお話。
管理人は元製紙会社社員。
技術者でクレーム対応もやってました。
紙にクレームが来るのかと思うでしょうが
これが結構な割合で来るんですね。
内容も様々なんですが、多いのは
シワダブリ、紙粉というような印刷不良。
これは管理人が印刷用紙担当が
長かったからそう思うんですけど。
言いがかりみたいなクレームも多くて
なかなか困ることもありましたね。
よく言われたのがうまい印刷屋は
クレームを言ってこないということ。
結局、紙の扱いが分かっているかどうかで
クレームになったりならなかったりする。
たまに無茶苦茶な使い方をして
文句を言ってくるところもありました。
これは販売している製紙会社にも
もちろん問題がありました。
だいたいユーザーがどんな使い方を
しているか分かってないとかですね。
なんだか紙ムケのクレームが多いなと
思ったら新しい印刷機になってたとか。
そのときに印刷速度が上がっていたのに
紙の表面強度対策してなかったとか。
紙に限りませんが、クレームというのは
かなり相対的なものでもあります。
先ほどお話した印刷不良にしても
昔ながらの印刷機なら問題ない。
そういうことも多いわけです。
それはそうとして。
クレームを受け付ける場合は基本的に
使用した紙の製造ロットNoが必要で
できればそのときの紙サンプルも
入手して分析することになるんですが。
お客さんによってはロットNoはわかるが
紙サンプルなんて使って残ってないとか
ひどいときにはロットNoも分からない
というのがあるんですよね。
逆に、紙はあるけどロットNoは
不明というのもありますけど。
それで。
大抵の場合はクレームが発生すると
悪いのは紙のせいになるんですが
たまに本当にこの紙は自社品なのか
と思うときもあるわけです。
そんなときにロットNoが分かっていて
紙サンプルが入手できると本当に
自社品かどうかを確認する
手軽な方法があるんですね。
ということで。
この記事では紙が自社品か
どうかを確認する方法について
管理人の調べたことを
お伝えしたいと思います。
紙が自社品かどうかを確認するのは分光光度曲線を比較する
紙の同定方法については、様々なアプローチが考えられます。目視による確認、質感や厚みの測定、さらには成分分析など、手段は多岐にわたります。
しかし、「その紙が自社品かどうか」という限定的な目的であれば、もっとシンプルかつ確実な方法があります。それが分光光度曲線を使った比較です。
特に、色調の違いを定量的に把握したい場合には非常に便利な手法で、手軽に結果を得られる点も魅力です。
この分光光度曲線を得るには、紙の色調を測定するだけで十分。専門的な知識がなくても、適切な測定機器があれば扱えます。
管理人が現場にいた当時は「カラーアナライザー」という装置を使って紙の色調を測定していました。今では、より高精度で操作も簡単な機器が増えています。
紙の場合、透過ではなく反射光を測定するため、分光光度曲線ではなく「分光反射率曲線」という表現が適切になります。紙は基本的に光を透過しないので、反射された光を分析するのです。
この「分光反射率曲線」とは、以下のように定義されます。
==ここから==
分光反射率曲線は、物体に反射した光の割合(反射率)を、波長ごとに測定し、可視光領域である400〜700nmの範囲において、波長順にグラフ化したものです。
==ここまで==
この定義だけでは少し難しく感じるかもしれませんが、実際にはこういうことです。特定の光を紙に当てて、どの波長の光がどれくらい反射されているかを測定し、それをグラフにすることで、その紙の「色の特徴」を視覚的に表すというわけです。
面白いことに、同じように見える紙でも、この分光反射率曲線には差が出ます。色調を構成する要素が異なれば、当然ながら反射率も異なるのです。
特に、同じ工場、同じ製造ラインで作られた、同一銘柄の紙であれば、かなり近いグラフになります。製紙会社では、製品の色調がブレないよう、厳密な色調管理が日常的に行われているためです。
同じロットであれば、ほぼ完全に一致するグラフが得られることもあります。逆に、別の会社の製品や、別のマシンで作られた紙であれば、グラフの形状は大きく異なる傾向にあります。
色調に関しては、顧客と明確な取り決めがない限り、各社が独自に調整しています。そのため、見た目は似ていても、色合いには必ず差が生じます。
例えば、「上質紙」というジャンルの中でも、メーカーごとに色味は微妙に異なりますし、ライナー紙やコート紙でも同じことが言えます。白い紙でも、それぞれ「白の種類」が違うのです。
さらに、色調に大きな影響を与える染料の種類やその濃度も、会社やマシンによって異なります。パルプの配合も違えば、使用する水の成分も異なるため、色の再現は非常に難しいのです。
「他社品と同じ色にしてください」と言われても、完全に一致させるのは不可能です。あくまでも「近づける」レベルにしかなりません。
見た目は似ていても、機械で測定すれば微妙な違いが現れます。逆に言えば、そうした違いを見抜くには、機械測定が最も正確なのです。人間の目も鋭いですが、やはり限界があります。
今のカラーアナライザーは非常に優秀で、測定データから瞬時にグラフを生成し、PC上で重ねて比較できるので、違いが一目瞭然です。もし専用機がなくても、データをエクセルなどに入力すれば簡単に比較可能です。
管理人が品質クレームを担当していた時代には、ロット番号が分かっていれば、そのロットの保管サンプルと、問題のあるサンプルを色調測定し、グラフを重ねて確認していました。
結果として、自社品であればグラフは一致し、他社品であれば一致しませんでした。この方法は、かなり高い精度で真贋を判定できる便利な手段だったのです。
しかも、非破壊で実施できるため、サンプルを傷つけることなく分析できる点も大きな利点です。
分光光度曲線のデータベース化のすすめ
あらかじめ既知の紙やフィルムの分光光度曲線を測定しておき、データベースとして保存しておくと、後々のトラブル対応や製品比較に非常に役立ちます。
この記事では主に紙に焦点を当てていますが、実際にはフィルムなどの他素材にも応用可能です。たとえば、透明なOPPフィルムやPETフィルムでも同様の測定ができます。
透明素材の場合は「分光透過率曲線」として扱われ、透過する光の波長ごとの割合を測定します。これにより、透明度の違いや、特定の波長の吸収特性なども明らかになります。
たとえば、蛍光染料が含まれているかどうかなども、この手法で非常に明確に判別することができます。
材料ごとに光の反応が違うだけでなく、同じ素材でもメーカーや製造条件によって特性が異なります。紙と同様、色調は製造プロセスに左右される繊細な要素です。
「透明フィルムはどれも同じだろう」と思いがちですが、測定してみると驚くほど違いが出ることがあります。
このように、分光光度曲線を使った分析は、高度な化学分析のような難しさがなく、しかもサンプルを傷めないという点で非常に優れています。
紙・フィルム・シートなど、色調測定が可能なあらゆる素材に応用でき、品質管理やトラブル対応、製品同定などで幅広く活用できると感じます。
管理人のまとめ
今回は、「紙が自社品かどうかを見分ける方法」というテーマでお話をしました。
結論としては、色調測定を行い、その結果から分光光度曲線(紙の場合は分光反射率曲線)を比較することで、自社品かどうかをかなりの精度で判断できます。
サンプルと自社の保存データを比較すれば、たとえ見た目が似ていても、グラフの形状で明確な違いが出るのです。人の目では判別が難しい微細な違いも、機械による測定なら見逃しません。
しかも、この手法は紙だけでなく、フィルムや透明シートなど、他の素材にも有効です。非破壊で簡便に行えるため、品質管理の現場では非常に重宝される手段となっています。
色というのは一見曖昧な要素ですが、こうしてデータとして可視化すれば、非常に明確で精度の高い情報になります。
この記事が、紙の識別やトラブル対応に役立つ情報として参考になれば嬉しいです。
色調を科学的に捉えるこの手法、ぜひ上手に活用してみてください。