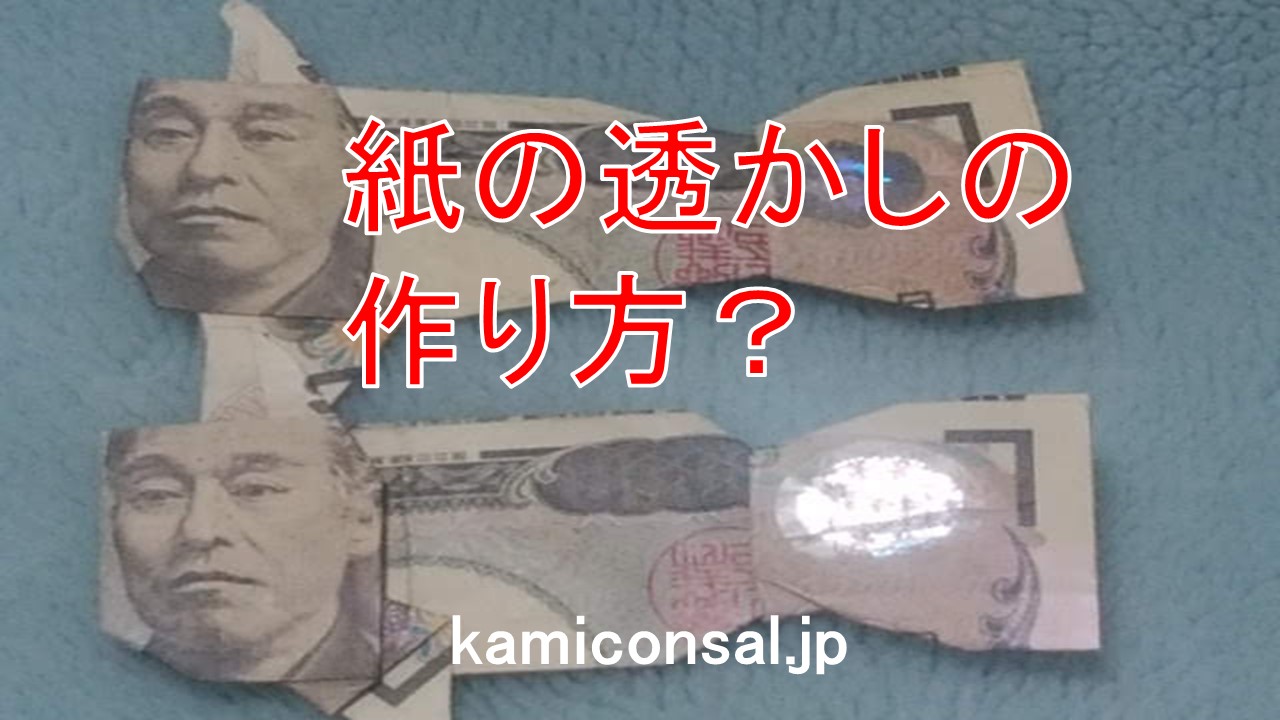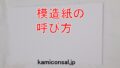この記事は約 8 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、紙の透かしの作り方は?
白透かし、黒透かし、透かし印刷など
というお話。
透かしと言えばお札ですよね。
透かしてみれば模様が浮かぶ。
技法としては古くからありますが
何度見ても不思議なものだと思います。
ところで。
この透かし、どうやって作るのが?
気になりますよね~
ということで。
この記事では紙の透かしの作り方は?
白透かし、黒透かし、透かし印刷など
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
紙の透かしの作り方。抄紙機の場合
そもそも「透かし」なんですけど。
どういうものかという定義から。
ウィキペディアによると
==ここから==
透かし(すかし、英語: Watermark)とは、当てた光によって紙の上により明るく(暗い背景の上で反射した光ではより暗く)現れる区別することのできる画像や模様である。
==ここまで==
ということだそうです。
英語ではウォーターマークですね。
透かしは基本的に湿紙の状態で
模様をつけるものですから。
それで、紙の透かしの作り方ですけど。
大きく分けると抄紙機で作るか
印刷で作るかに分けられます。
昔からある技術は抄紙機。
紙そのものに凹凸をつけるわけです。
その方法も大きく2つに分けられます。
白透かしと黒透かしだそうです。
それぞれ、
「白透かし」は、表現したい線の部分を薄く漉く。
逆に「黒透かし」は、表現したい線の部分を厚く漉く。
ということになります。
一般的な透かしは白透かし。
ダンディロールという模様のついたロールを
湿紙に当てると模様の部分が薄くなるので
その部分が白くなるということだそうです。
たとば卒業証書とかそういう
証明書に使うようですね。
黒透かしはお札にも使われる特殊な技術。
模様の部分がロールに彫られて
その部分が厚くなるので黒くなる。
白透かしと黒透かしは写真で言えば
ネガとポジのような感じでしょうか。
印刷だったらロールに関しては
凸版とグラビアのイメージか。
例え方がちょっと微妙ですけど。
なお。
黒透かしは特別な許可がない限り
使ってはいけない法律があります。
==ここから==
昭和二十二年法律第百四十九号
すき入紙製造取締法
① 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
② 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
③ 第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
==ここまで==
まさか透かしに対して罰則のある
法律があったとは知りませんでした。
まあこの法律は昭和22年なので
罰金は5千円以下だそうですが。
日本は特に偽札には厳しいですから
こういう法律もあるんでしょうね。
ちなみに。
お札に使われている透かしは
白と黒の透かし両方だそうです。
高度な技術、というわけですね。
透かし印刷について
ここまで透かしについてお話しました。
紙に透かしを入れるのは古くからの技術。
重要なもの、証書やお札などに使われます。
では透かし印刷とは?
こんなことだそうです。
==ここから==
透かし模様の印刷をオフセット印刷方式で可能とした印刷手法です。
常温で固化しない液状の樹脂を紙に浸透させ光の透過率を変えることによって紙を透かせて見せることができます。
また、通常のオフセット印刷機で作成できるため透かし用紙を一から抄造するよりもはるかに安価に製造できるのです。
==ここまで==
ということだそうです。
これはオフセット透かし印刷。
抄紙機での作成とは全く違います。
抄紙機の場合は紙に厚薄をつけて
光の透過度を変えるわけですが
印刷の場合は樹脂を染み込ませて
光の透過度を変えるというわけ。
狙っている結果は同じでも
やり方は全く違うわけです。
一長一短がありますが印刷のほうが
自由度が高いのは間違いありません。
印刷ですからデザインが自由になる。
絵柄も変更できるし透け具合も
調整できるということです。
ただし、短所もあります。
ひとつはインキによっては
黄変化しやすいということ。
樹脂の部分が紙より劣化しやすい。
それからインキによってはにじむ。
紙との相性にもよりますが
透明な樹脂がにじんでくる。
イメージとしては紙に油を吸わせたら
透明な部分ができたと言う感じなので
劣化が早かったりにじみが発生するのは
ある程度は仕方がない用に思います。
なので用途が重要です。
長く残す証書などにはイマイチ。
逆に透かしの入った包装紙は
面白いのかなと思いますね。
包装紙なら長期保存の
保証はしなくていいので。
特徴を分かって使えば面白いと思います。
管理人のまとめ
今回は紙の透かしの作り方は?
白透かし、黒透かし、透かし印刷など
というお話でした。
紙の透かしの作り方は抄紙機で
作るか印刷で作るかの2パターン。
抄紙機の場合は白透かしと黒透かし。
印刷は透かし印刷がある。
ということでした。
白透かしや黒透かしは紙の厚薄によって
模様を浮かび上がらせる方法に対して、
透かし印刷は樹脂を印刷して
その部分を透明化させる方法。
それで。
お札は黒透かしと白透かしの
両方を使う高度な紙だとか。
偽造防止技術はすごいものなんですね。
この記事が紙の透かしの作り方の
参考になればと思います。
紙の透かし、面白いですね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
偽造防止用紙の仕組み!小さなドット、透かし、特殊インク?
⇒https://kamiconsal.jp/gizoubousiyousi/
紙にエンボス加工する方法!自分でも手作りで簡単に出来る?
⇒https://kamiconsal.jp/kamienbos/
パラフィン紙とは?グラシン紙にろうそくを含有させたもの!
⇒https://kamiconsal.jp/paraffinpaper/