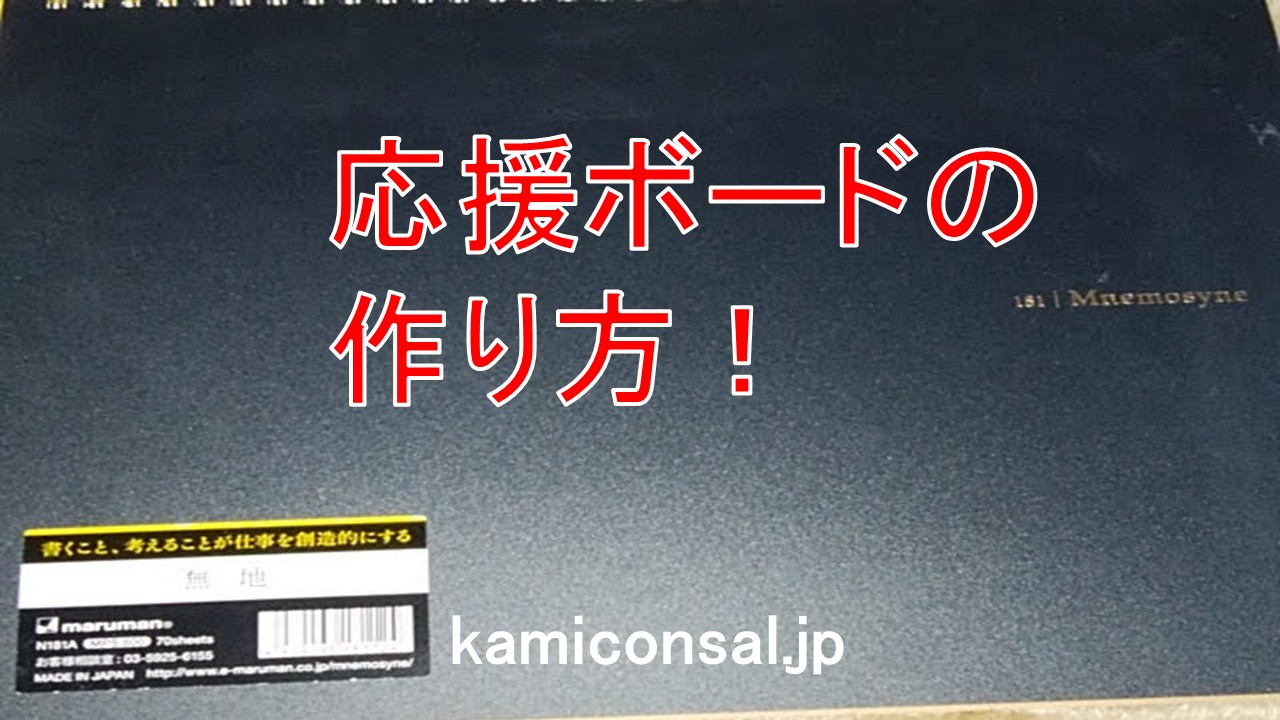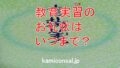この記事は約 9 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、応援ボードの作り方!
スケッチブックの大きさや文字はどうする?
というお話。
コンサートやスポーツ観戦、
舞台イベントなどで活躍する応援ボードは、
自分の気持ちをダイレクトに
伝えるための重要なアイテムです。
特にスケッチブックを使った応援ボードは、
手軽に作れてアレンジもしやすいため、
多くの人に利用されています。
ただし、ただ作れば良いというわけではなく、
大きさや文字の配置、色使いなどによって
見やすさや伝わりやすさが大きく変わります。
ここでは、スケッチブックを使った
応援ボードの作り方について、
大きさや文字の工夫、デザインのアイデア、
さらに持ち運びやマナーまで
詳しく解説します。
ということで。
この記事では、応援ボードの作り方!
スケッチブックの大きさや文字はどうする?
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
スケッチブックの大きさを選ぶポイント
応援ボードを作る際にまず重要なのは、
スケッチブックの大きさです。
大きすぎれば持ち運びに不便で周囲の観客の
視界を遮ってしまう可能性がありますし、
小さすぎると肝心のメッセージが
見えにくくなります。
一般的におすすめされるのは、
A3サイズからB4サイズ程度の大きさです。
A3サイズは十分な文字の大きさを確保でき、
遠くからでも目立ちやすいのが特徴です。
一方、B4サイズはややコンパクトで、
混雑した会場でも扱いやすいという
利点があります。
また、スケッチブックを選ぶ際には
紙質にも注意が必要です。
厚みのある画用紙タイプのスケッチブックを
選ぶと、文字や装飾を貼り付けた際にも
曲がりにくく、見た目が整いやすくなります。
リングタイプはページをめくりやすいですが、
片面をしっかりと仕上げて固定する場合は
テープやクリップで補強することを
おすすめします。
サイズ選びと紙質のバランスを考えることで、
使いやすく見栄えの良い応援ボードが
完成します。
文字の大きさとデザインの工夫
応援ボードの印象を決める
最大の要素は「文字」です。
会場の照明や距離感を考えると、
遠くからでも読み取れるように
大きくはっきりとした文字を
使うことが重要です。
一般的には。
1文字が縦横10センチ以上あると、
観客席の中ほどからでも
見やすくなります。
特に名前や応援メッセージなど、
伝えたい部分は大きく
目立たせることが効果的です。
文字のデザインに関しては、
単に大きいだけではなく、
背景とのコントラストを
意識するとさらに効果的です。
例えば黒い背景に蛍光色の文字を貼ると
目立ちやすく、暗い会場でも視認性が
高まります。
文字の縁取りを白やシルバーで行えば、
光の反射でより目を引きます。
また、文字をカットして厚紙に貼る
「立体文字」にすることで存在感が増し、
平面的な印刷文字よりも迫力が出ます。
余白のバランスにも注意し、
文字が詰まりすぎないように
配置することがポイントです。
さらに、文字数はなるべく短く
簡潔にすることが望ましいです。
長文になると読みにくく、
メッセージのインパクトが弱まります。
「がんばれ!」「ありがとう!」といった
短いフレーズや選手名、グループ名などを
中心に構成すると、瞬間的に伝わりやすい
応援ボードになります。
装飾と配色のテクニック
文字の他にも、装飾や配色を工夫することで
応援ボードの完成度は大きく変わります。
カラーペンや色紙、マスキングテープ、
ステッカーなどを組み合わせると、
個性のあるデザインに仕上がります。
特にイベントによっては
「ペンライトや照明に映える色」が効果的で、
蛍光ピンクやライムグリーン、
イエローなどは暗い環境でも
目立ちやすいカラーです。
また、ラメやホログラムシートを部分的に
使うことで光の反射を活かした装飾が
可能です。
文字の周りを星やハートで囲んだり、
メッセージの一部を強調するために
ラインストーンを貼る方法も人気です。
ただし、派手にしすぎると
逆に見にくくなったり、
光を反射しすぎて周囲に迷惑をかける
可能性があるため、バランスを
意識することが大切です。
配色に関しては、基本的に3色程度に
抑えると統一感が出ます。
例えば、背景を黒、文字を蛍光ピンクと白で
構成すれば、シンプルながら強い印象を
与えられます。
推しのカラーやチームカラーを
取り入れるのも効果的で、
一目で誰を応援しているのかが
伝わりやすくなります。
持ち運びと会場でのマナー
応援ボードを作ったら、実際に会場へ
持って行く際の工夫も重要です。
大きめのスケッチブックは
折りたためないため、
持ち運びに不便さを
感じることがあります。
そこで、キャリーバッグや専用ケースを
用意しておくと、移動中にボードが
折れたり汚れたりするのを防げます。
また、雨天のイベントではビニール袋や
クリアケースに入れて防水対策を
しておくこともおすすめです。
会場で使用する際には、
周囲への配慮が欠かせません。
前の人の視界を遮らないように
胸の高さで掲げる、または演出中は
控えるといったマナーが求められます。
特にスポーツやコンサートでは観客全体で
楽しむ場であるため、自分の応援が
他人の迷惑にならないように
注意することが大切です。
会場によっては応援ボードのサイズや
使用ルールが定められている場合もあるので、
事前に確認しておくと安心です。
さらに、長時間掲げると腕が疲れてしまうため
持ちやすい工夫も有効です。
スケッチブックの裏に持ち手を取り付けたり、
軽量化を意識した素材選びをすることで、
快適に応援できます。
実用性とマナーを両立させることで、
会場全体の雰囲気を壊さずに応援を
楽しめます。
管理人のまとめ
今回は、応援ボードの作り方!
スケッチブックの大きさや文字はどうする?
というお話でした。
スケッチブックを使った応援ボードは、
サイズ選び、文字の大きさや配置、
装飾の工夫、持ち運びやマナーといった
ポイントを意識することで、
誰でも完成度の高いものを
作ることができます。
A3やB4サイズのスケッチブックをベースに
遠くからでも読みやすい文字を大きく配置し、
背景とのコントラストを意識した
配色を取り入れることで、
効果的な応援が可能になります。
さらに、推しのカラーやイベントの雰囲気に
合わせたデザインを加えることで、
個性が光るオリジナルの
応援ボードが完成します。
最後に忘れてはならないのが、
持ち運びの工夫と会場でのマナーです。
自分の応援が誰かの妨げにならないように
注意しつつ、快適に使えるように
準備することで、イベントを
より一層楽しめるでしょう。
応援ボードは単なるアイテムではなく、
自分の想いを伝える大切な手段です。
工夫を凝らして作り上げれば、
思い出に残る素晴らしい
応援ができるはずです。
この記事が応援ボードの作り方の
参考になればと思います。
応援、楽しんで下さいね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
スケッチブックシアターを導入!子供の注意を引き付けやすい
⇒https://kamiconsal.jp/sketchbooktheater/
画用紙とケント紙の違い?絵画か製図かなど主な用途が違う!
⇒https://kamiconsal.jp/gayousikentositigai/
製図用紙はどこに売ってる?文具店、ホームセンター、通販!
⇒https://kamiconsal.jp/seizuyousidokoni/