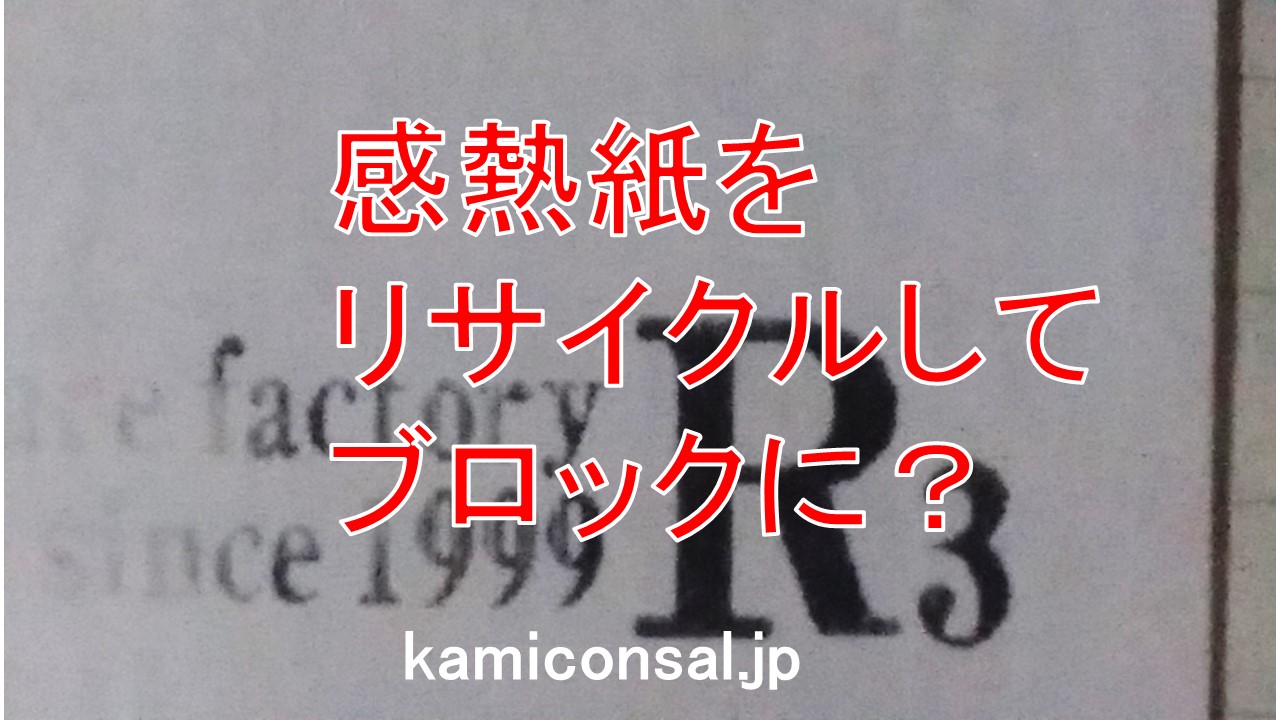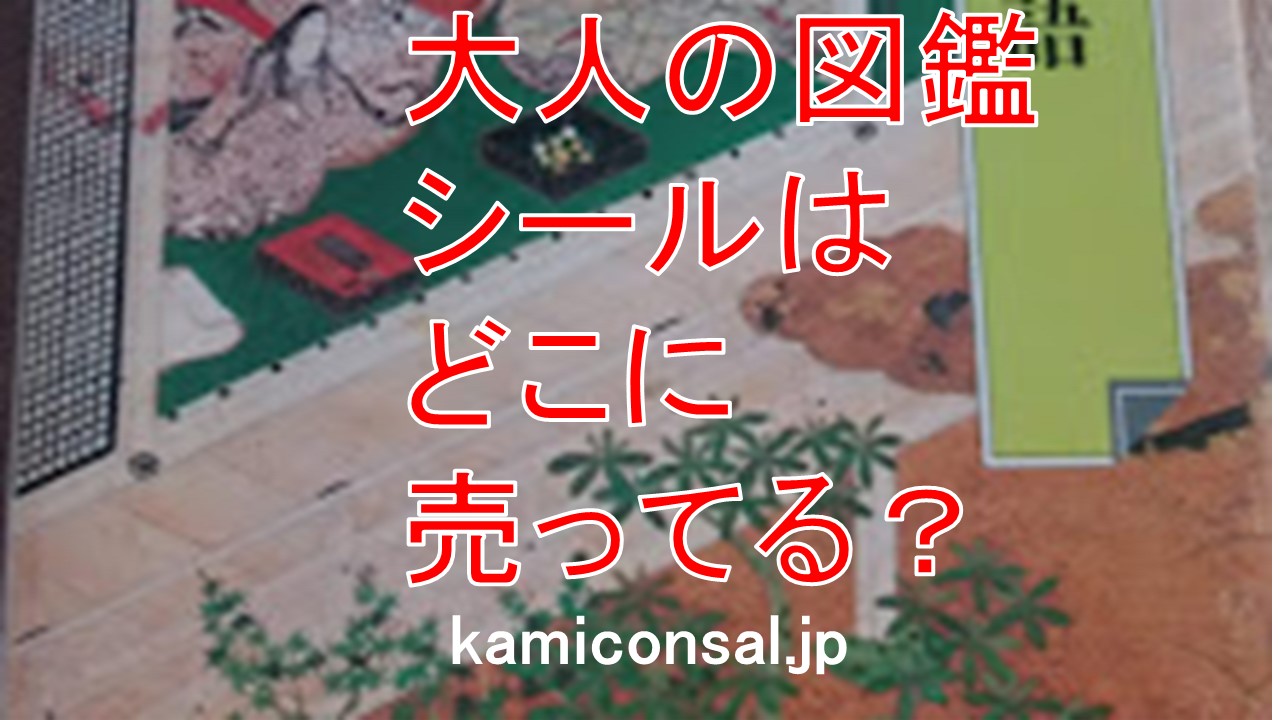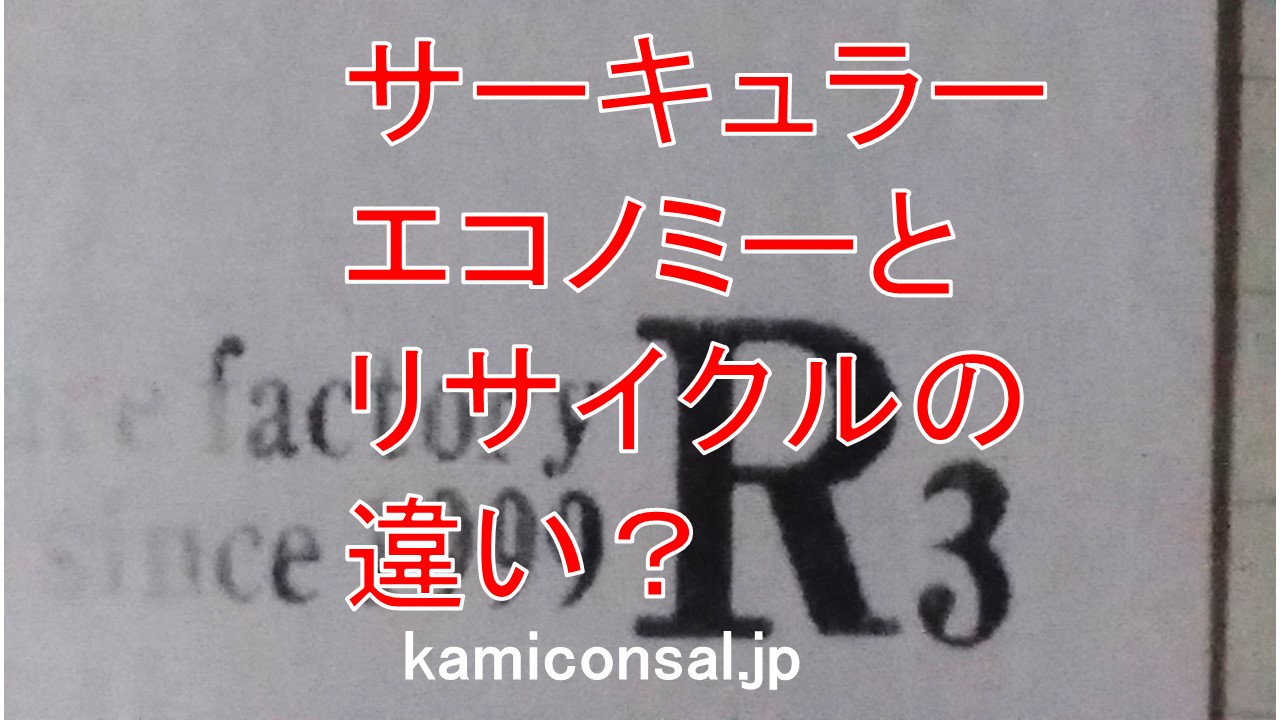この記事は約 6 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
「感熱紙はリサイクルできない」という話をよく耳にします。レシートや宅配ラベルなど、私たちの生活の中でもよく使われている感熱紙は、特殊な薬品が塗布されているため、通常の古紙回収ではリサイクルが難しく、「禁忌品」として分別されがちです。
しかし、最近ではこの感熱紙をアップサイクルし、ブロックとして再資源化する画期的な取り組みが登場しています。
この記事では、「感熱紙 リサイクル」「感熱紙 禁忌品 再利用」「感熱紙 ブロック アップサイクル」などのキーワードで検索される方に向けて、最新の再資源化技術とその課題・可能性について詳しくご紹介します。
感熱紙は本当にリサイクルできない?基本知識をおさらい
まず大前提として、感熱紙は一般的な紙のリサイクルシステムでは処理が難しい素材です。感熱紙の表面には、熱によって発色するための薬剤(ビスフェノールなど)が塗られており、通常の製紙工程に混ざると再生紙の品質を大きく損なう恐れがあります。
そのため、感熱紙は「禁忌品」として古紙回収から除外され、ほとんどが可燃ごみとして焼却処理されてきました。
注目の新技術!感熱紙をブロックに再資源化するアップサイクルの仕組み
技術のポイント:紙に戻さず、固形素材として再利用
注目されているのが、感熱紙を細かく粉砕し、固形ブロックに加工する技術です。この方法では、感熱紙を再び紙に戻すのではなく、全く別の形にアップサイクルすることで「品質劣化の問題」を回避します。
代表的な事例が、nunock paper by PANECOによる取り組みです。彼らは感熱紙のような再資源化困難な素材を、美しいブロック状の素材へと再生し、インテリアや家具材料として活用できるようにしています。
感熱紙アップサイクルの用途とは?
- 家具の板材(棚板、テーブル天板など)
- インテリアパネルやオブジェの素材
- エシカル商品として販売される装飾ブロック
このように、感熱紙は再資源化の難しさを逆手にとり、デザイン性のある製品に生まれ変わる“エコ素材”として新たな可能性を見出されています。
リサイクルを実現するための最大の課題は「回収」
感熱紙の現状:家庭からの回収は非現実的?
いくら技術的に再資源化が可能でも、原料である使用済み感熱紙が安定的に集まらなければビジネスとして成り立ちません。特にレシートのように小さく、生活の中で散発的に発生する紙は回収のコストも高くなります。
現在の家庭ごみ回収体制では、感熱紙を個別に集めることは困難です。ゆえに、実際の回収のターゲットは以下のような場所が現実的でしょう:
- コンビニやスーパーのレジ横に設置される「レシート不要ボックス」
- 企業・店舗のPOSシステムからの業務用レシート排出
- 物流業界の宅配ラベルなどの一括処理
コストとスケールの両立が鍵
機械を稼働させてブロック成形するには、ある程度の量が必要です。感熱紙だけでなく、アパレル業界の廃繊維などと混合して処理できるようなマルチ素材対応のラインがあれば、稼働率を上げることでコスト面もカバーできるかもしれません。
つまり、技術だけでなく「社会インフラとしての回収と再生のスキーム」がセットで機能しないと、持続的な感熱紙リサイクルは難しいというわけです。
感熱紙リサイクルの今後に期待すること
感熱紙のようなリサイクル困難な禁忌品がアップサイクル可能となることは、廃棄物処理の未来に大きな希望を与えてくれます。
エコ商品としての価値を付加し、インテリアなどの用途で使うことで、単なる廃棄物ではなく「資源」としての価値が生まれます。さらに、企業のCSRやSDGs達成の一環としても導入が進めば、より社会的な広がりを見せるかもしれません。
今後の課題は、「経済性・回収システム・販路」の3つの柱をいかに整備していくか。技術はある。あとはそれを支える仕組み作りです。
まとめ:感熱紙も新時代の資源に!
この記事では、「感熱紙はリサイクルできるのか?」という疑問に対し、最新のアップサイクル技術による再資源化の可能性を紹介しました。
感熱紙=燃やすしかない時代は、もう古いかもしれません。
これからは、感熱紙のような“リサイクル困難な紙”をも社会の資源循環に組み込む時代です。新しい技術とアイデアによって、禁忌品でさえも価値あるプロダクトに生まれ変わらせる。まさにアップサイクルの真髄です。
感熱紙の再資源化が今後さらに発展し、サステナブル社会の構築に貢献することを願っています。
(参考)
こんな記事も読まれています。
感熱紙の再利用は出来るのか?リサイクルすることは困難です
⇒https://kamiconsal.jp/kannetusisairiyo/
感熱紙と普通紙のFAX。リサイクルの観点からエコなのは?
⇒https://kamiconsal.jp/kannetusifutuusifax/
サーマルリサイクルとマテリアルリサイクルの違いは再資源化
⇒https://kamiconsal.jp/thermalmaterial/