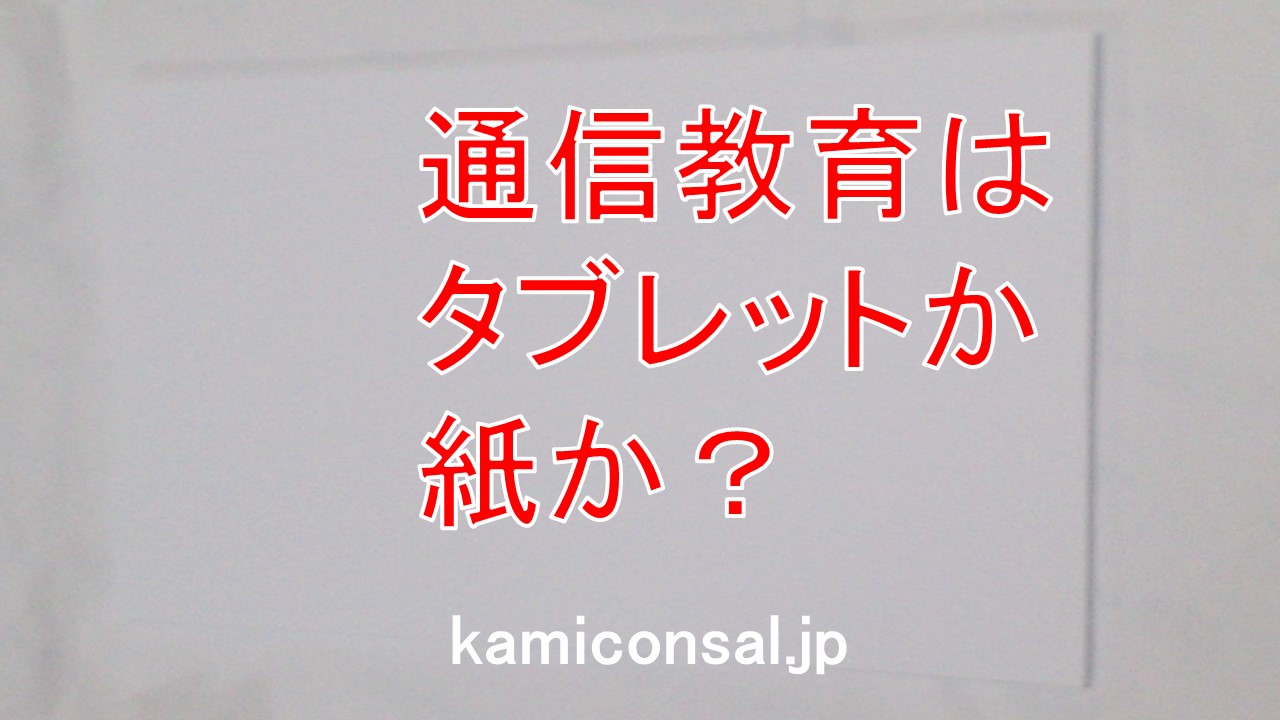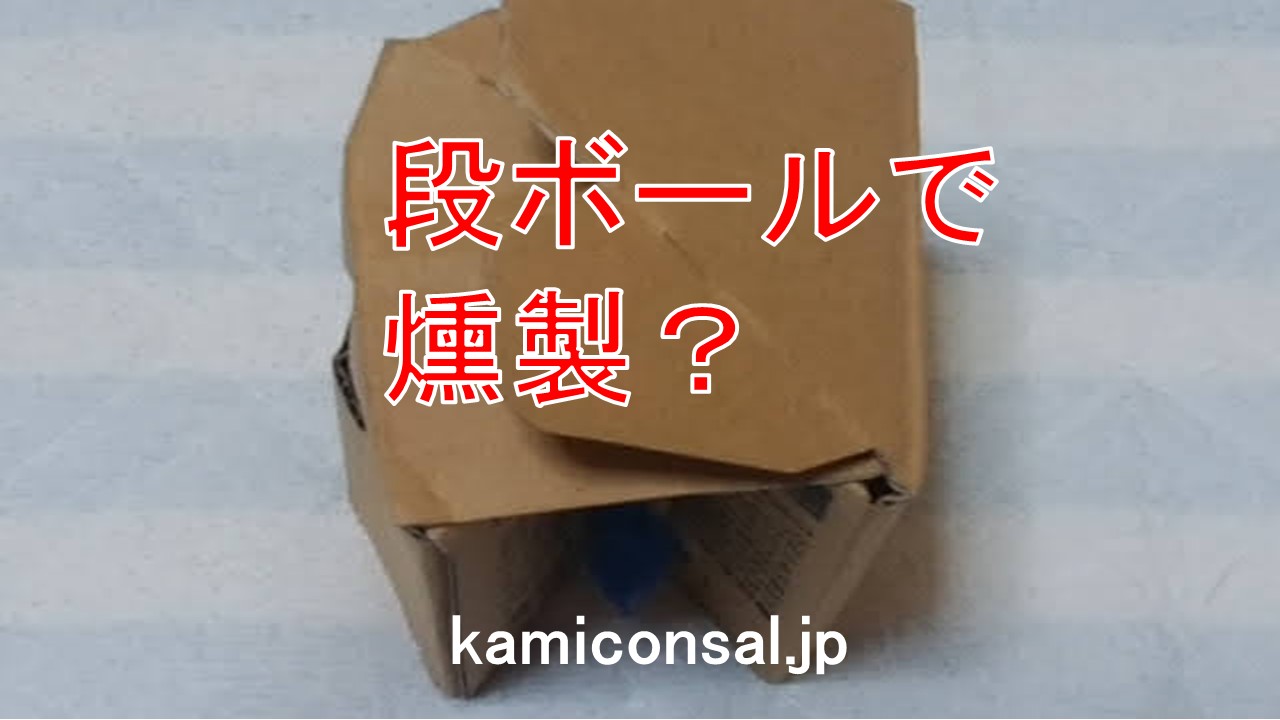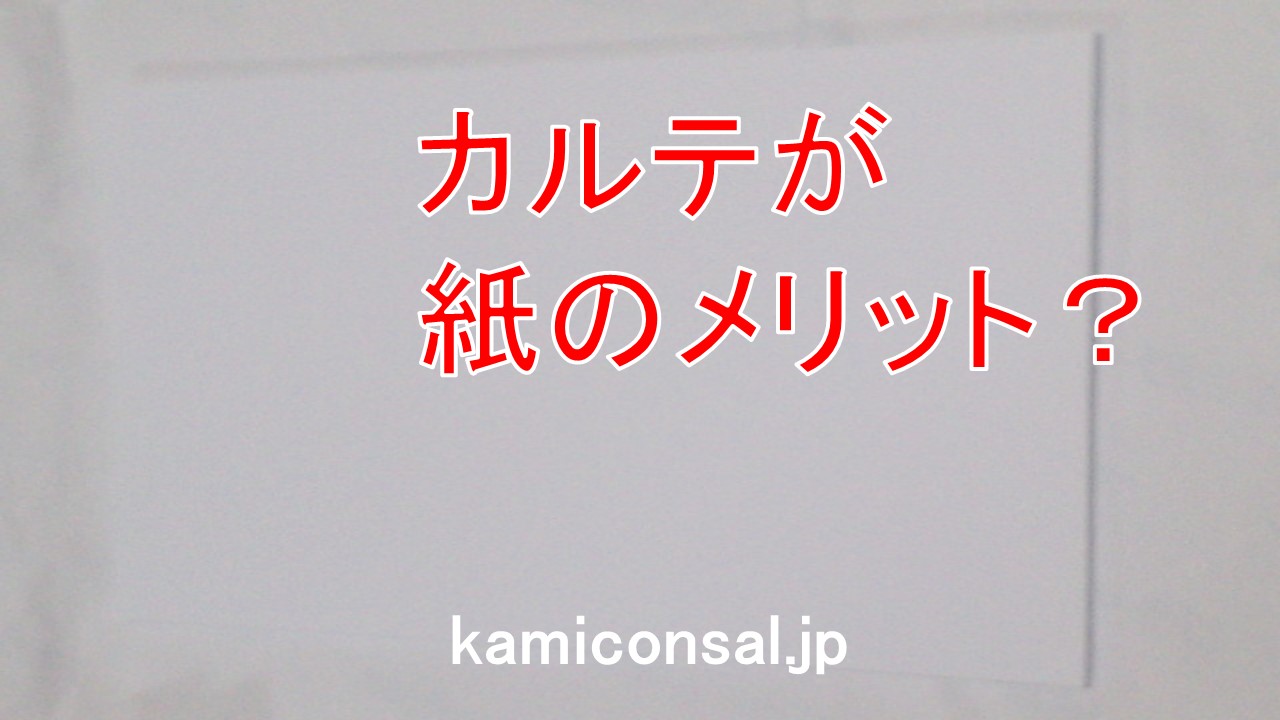この記事は約 11 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
近年、通信教育のスタイルは大きく変化しています。かつて主流だった「紙の教材」に加え、今ではタブレット端末を活用したデジタル学習も一般的になってきました。
では、紙とタブレット、どちらが学習効果が高いのでしょうか?この記事では、管理人の体験を交えながら、「通信教育はタブレットか紙か?」というテーマについて掘り下げていきます。
通信教育といえばZ会!紙教材の原点から考える
管理人にとって、通信教育といえば真っ先に思い浮かぶのが「Z会」でした。学生時代、まだインターネットの普及前だったころ、通信教育といえば紙の教材が送られてきて、手紙のように提出するスタイルが主流。
管理人自身、Z会の難問に挑戦した記憶があります。正直、難しすぎて途中で挫折した記憶もありますが、それでも今振り返ると、紙教材だからこそ得られた学習の習慣があったように感じます。
通信教育は紙の方が「机に向かう習慣」が身につく
管理人が実際に調査した結果、通信教育において紙の教材を使用する最大の利点は、「机に向かう習慣」が自然と身につくという点でした。この習慣は学習の土台を作る上でとても重要で、日々の学びを継続させる力となります。特に小学生や中学生のように学習習慣がまだ定着していない年代においては、「勉強=机に座って紙に向かう」というスタイルが、学習への集中力を育てる第一歩になるのです。
タブレット学習のように「どこでも学べる」ことは確かに魅力的ですが、その便利さゆえにソファーで寝そべりながら動画を見るだけの受け身な学習になりやすく、どうしても“ながら勉強”になってしまいがちです。耳だけで聞いていたり、目線がどこかにいっていたり、注意散漫な状態では、学習の効果は半減してしまいます。
それに対して紙の教材は、ノートや教科書を広げ、鉛筆を持って実際に手を動かすことが前提になります。つまり、机に座って学ぶという行為そのものが、学習へのスイッチをオンにする「儀式」として働くのです。これは心理的にも大きな意味を持ち、「今から勉強するぞ」という意識が自然と芽生えやすくなります。
また、保護者の視点から見ても、子どもが机に向かって紙の教材に真剣に取り組んでいる様子は、明らかに「頑張ってるな」と感じやすいです。家庭での学習状況が可視化されやすいのも、紙教材の大きな特徴でしょう。「やってる感」があることで、子ども自身も達成感を得やすく、親子のコミュニケーションにもつながります。
紙教材ならではの利点とは?
- ノートや問題集で「手で書く」ことで記憶に定着しやすい
- ページをめくるだけで素早く復習できる
- 電源不要でいつでも使える
- 机に向かうことで集中力を高めやすい
紙教材の利点は、その「アナログさ」にあります。特に、漢字や計算など「繰り返し書いて覚える」必要のある教科では、紙に書くという動作が記憶の定着に直結します。これは、視覚・聴覚だけでなく、「書く」という身体的な行動を伴うことで、脳の記憶回路がより活性化されるためです。
また、タブレットではスクロールや画面遷移が必要な復習も、紙の教材であればページをさっと開くだけで済むため、効率的に復習しやすいという特徴もあります。ちょっとした隙間時間でも、すぐに目的のページを開いて確認できるのは、紙ならではのスピード感です。
加えて、電源やインターネットが不要であるという点は、家庭内での学習だけでなく、外出先や旅行先などでも安心して使用できるというメリットにつながります。常に安定して使える紙教材は、意外と頼りになる存在です。
通信教育におけるタブレット学習のメリット・デメリット
メリット1:学習のハードルが低くスキマ時間に活用できる
タブレット学習の最大の魅力は、やはりその手軽さにあります。スマホ感覚で持ち歩けるタブレットは、移動中の電車やバスの中、ちょっとした待ち時間など、日常の中に存在するスキマ時間を有効活用できます。この「いつでも・どこでも」学べる柔軟さは、特に忙しい子どもたちにとっては大きな味方となるでしょう。
また、「机に向かわなくても学べる」という気軽さが、学習への心理的ハードルを下げてくれます。これにより、学習の習慣化が自然と進むことも少なくありません。
メリット2:繰り返しの練習が容易
タブレットには、AIによる分析機能や、間違えた問題を自動で再出題する仕組みがあるなど、デジタルならではの学習効率の良さが際立ちます。一度間違えた問題を何度でもやり直せるうえに、すぐに正解が表示されたり、音声やアニメーションで解説されるなど、理解を深める仕組みが満載です。
さらに、消しゴムを使わずに何度も書き直せるという点も、漢字練習や計算練習で便利に感じるポイントです。
メリット3:親の負担が減る
タブレット学習は、親の手間を大幅に軽減してくれます。例えば、自動採点機能によって、親が一つひとつの問題に丸付けをする必要がありません。アプリが学習状況を記録し、子どもの進捗をレポートとして見せてくれるため、親は「見守る」ことに集中できます。
共働きの家庭や、兄弟が多くて時間に追われがちな家庭にとって、このようなサポート機能は非常に助かる存在です。
デメリット:姿勢の悪化・集中力の低下のリスク
一方で、自由度が高すぎるという点が、タブレット学習の落とし穴でもあります。好きな場所で使える反面、学習に適していない環境──たとえばソファーやベッドなど──での使用が増えてしまうと、姿勢が悪くなりやすく、それが身体的な不調の原因にもなりかねません。
また、“ながら勉強”のような集中力が散漫なスタイルが常態化してしまうと、学習効果が低下するリスクも高くなります。ゲームやYouTubeなど、誘惑がすぐ近くにある環境では、どうしても注意が逸れてしまいやすいのです。
通信教育を効果的に活用するためには、タブレット学習の利便性と紙教材の集中力維持のバランスを考え、子どもの学習スタイルや性格に合った方法を選ぶことが大切です。
紙とタブレット、どちらを選ぶべきか?
結論から言えば、通信教育では「紙教材」と「タブレット教材」の両方をうまく活用する、いわゆる“併用スタイル”がもっとも効果的だと管理人は考えています。それぞれに異なる利点があるため、目的や学習内容によって使い分けることで、効率の良い学習が可能になります。
たとえば、次のような方法で紙とタブレットを使い分けることが推奨されます。
- 数学の文章題や記述問題:紙の教材を使うことで、じっくり時間をかけて考える姿勢が育まれます。紙に書くという行為自体が記憶の定着につながり、計算過程や構造を視覚的に確認しやすくなります。
- 英単語や理科・社会の暗記:タブレットなら、音声や映像を使った学習が可能で、ゲーム感覚で楽しく覚えられます。電車の中や待ち時間など、スキマ時間にも手軽に使える点が大きなメリットです。
- 学習の導入:難しい内容に入る前に、タブレットを使ってアニメーションや動画で興味を引き出すと、子どもの集中力が高まります。初めて触れる単元も、視覚と聴覚を刺激することで理解しやすくなります。
- 仕上げや定着:学習内容をしっかり定着させるには、やはり紙に手を動かして書く作業が重要です。復習やまとめの時間に紙のワークを取り入れることで、学習成果を長期記憶に残すことができます。
このように、通信教育に限らず、日々の学習においては「習慣化」が成功の鍵を握っています。その点、紙教材には“学習の儀式性”が備わっており、ノートを開いて鉛筆を持つという一連の動作が、自然と「勉強モード」への切り替えを促してくれます。
さらに、紙に書くというアナログな行為には、脳を活性化させる効果もあるとされています。特に小学生のような発達段階では、タブレットだけに頼らず、紙を使うことで思考力や表現力も育まれていくでしょう。
まとめ:通信教育は紙とタブレットのハイブリッド活用が正解!
この記事では、通信教育における「紙教材とタブレット教材のどちらが良いか?」という疑問に対し、管理人自身の体験や情報をもとに詳しく掘り下げてきました。
結論としては、どちらか一方に偏るのではなく、それぞれの特性を理解した上で使い分ける「ハイブリッド学習」こそが、現代の子どもたちに最適なスタイルだといえます。タブレットは操作性に優れており、子どもが自発的に学習に取り組みやすい一方で、紙教材は集中力や継続力を育てるうえで非常に有効です。
親御さんにとっても、子どもがどこでつまずいているのかが視覚的にわかる紙教材は、学習サポートを行ううえで大きな味方となります。また、タブレットの履歴機能を活用すれば、進捗管理や苦手克服にも役立ちます。
通信教育を選ぶ際には、教材が紙中心なのか、タブレット中心なのか、あるいは併用可能なのかを確認し、お子様の性格や生活スタイルに合わせて選ぶことが重要です。
この記事が、あなたのお子様の学習スタイルを見直すきっかけになれば嬉しいです。ぜひ、紙とタブレットの両方をうまく活かして、無理なく、そして楽しく学びを深めていってくださいね。
ご家庭での学びの時間が、もっと充実したものになりますように。これからの学習、心から応援しています!
(参考)
こんな記事も読まれています。
カートカンのメリット!国産の間伐材を使って森林育成に貢献
⇒https://kamiconsal.jp/cartocanmerit/
コート紙90kgと135kgの違い。重さで何が変わる?
⇒https://kamiconsal.jp/coatedpaper90kg135kg/
紙の発火点は約何度?上質紙で450℃、新聞紙で290℃!
⇒https://kamiconsal.jp/kamihakkaten/