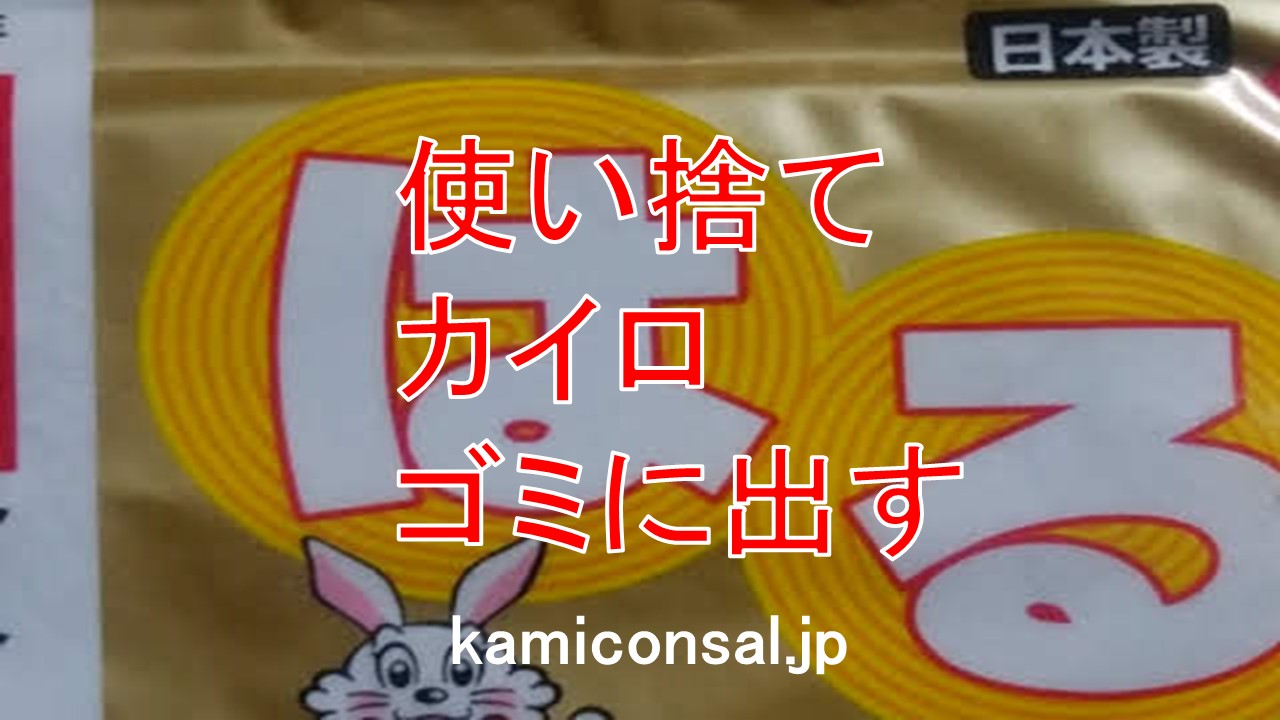この記事は約 10 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回はグリーンマークの
コピー用紙について。
グリーンマークってあるんですよね。
コピー用紙にマークが入ってたりします。
以前勤めていた製紙会社では
グリーンマークではなくて
エコマーク取得については
よく聞いたんですよね。
特に官公庁向けのコピー用紙は
エコマークを取得しないと販売できないとか。
管理人にはグリーンマークとエコマーク
何がどう違うのかよく分かりませんでした。
なんとなく環境に優しいとか、
古紙をたくさん配合しているとか
それでどこかの団体に申請して
認可してもらえれば名乗れる感じ。
ただ古紙配合率については
色々変更もあったみたいで
管理人が関係していた頃とは
変わっているのかも知れません。
それで今どうなっているのか
もう一度確認してみたいと思います。
ということでこの記事では
グリーンマークのついたコピー用紙や
似たようなイメージのエコマークについて
自分なりに調べたことをお伝えします。
グリーンマークのコピー用紙 古紙配合率は50%以上
<グリーンマークの定義>
そもそもグリーンマークは何なのか?
まずはここからですよね。
それでウィキペディアを確認しました。
==ここから==
グリーンマークは、古紙を原料に
再生利用した製品のための目印である。
環境ラベリング制度の一つ。
古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルの
促進を図ることを目的としている。
1981年に財団法人
古紙再生促進センターが制定した。
もともと、「古紙=粗悪なもの」
というイメージがあったため、
古紙利用製品に対する消費者の
イメージ向上を目的としてスタートされた。
しかし初期の頃はなかなか普及せず、
トイレットペーパーやちり紙などにしか
利用がなかった。
1980年代の終わりから、
社会の環境保全活動が活発となったことから、
古紙利用が見直され、
グリーンマークの表示製品も
増えてくることとなった。
(設定基準)
古紙を原則40%以上利用した製品に
表示が許される。
ただし、
トイレットペーパーとちり紙は100%利用、
新聞用紙とコピー用紙は50%以上利用。
==ここまで==
ということです。
グリーンマーク自体は
元々古紙配合品は粗悪品
というイメージを払拭するために
作られたもののようですね。
元製紙会社社員としての
正直な話をすると、
紙は白いものが良い紙だ
という考えが根強いです。
だから白色度が上がらない
古紙なんて入れたくはない。
古紙を入れるのはボロ紙の
新聞とか更紙とか段ボールで
上質紙とか高白色のコート紙に
入れるのは邪道だ
というのが上質系の紙に
関係していた技術者の本音です。
どうして色が白いもののを
わざわざ黒くしないといけないのか?
製造する側も使う側も
こういう意識は共通していたと思います。
現在はどうか分かりませんが、
あまり変わっていないんじゃないでしょうか。
少なくともグリーンマークは
そういう意識を改善したい制度なんですね。
それでその基準は古紙配合率40%以上。
ただし、
トイレットペーパーとちり紙は100%利用、
新聞用紙とコピー用紙は50%以上利用。
ということなんですね。
これが制定された1981年当時、
環境保全のために
上質紙に古紙を配合するという
考え方がなかっただろうと思います。
当時は品質重視で無理はしない、
という感じだったと思うんです。
もしもそうならこの基準、
技術的には結構緩いです。
元々古紙配合品である
新聞紙、トイレットペーパーやちり紙は、
既存品の状態で
古紙配合率をクリアしていたはずですし、
中質紙や更紙も古紙配合率40%は
十分対応できるレベルでした。
コピー用紙だけは歴史的に新しいので
高白色の古紙を使用することを想定して
配合率が設定されている感じで、
これも技術的に可能なレベルだと思います。
しかしこれを上質紙にも適用するのは
無理があると思うんですよね。
そもそも上質紙の定義は
バージンパルプ100%なんですから。
環境のためということで
品質を無視して基準を決めたら
ろくなことにならないなというのが
技術者の本音です。
<エコマークの定義>
次はエコマーク。
これもウィキペディアで確認してみます。
==ここから==
エコマークは、環境保全に役立ち、
環境への負荷が少ない
商品のための目印である。
環境ラベリング制度のひとつ。
消費者が、暮らしと環境との
関係について考えたり、
環境に配慮された商品を
選ぶための目安として
役立てられることを目的としている。
このマークは、環境省所管の
財団法人日本環境協会によって
1989年に制定された。
現在は、国際標準化機構(ISO)
環境ラベル表示のType1として
運営されている。
使用するには、
協会の認定及び契約が必要となる。
また、エコマークは、財団法人
日本環境協会の登録商標でもある。
==ここまで==
ということです。
エコマークは取得条件が
とてもややこしい。
コピー用紙については
基本的に古紙配合率70%以上で、
森林認証パルプや間伐材等パルプ、
持続可能性を目指した原料
も配合してもよい
という感じになっています。
エコマークについては
古紙配合品のイメージ向上とかではなく、
完全に政策として環境省主導で
始まっていますから
かなり無理のある
基準になっているように思います。
管理人にはグリーンマークは製紙会社や
ユーザーの現実を見て制定されているが
エコマークはお役所が
無理やりやらせている感じがするんです。
特にエコマークはこれを取得しないと
役所に事務用品は売れないので
各製紙会社はかなり
大変だったのではないかと思います。
それで日本製紙の古紙配合率偽装、
というような不祥事も起こったんだろうなと。
古紙配合率100%のコピー用紙は出来るのか?
ここからは元製紙会社社員として
本音をお話させて下さい。
古紙配合率100%のコピー用紙なんて
出来るんですか?
というのが率直な疑問なんですが
これ原料があれば出来るんですね。
管理人はコピー用紙ではありませんが
それとほとんど同じような紙で
古紙100%のインクジェット用紙の
開発に関わったことがあります。
これだけ古紙の高配合は
無理だと書いておきながら、
そういう紙の開発もやってましたし、
商品化もしたんですね。
それは日本製紙の古紙配合率
偽装事件が発覚する前のこと、
ほとんどのメーカーが古紙配合率を
偽っていた時期に本当に古紙100%の
普通紙タイプのインクジェット用紙を
生産していました。
それもプリンタメーカーの純正品として
採用されてたんですね。
だから古紙配合率100%のコピー用紙は
作れるんです。
しかし先程お話しましたが原料の確保が問題。
その高白色の古紙パルプを
どうやって大量に確保するのか?
管理人の担当していたときは
一番小さな抄紙機で
古紙パルプの供給が
間に合うように生産量を落として
短時間だけ抄造するということで
どうにか原料を確保していました。
古紙設備のないメーカーでも
古紙100%品を製造していますが、
そういうところは多分古紙パルプを
購入していると思います。
しかしそれではコストが合わないだろう、
というのが正直な感想です。
管理人のまとめ
今回はグリーンマークのコピー用紙
についてお伝えしました。
グリーンマークとエコマーク
似ているようですが
制度の主旨も管轄している団体も
古紙配合率の条件も違うんですね。
それから古紙配合率100%のコピー用紙は
技術的には可能なんですが
実際に生産して採算を取るのが
大変だろうなと思っています。
いずれにしても。
資源のリサイクルは社会の問題で
今後後戻りすることはないでしょう。
しかし環境問題というのは製造会社に
かなり無理をさせているのも事実。
この記事を読んで本当の意味での
環境問題を考えるきっかけになれば
本音を書いた意味もあるかなと
思っています。
環境問題やリサイクルとは
上手く付き合いましょうね!