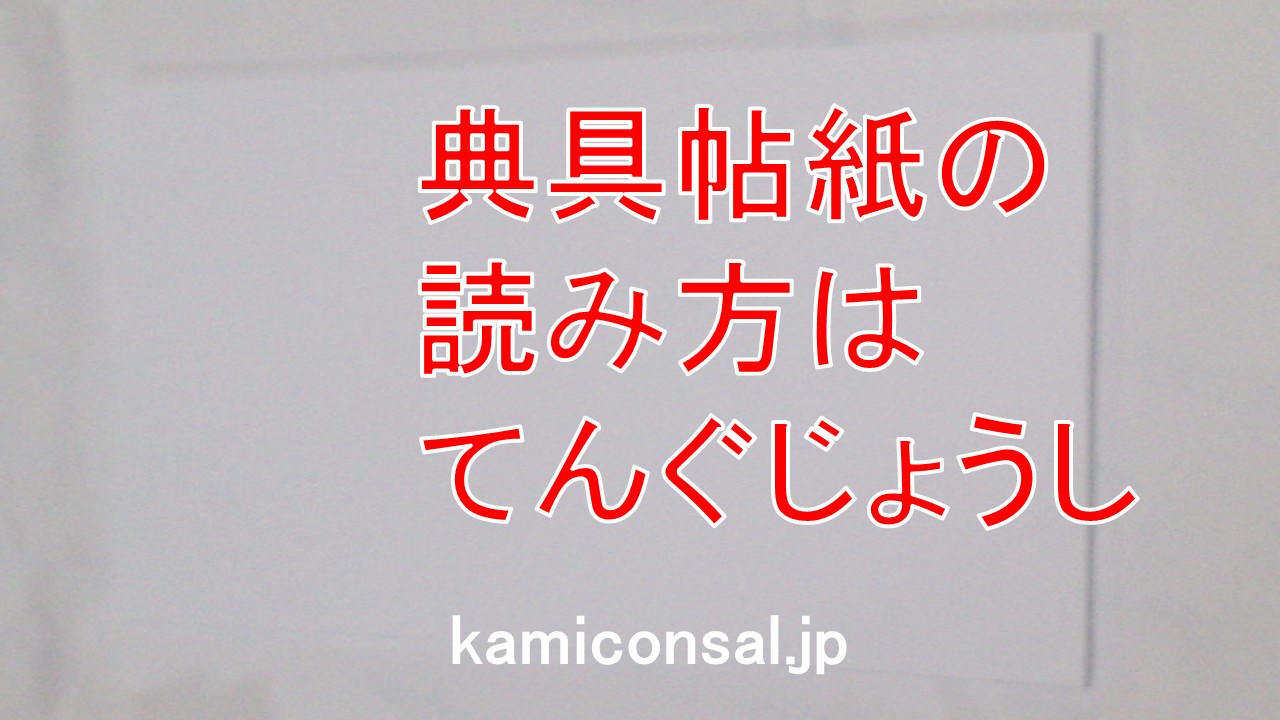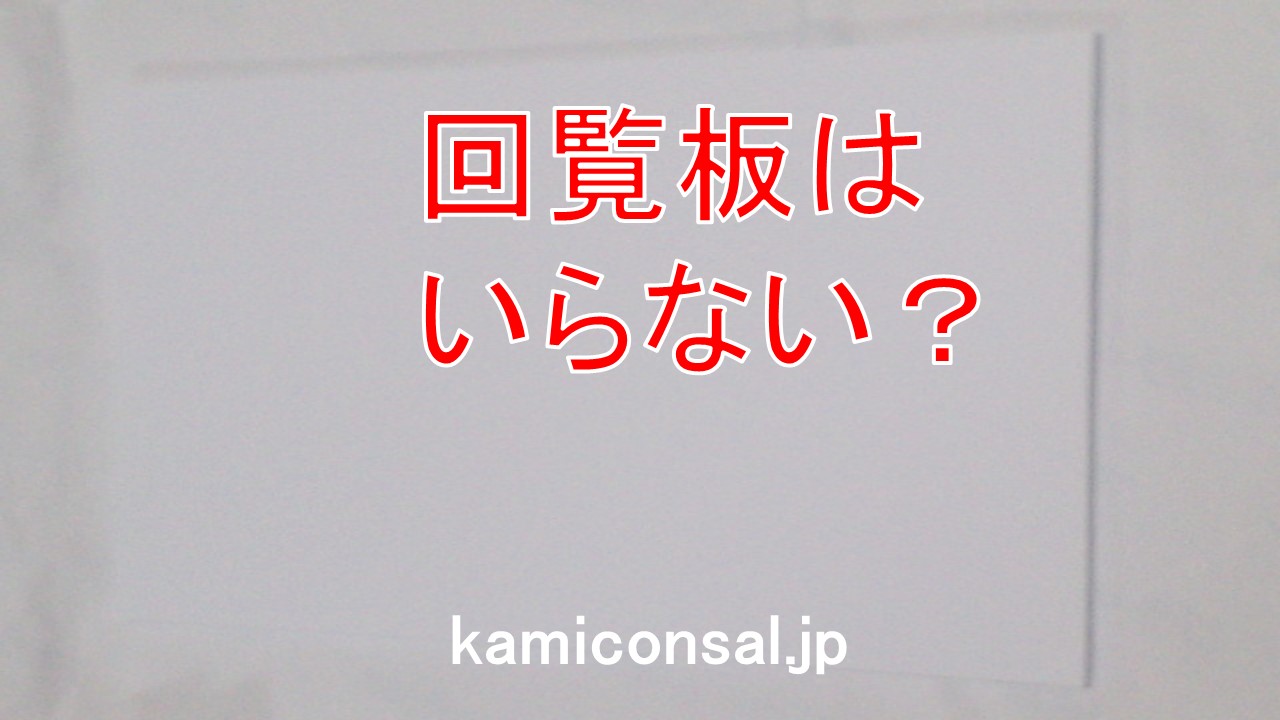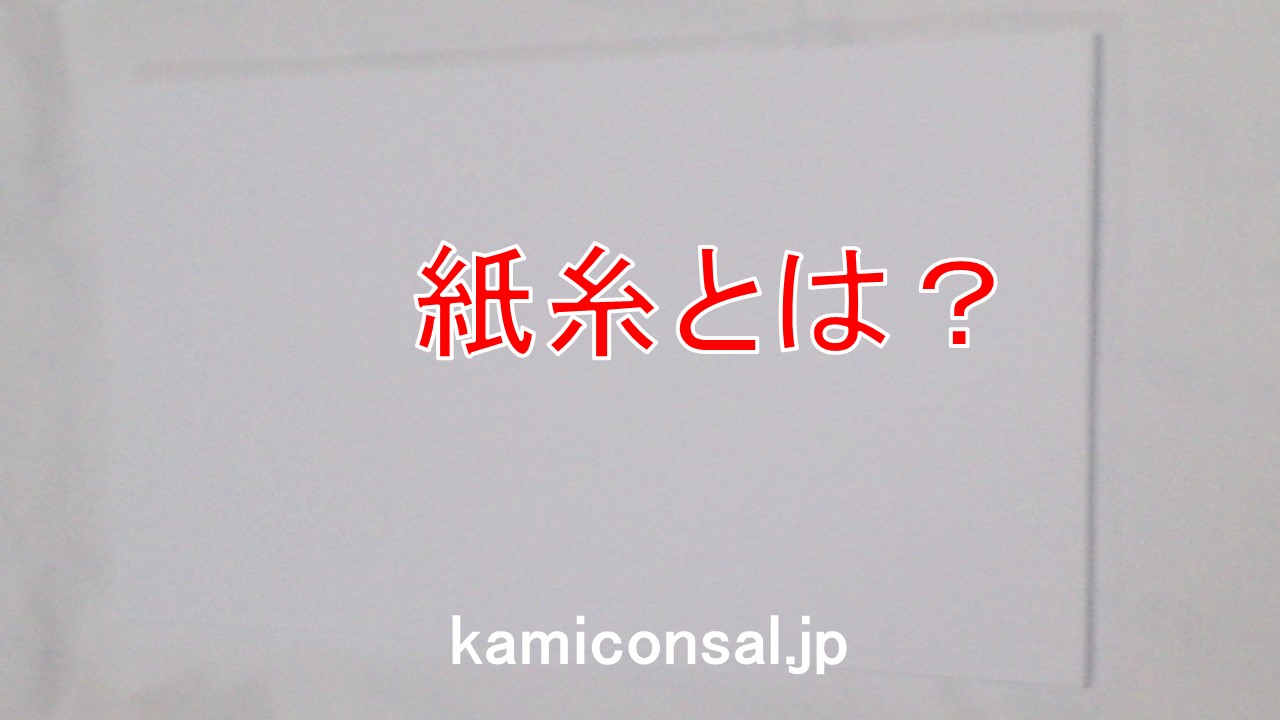この記事は約 9 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、典具帖紙の読み方はてんぐじょうし。
美術品の修復に欠かせないというお話。
管理人、図工の成績は「2」なんですが
美術品の修復作業には興味があります。
純粋にすごい技術ですからね。
古いものを残すというだけでも
尊いものだとおもうんですよね~
で。
そういう古文書とか絵画とかの
修復に使われるのが和紙。
その耐久性は抜群ですから。
その和紙の中でも有名なのが
典具帳紙なんだそうです。
読み方は、「てんぐじょうし」
管理人的には「帖」の文字が
馴染みがなくて読みにくかったか。
まあ読み方としてはそんなに
難しいところはないですかね。
それはそうとして。
この典具帖紙がどんなものか
気になったんですよね~
なので少し調べてみようかなと。
ということで。
この記事では典具帖紙の読み方は
てんぐじょうし。美術品の修復に欠かせない
について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
典具帖紙はどんな紙なのか
まずは典具帖紙についてですが、聞き慣れない方も多いかもしれません。典具帖紙(てんぐじょうし)は、非常に薄くて繊細な和紙の一種で、主に美術品の修復や保存など、専門的な分野で使われる紙です。最近では一般の人でも手に入れやすくなっていて、アマゾンなどのオンラインショップでも販売されています。
とりあえず、Amazonで検索してみたところ、しっかり取り扱いがありました。
これですね。
商品名にもある通り「土佐」と記載されていることから、高知県の特産品として知られているようです。もともとは美濃和紙として作られていた技術が土佐に伝わり、独自に発展したとされています。そう考えると、地域ごとの伝統技術の受け継がれ方にも興味が湧いてきますね。
ちなみに高知県には、ニッポン高度紙工業株式会社のように、極薄の紙を得意とする企業も存在しています。そういった背景もあり、薄くて丈夫な紙の製造技術が地域全体で高い水準にあるのかもしれません。
それで、典具帖紙の最大の特徴は「世界一薄い和紙」として知られていることです。
管理人が調べた範囲では、米坪9g/㎡、厚さ20μmという数値がよく引用されています。これはあくまで一例であり、製造ロットや製法によってはさらに薄いものも存在するそうです。たとえば、米坪2g/㎡という超極薄タイプもあると聞きます。
ここで「20μm=0.02mm」という厚さがどれくらい薄いかイメージしやすい例を挙げましょう。トイレットペーパーの厚さがだいたい50μm、つまり0.05mm程度です。ティッシュペーパー1枚はさらに薄く、約0.04mmとされています。
つまり典具帖紙は、ティッシュ1枚のさらに半分の薄さしかないということになります。あのペラペラなティッシュでさえ薄いと感じるのに、それをさらに半分にした厚さの紙が存在して、それが実際に使われているというのは驚きですよね。
管理人は以前、一般的な紙を製造する仕事に関わっていた経験がありますが、その立場からすると、このような超極薄紙の存在はまさに驚異的で、とんでもなく繊細な技術だと実感します。
ここまで薄いからこそ、美術品や文化財の修復の際に、対象物の上から貼り付けても視認できないレベルで自然に仕上がるわけです。見た目を損なわず、しかも補強や保護の役割を果たすことができる、まさに「すごい紙」だと感じます。
土佐典具帖紙の製造工程
土佐典具帖紙の製造工程についてですが、これも非常に丁寧で手間のかかる伝統技術です。
製造の詳しい流れについては、以下のサイトに詳しく掲載されています。
ひだか和紙HP
⇒https://www.hidakawashi.com/jp/tengu/process.html
また、文化遺産オンラインにも製造方法についての解説が載っており、非常に参考になりますので、以下に一部引用しておきます。
==ここから==
土佐典具帖紙は、極めて薄く、かつ強靱な楮(こうぞ)和紙の製作技術である。明治初期に高知県に技術が導入されて発達した。仁淀川流域で生産される地元産の良質な楮を原材料とし、消石灰で煮熟(しゃじゅく)(地元では灰煮(はいに)という)した後、小振(こぶり)洗浄、ちり取り等の入念な原料処理を行い、不純物を除去して用いる。極薄の紙であるためわずかな塵の混入も許されず、丁寧な原料処理が行われる。トロロアオイのネリを十分にきかせた流漉(ながしずき)で、抄紙(しょうし)の工程では、渋引きの絹紗を張った竹簀(たけす)及び檜(ひのき)製漆塗の桁を使用し、簀桁(すげた)を激しく揺り動かして素早く漉き、楮の繊維を薄く均一に絡み合わせる。漉き上がった紙は「カゲロウの羽」と称されるほど薄く、繊維が均一に絡み合って美しく、かつ強靱である。
==ここまで==
実際にひだか和紙の公式サイトを見て感じたのは、まず第一に原材料の選定と処理の丁寧さです。原料の楮は地元で栽培された高品質なものを使い、消石灰で煮熟してから不純物を一つ一つ取り除くという工程は、普通の紙づくりとは一線を画す徹底ぶりです。
特に、極薄の紙をつくる場合は、抄紙の技術だけでなく、その前段階である原料処理が極めて重要です。通常の紙では多少の異物や繊維のムラがあっても問題にならないことが多いのですが、典具帖紙のような極薄の紙では、そのわずかな不純物すら大きな欠陥になってしまいます。
だからこそ、手作業で何度も確認をしながら、異物やゴミを徹底的に取り除いていくという地道な工程が欠かせません。そういった丁寧な仕事があってこそ、完成した紙が美しく、かつ丈夫で、修復に使っても違和感がない品質を保てるのです。
現代のように効率とスピードが求められる大量生産の現場では、まず考えられないほどの時間と手間をかけた工程です。その反面、人の手による丁寧な仕事だからこそ生まれる美しさと信頼性があります。
こうした伝統技術の価値は、決して数字や生産量だけでは測れないものだと、改めて実感しました。効率一辺倒ではなく、時間をかけて良いものを作る姿勢こそが、典具帖紙の魅力であり、尊さでもあると感じます。
それで。
この典具帖紙を使った修復作業の
動画がありました。
この動画を見ればどれほど紙が
薄いかがよくわかりますね~
管理人のまとめ
今回は典具帖紙の読み方はてんぐじょうし。
美術品の修復に欠かせないというお話でした。
典具帖紙の読み方は
「てんぐじょうし」
土佐が有名なんですね。
とても薄くて丈夫な紙で美術品の
修復などに使われるんだとか。
管理人は美術品のことはさっぱりですが
この修復ってすごいなと思っています。
そして典具帖紙のこの薄さ。
もと製紙会社社員としては
驚くべき薄さなんですよね。
トイレットペーパーや
ティッシュペーパーの
厚さの半分と言われたら
やっぱりすごい技術だと。
こういう技術は長く残って
古いものの補修に使ってほしい。
本当にそう思いますね~
この記事が、典具帖紙の読み方の
参考になればと思います。
典具帖紙、すごい紙ですね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
印刷の刷り順について。オフセット印刷が墨藍紅黄の理由は?
⇒https://kamiconsal.jp/insatusurijun/
熱転写用紙はインクジェットでは使えない!その理由はナニ?
⇒https://kamiconsal.jp/netutensyayousiinkjet/
新聞紙が灰色の理由?原料、価格、品質の面から説明します!
⇒https://kamiconsal.jp/shinbunshihaiiroriyu/