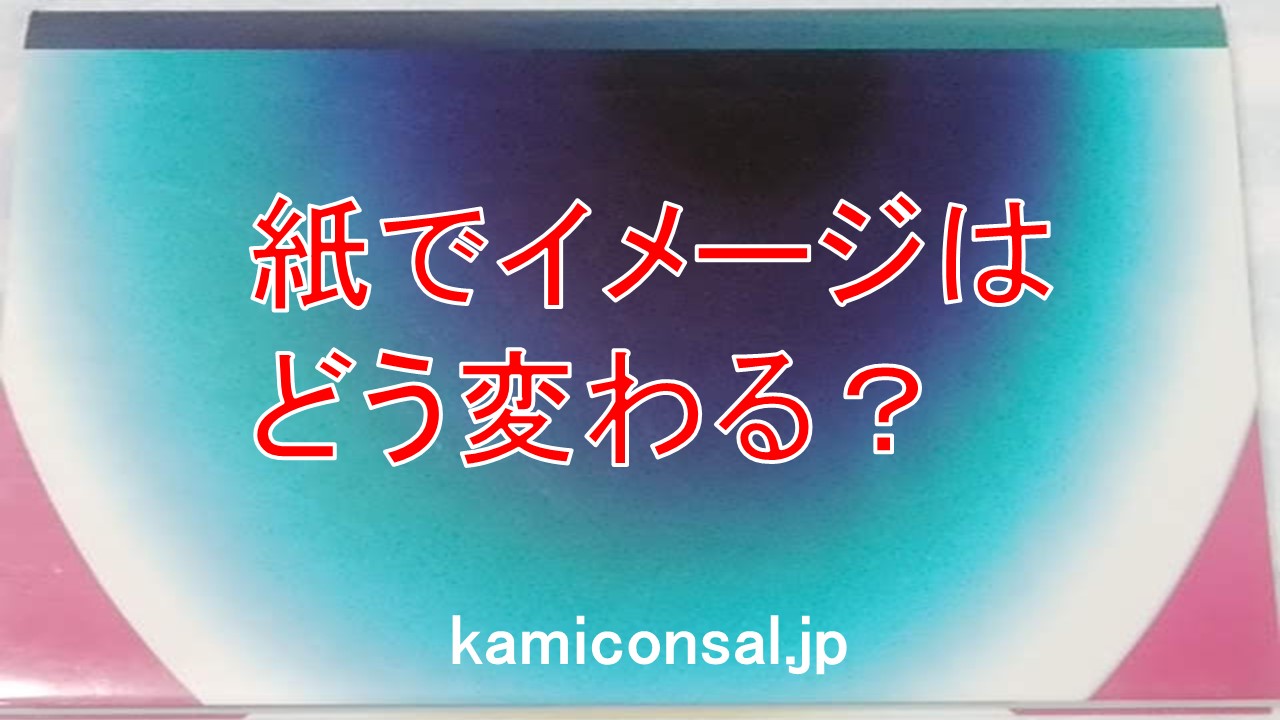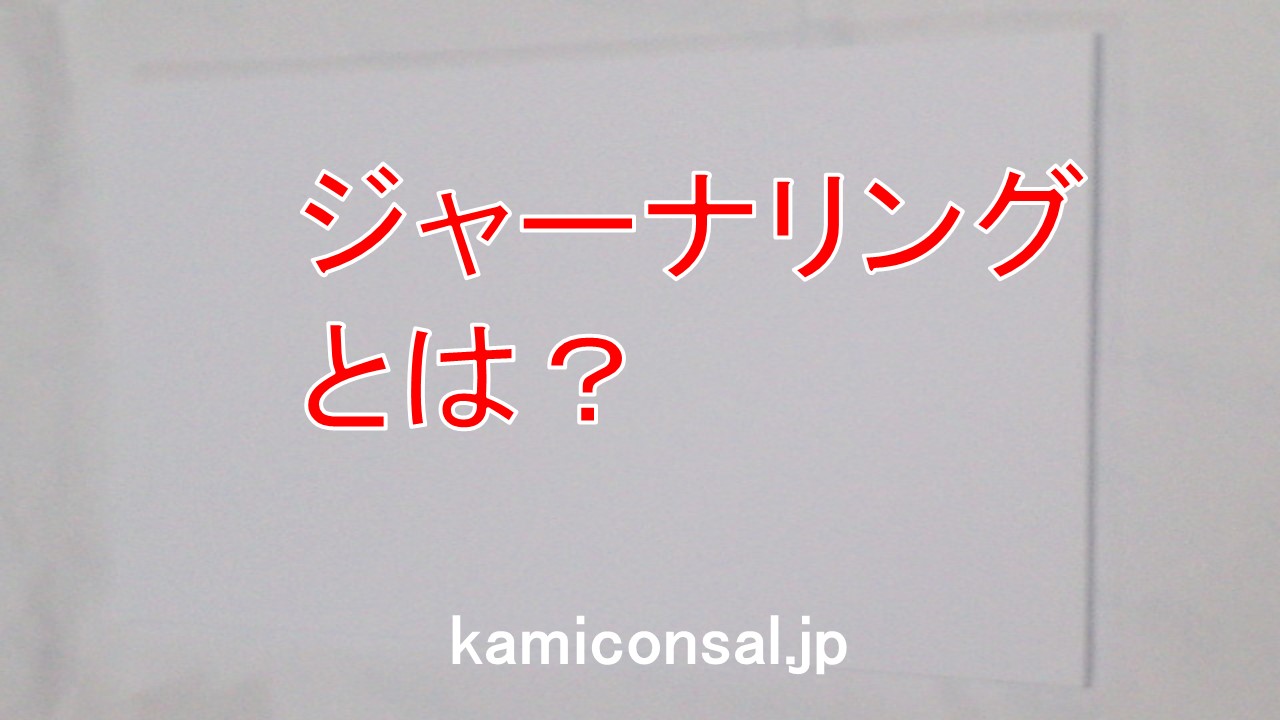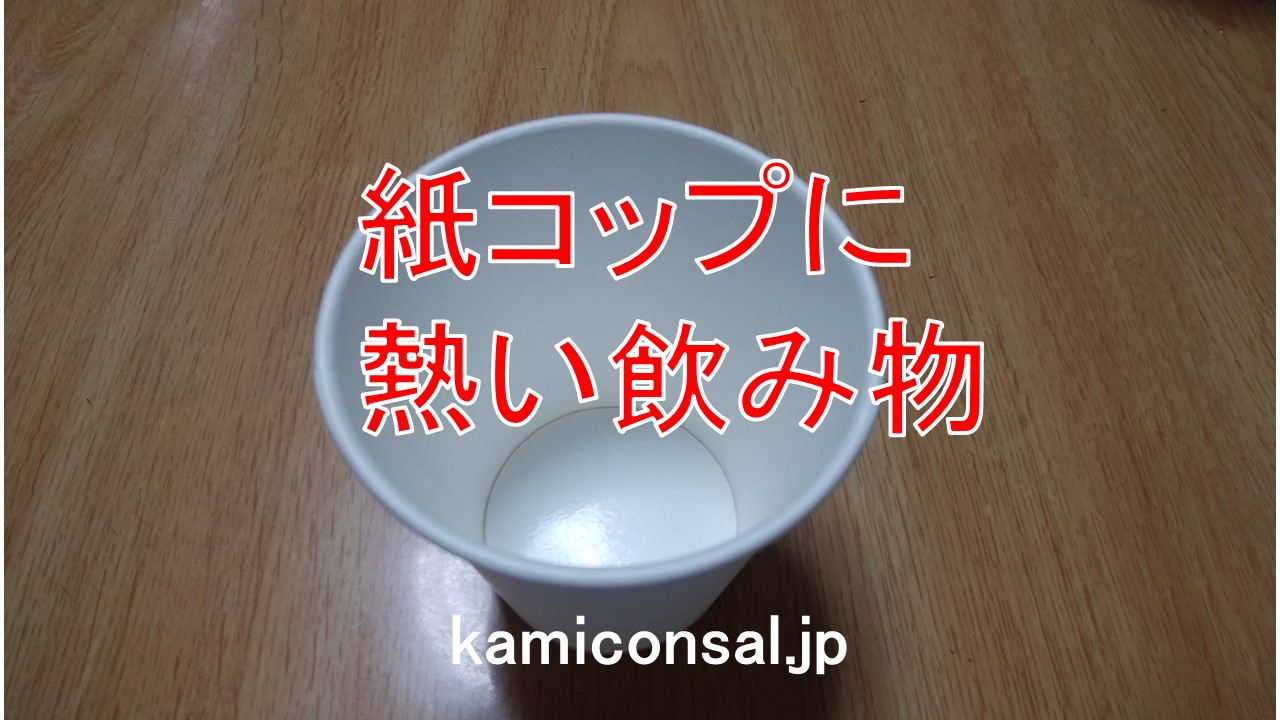この記事は約 13 分で読めます。
![]()
管理人の紙コンサルこと、べぎやすです。
今回は、紙でイメージはどう変わる?
厚みのあるマット紙で高級感演出
というお話。
管理人は元製紙会社社員。
市場のニーズに合わせた紙を作る
という仕事をしたこともあります。
実際には工場で製造する側で
営業のいいなりでしたけど。
「こんな紙を作ればここに売れる」
みたいな話はよく聞かされました。
上手く対応できたものもあれば
どうしても出来なかったものもある。
紙なんて今更何するの?と言う感じですが
それでも新しいニーズへの対応があった。
地味ですけどね~
それはそうとして。
管理人が担当した印刷用紙でも
チラシや本に紙を使うとき
その紙がユーザーに与える
イメージはとても重要でした。
高級感を与えるか、安売り感を与えるか。
儲かっている感じを与えるか
儲かっていない感じを与えるか。
驚くべきことに安っぽい紙にも需要がある。
いい紙を作りたい側からすると
「何で?」と思いますけど。
ということで。
この記事では、紙でイメージはどう変わる?
厚みのあるマット紙で高級感演出について
管理人が調べたことを
お伝えしたいと思います。
紙でイメージはどう変る?内容とのマッチングが重要
それでですね。
紙によってどのようにイメージが変わるかという点ですが、これは実際には非常に奥深くて重要なテーマになります。
一般的な話から始めると、まず「高級感」を出したいときには、どのような紙が適しているのかという話になります。
わかりやすいポイントとしては、
- 紙にしっかりとした厚みを持たせる。
- 質感が落ち着いて見えるマット調の紙を選ぶ。
- 印刷に際しては、光沢の高い加工が可能な紙を使う。
といったところです。これは、視覚的にも触感的にも「上質さ」を演出するための基本になります。
では逆に、あえて「安っぽく」見せたい場合やコスト重視の場面ではどうか。
その場合には、
- 厚みのない薄手の紙を使用する。
- ギラギラとした光沢感が目立つ表面加工。
- 印刷面の光沢感が乏しい紙を選ぶ。
といった点がポイントになります。これは、感覚的に“軽くて安い”という印象を持たせるための手法です。
もちろん、これらはあくまで一般的な傾向であり、全ての場面において当てはまるわけではありません。
それに、紙の厚さや薄さには、JISなどの基準に基づく規格があるため、基本的にはその規格に従って紙は製造されます。
ただし、たとえばギラギラした光沢感や、印刷時の光沢をあえて落とすといった処理を“わざと”行うことはあまりなく、それは製造の過程や素材の選択によって自然と生じるものです。
とはいえ、そうした“特徴”が逆に評価されるケースもあるので、不思議な世界だなと感じることもありました。
話を紙のイメージに戻しますが、高級感のある紙の典型的な使用例として挙げられるのは、写真集やカタログなどでしょう。
特に自動車メーカーの高級カタログに至っては、最高ランクのアート紙を使用していることが多いです。
私が勤めていた会社では、それを「ダルアート紙」と呼んでいましたが、業界全体としても「スーパーアート」や「ダルアート」といった名称で流通しています。
この紙の特徴としては、厚みがあり、紙自体の白色光沢は低めで落ち着いたマット調。そして、印刷面の光沢は非常に高いため、印刷物が紙面から“浮き上がって見える”ような印象を与えます。
まさに、紙の質感と印刷効果が絶妙にマッチした仕上がりになるわけです。
写真集については、内容や価格帯によって幅がありますが、美術品を扱ったものにはこの種の紙がよく使用されます。
自動車カタログや高級アートブックは、そもそも商品価格が数十万円から数百万円と高価であるため、それにふさわしい紙が求められるわけですね。
紙そのものの製造コストは確かに高くつきますが、販売価格も高いため、ビジネスとしては魅力的な案件です。
ただし、その分トラブル時のリスクも高くなりますので、扱いには慎重さが求められます。
私自身は後発メーカーに勤めていたため、そうした高級案件に携わる機会は少なかったですが、業界の動向としては常に注目していました。
さて、ここで逆の立場の紙についても見ていきましょう。
分かりやすい例として挙げられるのが、スーパーマーケットのチラシです。
昔は「キザラ」と呼ばれる紙に、赤い極太文字で「大安売り」などと書かれたものが主流でした。
今もそのようなチラシはありますが、かなり少数派になってきています。
現在主流になっているのは、薄手のコート紙です。具体的には、A3コート紙と呼ばれるタイプです。
その他にも微塗工紙という選択肢もあります。
一般的には、米坪(紙の重さ)は64g/㎡から81.4g/㎡程度の範囲で、かなり軽く、手に持った時の感触もペラペラです。
また、白紙光沢を高めるための塗料が薄く塗られているため、表面にムラが出やすく、結果としてギラギラとした光沢になる傾向があります。
塗工量が少ないため、表面が十分にカバーされておらず、印刷光沢も高くはなりません。
つまり、印刷された文字や画像が“沈んで”見えるような感じになるのです。
ただし、この「安っぽさ」が実はスーパーのチラシには好都合とされています。
もしも高級カタログのようなダルアート紙でチラシを作ってしまったら、逆に違和感を覚えてしまう人も多いでしょう。
数十円、数百円の価格帯の商品を並べたチラシが、豪華すぎて近寄りがたい印象になるのは本末転倒です。
だからこそ、スーパーのチラシには薄手のA3コート紙が使われるのです。
もちろんコスト面の理由も大きいですが、それ以上に「イメージの整合性」が重要視されています。
私が業界にいた頃は、ちょうどこの薄手コート紙が急速に広まっていた時期でした。
紙自体は安くても、需要が多くて売れ行きは好調だった時代ですね。
紙でイメージはどう変わる?履歴書は厚みのあるものを!
この話題は、過去にもこのブログで何度か触れてきましたが、改めて書いておきます。
履歴書や契約書など、大切な書類に使う紙の選び方についてです。
最近はペーパーレス化が進んでおり、求人応募でもPDFでの提出が増えましたが、まだまだ履歴書を紙で提出する企業も多くあります。
このような場合、使う紙には十分な注意が必要です。
たとえば、安価なコピー用紙のような薄い紙を使用すると、自分の印象を下げてしまうリスクがあります。
採用担当者の側からしても、手に取った瞬間に「軽い印象」を持ってしまうかもしれません。
大切な書類だからこそ、しっかりとした厚みと質感のある紙を使うことが求められます。
印象というのは、文字の内容だけでなく、紙質などの物理的な要素でも大きく左右されるものです。
指定がない限りは、市販の標準的な履歴書用紙を使うのが無難です。
たとえば、以下のような製品がそれに該当します。
日本 日本法令 法令 履歴 書 jis 規格 説明 書付 a 4 履歴 書 用紙 4 枚 シール 付 封筒 3 枚 職務 経歴 書 3 枚
このような製品は、上質紙を使用しており、コピー用紙よりも厚みがあるため、手に取った際の印象が全く違います。
履歴書というのは、応募者の「顔」となる書類ですから、内容ももちろんですが、紙選びも大事な要素になるのです。
紙によるイメージ操作。わざと紙質が悪そうな紙を使う場合も?
ここまで、紙質が与えるイメージと用途のマッチングについて解説してきました。
ところが中には、「わざと」安っぽく見せるために紙質の劣る紙を使うという、特殊なケースも存在します。
私が経験したもので印象に残っているのは、お役所関係、正確には外郭団体のようなところからの発注です。
公共性の高い事業では、「利益を出してはいけない」「豪華すぎると批判される」といった社会的なイメージがあるため、あえて安っぽい紙が求められるのです。
購入価格そのものは高くてもかまわないが、見た目に高級そうでは困るという、なんとも複雑な要望でした。
私が担当していた紙が、まさにその用途で使われました。
採用されたのは、中質微塗工紙で、マット調の質感でした。
文字や数字が多く印刷されるため視認性を重視し、印刷は沈むような仕上がり。
白色度も低く、全体的にくすんだ印象を与える紙でした。
技術者としては、こういったニーズには正直釈然としませんでしたが、確かに“売れる”紙でもありました。
似たような事例としては、古紙入り用紙の白色度をあえて下げて欲しいというリクエストもありました。
品質が良すぎると「これは古紙が使われていないのでは」と疑われるため、あえて見た目を落とすというケースも存在します。
私は常に、「良いものを安く提供することが誠実な仕事」と考えていましたが、現実にはそうした“見た目のコントロール”も求められることがあるのです。
とはいえ、そうした要望は長くは続かず、最終的には商品や用途に応じて、適正な紙を選ぶスタイルへと戻っていきました。
管理人のまとめ
今回は「紙でイメージはどう変わるのか」というテーマで、厚みや光沢、紙質の違いがもたらす視覚的・心理的な影響についてご紹介しました。
基本的には、商品やサービスの内容に見合った紙を選ぶのが最も重要です。
高級品を扱うカタログや写真集であれば、厚手でマット調、印刷が引き立つ光沢紙が適しています。
一方で、スーパーのチラシのように価格重視で大量配布するものには、薄手でギラギラした光沢紙が合います。
履歴書や契約書のように信頼感や誠実さが求められる書類には、しっかりとした厚みのある上質紙が無難です。
また、文章量や画像の量によって、マット紙か光沢紙かを選ぶのもポイントです。
さらに、公共性の高い団体などでは、儲かっていないことを印象づけるために、あえて“安っぽい紙”を使うという逆転の発想もあります。
紙というのは単なる印刷素材ではなく、その選び方ひとつで印象や信頼感、商品価値までも左右する大事な要素なのです。
目的や狙いに応じて、適切な紙を選ぶようにしましょう。
この記事が「紙でイメージがどう変わるか」を考えるうえで、少しでもお役に立てば幸いです。
ぜひ、使う紙をうまく選んでくださいね!
(参考)
こんな記事も読まれています。
漫画本に酸性紙が多い理由。変色よりも厚みが大事だから?
⇒https://kamiconsal.jp/mangahonsanseishi/
クロスにポスターを貼る!どちらも傷つけない方法はあるか?
⇒https://kamiconsal.jp/crossposterharu/
インクジェットの退色。シールの印字が消える対策はコレ!
⇒https://kamiconsal.jp/inkjettaisyoku/